|
11.神馬に蟹の精 インドはおとぎの国
5月16日 薄曇 マドゥライ 〜 ティルチラパッリ
疫病から復活した僕は、午過ぎにホテルを出て、元気はつらつバス・スタンドへ向かった。訊いてみると、ちょうど目の前のバスがティルチラパッリ行きだった。飛び乗るとすぐに動き出した。今日はついてる。22ルピーで座席はリクライニング、益々今日はついてる。但しちょっとでも叩くとシートから埃が濛々と出た。掃除しろよなあ。荷棚も埃だらけで、荷物も汚れた。『スーパー・デラックス』と書いてあるが、『スーパー・ボロックス』に改名した方が良さそうだ。これは旅行会社の高いバスでもそうだ。
前の席にいると、あと何キロという標識も見えるので、降りる時は自分でわかる。「今日は自分でわかったぞ」と得意になって降りようとしたが、ティルチラパッリ直通便で、ここが終点、みんな降りた。インド人のいけないところは、降りる三十分前にはもう出口に殺到していることだ。お陰でこっちが身動き取れなくなってしまった。出口に一番近い場所にいたというのに、結局荷物を下ろすのに手間取り、最後に降りた。
バス・スタンドで寄って来たリクシャー・ワーラーにホテルまで連れて行ってもらう。あとで散歩してわかったことだが、わざと遠回りして20ルピーも取りやがった。バス・スタンドまでほとんど直線で、歩いて十分もかからなかった。
おまけに明日の観光三カ所の寺院を貸しきりで回らないかと言う。値段を訊くと500ルピー! 問題外。「早く出て行け」と言うと、「テスト・プライスだ」と言いながらどんどん値段を下げていく。200ルピーまで下がったところで、こっちが思っていた値段になった。明日の朝からチェックアウトの時間まで三カ所回れるのはリクシャーならではだ。そこで、渋々という顔をして雇うことにした。
このホテルは60ルピーと安かったが、完全なインド人向けホテルで、のんびりしている。家族でやっているみたいで、まずお婆さんがフロントで番をしていて、これが要領を得ない。言葉も全く通じない。何だかんだ言ってるうちに、やっとのことでおかみさんを呼んで来た。だったら最初から呼んで来いよ。
このおかみさんは宿帳ものろのろと書いていたが、人当たりは好く、言葉も通じた。インドの街を歩いていると、ほとんど男ばかりがうろうろしていて、男ばかりの国かと錯覚してしまいそうになる。女性は家庭にいるものだそうで、働いている女性もあまり見かけないが、南の方に来ると女の人も普通に働いていて、よく外も出歩いている。概して北インドの方が古い慣習を頑なに守り続けているような気がする。
このおかみさんに尋ねてみると、このホテルにはレストランはないそうで、別のホテルのレストランを教えてくれた。行ってみると、メニューがない。子供のボーイがやって来たので、「何がある?」と訊くと、「ロースト」しかないと言う。選択の余地もないので、「じゃあそれ」迷わなくて便利だ。「いくら?」と訊くと、「9ルピー」安い。日本円にすると30円くらいだ。ミールスより安い。これなら小学生のお小遣いでも立派に食っていけそうだ。今日はやっぱりついてるぞ。
まずバナナの葉をテーブルの上に拡げたので、似たようなものだろうと思っていると、馬鹿でかいドーサーがやって来た。ドーサーというのはチャパティとは違い、薄っぺらい堅めのホットケーキみたいな食べ物だ。直径30センチメートルくらいあるのをくるりと巻いてある。これをちぎって(無論丸かじりしようと当人の勝手だが)、カレーにつけては食べる。ちょっと甘みがあり、僕の舌ではカレーとはあまり合わなかった。
そうだ、思い出した。アーマダバードで食べた『マドラシ・ディッシュ(マドラス風料理)』とは確かにこの『ロースト』だったはずだ。
ボーイが「も一つどうだ」と言う。しかし一枚で腹一杯になってしまったのでやめた。本当に今もってインドの物価というものがはっきりと把握できない。一時わかってきたつもりでいたものの、もっと長くいるとまた混乱してきた。このローストもそうだが、ダウラタバードの彫刻とか、カニャークマリの藁人形とか、本当に儲けがあるのだろうか? それとも他がボり過ぎてるのか?
ホテルは純インド式で、シャワーも庭にある。もう日が暮れかけていて、暗いシャワールームでシャワーを浴びた。ルームと言うほどの代物ではない。日が沈むと蚊がいっせいに発生した。シャワールームから部屋に戻るまでの間に、吸血鬼どもにさんざん血を吸い取られた。
部屋に戻ると吸血鬼どもがわんさと不法侵入していた。窓を閉めると暑くてたまらないので、蚊取り線香の出番となる。窓の下と入口と、二つ焚いた。来るなら来てみろ、吸血鬼どもめ。
ようやく治った僕の病気は、結局医者に診てもらわなかったので、はっきり何だったか病名はわからないが、たぶん赤痢だったろうと思う。しかしこの熱帯地方の蚊には更に気をつけなければならない。刺されるとマラリアになる可能性があるからだ。
途中で出会った人から聞いた話だが、その人はマラリアにかかった日本人旅行者にホテルでたまたま出会ったそうなのだが、患者は「熱くて寒い」と言っていたそうだ。寒いと言ってはぶるぶる震え、熱いと言ってはぐったりして、それは見るも無惨な姿だったという。
そうは言っても、僕はインドの蚊にこれまでどれだけ多量の献血をしたかわからない。特定の種類の蚊がこの伝染病の媒体になるそうだが、蚊の寿命なんて、どうせ蚊のように短いので、蚊に食われたからと言ってマラリアに罹る確率は低いとは思うが、油断は禁物、蚊取り線香ぐらいは焚いた方がいい。
特に安宿に泊まるバック・パッカーには蚊取り線香は必需品だ。蚊取りマットをつけてくれるホテルもあるが、そこまでサービスしてくれない所の方が多いので、インドに着いた日に仕入れておくといい。その辺の店で売っている。
夜に部屋にいると、小さな男の子が大きな缶をぶら下げてやって来た。ドアを開けると、
「スダル」
と言った。この四角い錆びついた大きな缶の中身が何なのかは知っている。蓋を開けさせてみると、やっぱり透明の液体に漬かった豆だった。
「スダル、いらないよ」
僕は手を振って断った。この『スダル』というのはどういった食品なのか? どこでもよく売り歩いているので、インドではポピュラーなおやつみたいだ。見ればすぐわかる単純なものだけれど、「ダル」は大豆のことだとして、そうすると「ス」は何だろう? 僕は未だに食べたことがないのでそこんとこがはっきりしない。
必ず汚いブリキ缶に入れて売り歩いている。それも必ずメッキが剥げ、錆びついている。あの入れ物を見ただけで食べてみる気になれないのだ。スダルは汚れたブリキ缶に入れなければならないという決まりでもあるのだろうか? それはともかくとして、見たところ、「ス」は日本語と同じで「酢」のように思われた。大豆の酢漬けだろうか?
インドには健康のためとかではなく、宗教上の理由で菜食主義者が多いから、大豆は大切な蛋白源となっているようだ。僕の苦手な「ダル」は、ちょうど日本の納豆やみそ汁に当たるだろう。しかし僕は、大豆は嫌いではないが、インドの「ダル」はたいてい辛すぎるか、そうでなければ味も素っ気もないので、ちょっと食う気にはなれない。
まあ、スダルの語源を詮索してもしょうがない。どうせこれからも食べないだろうし。代わりにこれをやろうと言ってチューインガムを差し出したら、男の子は缶をその場に置いたまま逃げて行ってしまった。
「何なんだろう? ガムが怖いのかあ? おかしな子供だな」
と不思議に思っていると、また戻って来た。今度は妹を連れて来ていた。この子たちはこのホテルの子供なのだ。妹に「もらえよ」と言っている様子だった。女の子ははにかみながら手を出し、ガムを受け取った。妹思いのいい兄貴だなあ。それでまた、
「スダル」
と来た。
「だからいらないって言ってるだろ。スダル、ノー、だよ」
男の子はやっと納得したみたいで、次の部屋へと売りに行った。
5月17日 晴 ティルチラパッリ 〜 マドラス
朝八時前に昨日のリクシャー・ワーラーが来て、インド一広い寺へ連れて行ってもらった。ところが入場券を買ってからわかったことだが、この寺はヒンズー教徒以外は中に入れないことになっていた。特に例外というわけではなく、こういう所はヒンズー教の寺院には多い。
とりあえず屋上に上がって見晴らしてみると、本当にインド一広いかもしれない、どこまでも建物が続いているのが見て取れた。来る途中でワーラーがしきりに指し示していた黄金寺院の金色の屋根も、くすんだ色の寺院群の真ん中で一際目立っている。日本の金閣寺みたいなこの黄金寺院という建物は、インド各地にあるみたいだが、ここの黄金寺院は周囲の景観にそぐわず、これ一つあるがためにかえって全体が安っぽくも感じられた。
その屋上で、ついて来た寺のガイドと称す男が言った。
「俺は免状を持っている。300ルピーで3キロメートルを案内するぞ」
「免状? 何のことだ?」
よく意味が分からず問い返すと、
「俺と一緒だと寺の中にも入ることができるんだ」
男は言った。それが本当だろうが偽りだろうが、どっちにしたってふざけてやがる。
「そんな馬鹿な話があるか。いらない」
とにべもなく断った。すると、こっちが黙って景色を眺めている束の間にも、200ルピー、150ルピー、120ルピーと勝手に値が下がっていく。賄賂を要求する門番みたいな奴だ。こいつに金を渡さないと中に入れないとは、ひどい寺だ。しかしあとから考えてみると、これははったりだったのかもしれないという気もする。ガイドに金を渡しさえすれば異教徒でも入ることができるというのは普通に考えればおかしい。異教徒でも入って構わない寺だったのかもしれない。
しかしこの時はそんなことは考えず、腹が立っていたのでさっさと帰ろうと階段を下り始めた。ガイド料はあっと言う間に60ルピーまで値下がりしていた。
「せっかく来たのに寺の中を見ずに帰るのか?」
ガイドと称す男は追いすがって来た。
「マドゥライの寺は3ルピーだったぞ」
と適当に言ってやると、
「マドゥライはナンバーツー、ここはナンバーワン。カメラ料20ルピーが無駄になるぞ」
獲物を取り逃がすまいと必死で悪あがきしているのがわかる。その言いぐさに益々腹が立ち、門を出ると、男の目の前でカメラ券をこれ見よがしに捨ててやった。そのまま男を無視してリクシャーに乗り込んだ。向かいの店で休んでいたワーラーが慌ててやって来た。あまりにお早いお帰りに驚いているようだったが、
「ここは異教徒お断りだったぞ」
としかめっ面して言ってやると、
「じゃあ次行こう」
と平気な顔して急いでエンジンをかけた。
次の寺は小さかったが、今度は前もって異教徒OKかどうかをワーラーに確かめさせると、ここは本当に駄目みたいだった。早くも三つ目の寺へと向かう。
「どこも入れないじゃないか」
と運転席のワーラーに文句を言うと、
「次は大丈夫だよ」
とワーラーは笑って答える。悪いと思いもしない、謝りさえしないところがリクシャー・ワーラーらしい。
次のロック・フォート(岩山を掘って造った砦)にはなんとか入ることができたものの、内部の大部分が寺院に改造されていて、そこも異教徒は入ることができず、結局岩山の中を通って頂上まで登り、降りて来ただけだった。そのあとホテルに戻らせたが、たった二時間の観光で終わり、200ルピーは高くついた。
ホテルでうとうとしながら時間をつぶし、三時頃バス・スタンドへ向かう。凄い人出だ。マドラス行きのプラットホームと切符売り場を教えてもらい、そっちの方へ向かっていると、おじさんが近づいて来て、
「どこ行くの?」
「マドラス」
「65ルピー。三時十五分に出て、九時十五分に着くよ」
ついて行くと、民間の旅行社の客引きだった。料金は60ルピーで、5ルピーはこのおじさんのマージンだと自らばらしている。それにしても60ルピー(200円くらい)は安い。さっきの近場をちょっと回っただけのリクシャーが、貸し切りとはいえ200ルピー(700円)だ。やっぱりリクシャーは高い。バスは安い。
そしてまたもやバス・スタンドに着いた途端に出発。最近は妙にタイミングがいいなあ。バスに乗るのに数時間
〜 半日は待たされていたあの頃は一体何だったんだ。
夜九時半を過ぎた頃にマドラスに着いたが、マドラスの街はかなりでかい。デリーより広い気がする。セントラル行きだったが、マドラスに入ってからなかなかセントラルに辿り着かない。終点が駅だと言うので、そこまで行ってから降りたが、セントラル駅ではなかった。
どこにいるのかさっぱりわからないので、リクシャーを捕まえてホテルに連れて行ってもらうことにした。最初に連れて行かれた所は125ルピーだったが、部屋を取ったあとで、「インド人しか泊めないんだ」と宿のおやじが言い出した。最初から言え、クソおやじめ。
次の所へ行くと、ここは250ルピーだった。高い!(梅の上コース旅行者としての叫び)しかし大都市だし、この辺りで手を打っとかないと、とカルカッタ入りした夜のことが頭をよぎる。
このホテルのマネジャーも、どういう理由からか、僕を怪しむような目つきで見ながら、あまり泊めたがっていないような口ぶりだ。フロントで手続きをしていると、リクシャー・ワーラーが横から、
「あと20ルピーくれ」
と言った。最初に断られたホテルまでが30ルピー、そこからこのホテルまでが20ルピーということで、渋々その合計50ルピー支払ってからまだそんなことを言う。とうとう頭に来て、
「最初の外人を泊めないホテルへ連れて行ったのはおまえのミスだろが。まだ金取る気か!」
と怒鳴ってやった。フロントにいたホテルの泊まり客たちもびっくりした様子で、足を止めて何事かと傍観している。ここんとこ平穏無事でおとなしくしていたので、赤痢全快祝いということにして、久しぶりに大和魂に点火してやるか。しかしこいつは張り合いのない奴だった。怒鳴られるとすんなり諦めてホテルから出て行ってしまった。
ところがチェックインが済んでボーイに部屋に連れて行かれたあとで、すぐにマネジャーがやって来て、外国人は三階だと言われ、部屋を移動させられた。またまた嫌がらせかあ。嫌な所に来てしまったなあ。
だが新しい部屋に入ると、マネジャーは一泊200ルピーだと言った。ちょっと得した気分になりほくそ笑む。そして明日マハーバリプラムへ行くんだと言うと、
「それじゃあ、またマドラスに戻って来ますねえ?」
「そのつもりだけど」
「マハーバリプラムから戻って来た時は、是非またうちに泊まって行って下さい」
と言って僕に名刺を手渡すと、部屋の設備の説明を始めた。いつの間にか僕のことを「サー」付けで呼んでいる。おいおい、さっきとは態度が全然違うじゃないか。やって来た時は、人をまるで連続放火犯みたいに扱いやがったくせに。
「ではおやすみなさいませ、サー」
マネジャーはいんぎんな態度のまま部屋から出て行った。
このホテルは外観とは違って内部は綺麗で設備も整っていた。インドにしては珍しく、シャワールームに石鹸やバスタオルまで備え付けてある。これまで泊まってきた安宿とは雰囲気も違う。たまにはこういう部屋もいいけれど、おらやっぱり安宿が良かっぺなぁ。
『安宿』とは、値段が安いだけでは安宿とは呼べない。値段がやけに安く、且つ、雨季には洪水で流れてしまいそうなほどぼろっちくないといけない。
窓ガラスは入れてから何年も拭いたことはなく、万年曇ガラス、割れたままにしてある場合もままある。無論のことカーペットなど敷いていなく、階段や廊下は言うに及ばず、部屋の床さえコンクリート剥き出し。されど穴ぼこが空き煤けてコンクリートの無表情さを感じさせない。
ボーイは決してきびきびとは動かず、何をするにも要領が悪く、どこか抜けている。客の部屋に勝手に押し入って来て、「フレーンド!」とか言いながら客の持ち物をねだる。そればかりかホテルのオーナーまで外国人泊まり客から余分な金を詐欺り取ろうとする、経営者か盗賊か得体の知れない奴。頼まれたことは何でも安請け合いして、そのくせ儲けにならない用事なら瞬時に忘れて永久にすっぽかす。
お調子者、さもなくば無愛想、従業員たちはこの二種類のタイプのどちらかと必ず決まっていて、接客態度は全て本人の自由意志に任されている。――善きにつけ悪しきにつけ、これぞ安宿であろう。
しかしどっちにしろ、マドラスのような大都市のホテルは軒並み料金が高いので、マハーバリプラムからの帰りは泊まらずに通過しようと思っているのだ。マネジャーの姿勢は関係ないのである。
5月18日 晴 マドラス 〜 マハーバリプラム
朝、鉄道の予約をしにセントラル駅へ行く。次に行く予定にしているマハーバリプラムという所は、ここマドラスから海岸沿いを少し南へ行った所にあり、三、四日ほどそこに行ってからまたマドラスに引き返して来るので、その時乗る列車の予約なら取れるだろうと思っていたのだが、今度も駄目だった。てんで駄目。北へ向かう列車は今日から一カ月間、全て満席になっていた。
このタミルナドゥ州の北の端にあるマドラスからオリッサ州の真ん中辺にあるブバネーシュワルまでの1000キロメートル強は、謎の地帯だ。『○○の○き方』でも空白地になっている。このアーンドラ・プラデーシュ州とオリッサ州南部のベンガル湾沿いには、町が一つもない――なわけないだろうけど、ガイドブックの知らない未知の地域なのだ。
まあ、バスを乗り継いで行けば、行けないこともないだろう。思えば、ジャンシー
〜 アーグラー間のすし詰め列車に乗って以来、列車には乗っていないことになる。あのあとは全てバス移動だ。この国は人口が多いのに、本数が少なすぎるのだ。乗れないこともないのだが、いくら安いと言っても、あのジャーニー・チケットで乗るのだけは懲り懲りだ。家畜でも嫌がるに違いない。あれなら死と隣合わせの恐怖バスの方がまだましだろう。「拷問か恐怖か」と迫られれば、恐怖の方がまだしも耐え易きものだとしみじみ思う今日この頃である。
しかしまだ距離的に三分の一近くも残しているというのに、土壇場になって日程が詰んできた。とは思いながらも、日本で立ててきた綿密なスケジュール表に従い、海辺のマハーバリプラムへと、一時南に逆戻りすることにする。
リクシャーを捕まえてバス・スタンドまで連れて行ってもらう。バスが何台か停まっていた。どれに乗るのかわからなかったが、リクシャー・ワーラーが一生懸命訊いて回ってくれたので、僕はじっとしているだけで済んだ。この人は例外的に善いリクシャー・ワーラーだった。
しかしバスに乗り込むと、もう席がいっぱいになっていた。いや、どうしたことか、乗降口のすぐ後ろの席だけ空いているではないか。立っている客もいっぱいいるというのに、どうしてこんないい席だけ空いてるんだろ、と思って座ろうとしたが、だれもそこに座らない理由がすぐにわかった。
ここはマハラジャ専用シートだったのだ――いやいや、冗談。マハラジャがこんなおんぼろバスに乗るはずがない。実は呪いが掛かった席だったのだ――というのもほんとはウソだけど、当たらずとも遠からず、乗客は呪いを避けていた。二人掛けのシートの窓側の床を見たら、ゲロが落ちていた。「掃除しないのか。しないだろなー」と一人問答しながらも、マハーバリプラムまで立ち通しは嫌だから、躊躇することなく通路側の席に座った。
乗客はなおも次々と乗り込んで来る。荷物も通路に置いたままにしていると、車掌がやって来て、「奥に詰めろ」と言われた。そこで隣の床を指差し示すと、「ウォンティ」と言って納得顔で行ってしまった。納得してないで、どうにかしてくれよー。あとから乗って来た人たちも、「ウォンティ」と言い、座るのを諦めて立っている。周りの人たちも気づいて、人が座ろうとする度に、「ウォンティ、ウォンティ」とみんなで注意する。お陰でタミル語を一つだけ学習できた。どうせ覚えるのなら、もうちょっとましな言葉を覚えたかった。
ところが強者婆さんが乗り込んで来た。片目がつぶれている。僕に向かって「詰めろ」と言っているみたいだったので、覚えたての言葉で「ウォンティだ」と指差してやった。周りの人たちも例によって「ウォンティ」の大合唱。しかし婆さん少しも意に介さず、僕を乗り越えて呪いの席に座った。片足を前の手すりに載せ、もう一方を窓枠に載せて座る。器用な人だ。ヨガでもやっていたのかもしれない。
バスは超満員となり、ようやく発車した。独眼竜婆さん、仕事道具を取り出し、その窮屈な姿勢のまま早速内職を始めた。小さな籠に花びらがいっぱい入っている。それを針と糸でつなぎ、どうやら花輪を作っているようだ。まだできあがっていないというのに、早くも花輪に買い手がつく。すぐ近くにいた貴婦人風の人。婆さんは偉そうな態度で花輪と引き替えに金を受け取った。そうしてまた次の花輪を作る。
インドではバスが停まっていると、窓の外に物売りがやって来て、いろいろな食べ物を買うことができるのだが、今回は発車前に買ったみかんがひどく不味かったので、近くにいる人たちに分けてやろうとすると、みんな「いらない」と笑顔で断ってきた。たぶん美味かったらこんな親切はしなかっただろう。あんな不味いみかん、生まれて初めて食った。
唯一受け取った相手が隣の婆さんだった。食べもしないでカバンの中にしまった。とりあえず二個やったが、残りのみかんも周りの人たちに断られているうちに、独眼竜婆さん、僕の肩を叩いて手を出した。もらってやろうと言っているみたいだ。こちらから渡すより早く、ふんだくってまたカバンの中にしまい込んだ。やれやれ、五個買ったみかんのうち四個はこのババアのために買ってやったようなものだ。どうせ食えないのだからいいけど。
しかし途中でふとあることに気がついた。婆さん内職に熱中しているうちに、いつの間にか足を床に下ろしている。インド人は伝統として裸足で歩くが、今では靴やサンダルを履く人も多い。それでも特に女性は、まだまだ裸足で歩いている人もよく見かける。けれども乗り物にまで裸足で乗って来る人はさすがに見かけない。だいたいこんな混んでいるバスなどでは、足を踏んづけられたら危ないじゃないか。
ところがこの独眼竜婆さんだけは靴を買う金がないのか、それとも保守家なのか、裸足だった。いやいや、こんな抜け目のないババアだ、小金を貯め込んでいるに違いない。恐らく靴など余計なものだとでも思っているのだろう、要するにケチなだけだ。このババアなら靴の必要性など感じないに違いない。なぜなら、横目でチラチラ観察していたけれど(なんでこんなものを観察するのか、我ながら馬鹿々々しくなるが)、床はそのうちババアの裸足により塗り伸ばされた『ウォンティ』で、ワックス掛けしたようになってしまった。
独眼竜は途中でさっさとバスから降りてった。ああいうのがマハーバリプラムへリゾートに行くはずもないな、と思っていると、そこから乗り込んで来た客の一人が、「席が空いてるぞ、ラッキー」とばかりに急いで僕の隣に座った。以前から立っていた乗客がなぜそこに座らなかったのかという疑問などは抱かなかったようだ。どういう経路を辿るにせよ、インドではペットボトル以外のゴミは自然になくなるようにできているみたいだ。
マハーバリプラムに着いて、僕が泊まった所は150ルピーと高かった。浜にある普通の安宿だが、部屋は殺風景、ろくな設備もない。だが部屋が全て中庭に向いていて、泊まり客たち(みんな西洋人)の洗濯物がいっぱい干してあり、キャンプ場みたいな雰囲気で楽しい。若い女性も平気でパンツを表にぶら下げている。西洋人の表札みたいなものなのかもしれない。
晩めしは浜で獲れた魚が出るということだ。今日は『キングフィッシュ』だと言ってたので、キングフィッシュってどんな魚だと根ほり葉ほり訊いてみたが、「キングフィッシュはキングフィッシュだ」と言われただけだった。そりゃ魚の名前を言い換えてわからせるなんて不可能なんだろうけど。
早速海を視察に出かけてみたが、やっぱり汚かった。砂浜は白砂でとても広いのだが、水が汚い。海水浴中止と決定。汚い水の中で泳いだからといって死ぬわけでもないが、汚い水で沐浴しにインドまで来たわけでもない。結局インドで泳いだのはコヴァーラムだけだった。
海岸寺院へ行ってみたが、先にここに来た万根クンが言ってた通り、しょぼかった。世界文化遺産と言ってもいろいろあろう。その道で、服を着た猿に捕まった。猿使いが紐を握っている。宙返り一回しただけで、この猿め、手を出して早くも金を要求しやがる。まんまと2ルピー奪われた。人生を舐めた猿め。猿に人生がわかってたまるものか。
今日はやたらにコインが貯まったので、バクシーシの大売り出しだった。これからはふてぶてしい物乞いにはやらないことにした。形だけでもありがたがる奴だけにやることにする。
それにしてもここは本当にのどかでいい。ベンガル湾なので、海から日が昇るはずだが、夕方になると北の空が紫色になった。海は群青色で、月が昇っている。砂浜に椰子の実が打ち寄せられ、波に洗われているのを見つけ、思わず「名も知らぬ遠き島より流れ来る椰子の実一つ」というフレーズが口をついて出て来た。あとで知ったことだけど、本当は「流れ寄る」が正しいらしい。
なもしらーぬぅ、とおきしぃーまよりなーがれくーるやしーのみひとつぅ♪
その先は知らないので、「やしーのみひとつぅ」と繰り返していると、もう一つ椰子の実が打ち寄せられているのを見つけた。
なーがれくーるやしーのみふたつぅ♪
おやおや、椰子の実は二つどころではない、三つ、四つ、五つ……、砂浜を見渡してみると、椰子の実はそこらじゅうにごろごろしているではないか。
「さすが椰子の実の本場!」
と感心し、おもむろにその椰子の実の一つを拾い上げてみる。
「おや?」
よく見ると、椰子の実には穴が空いていた。ナタでスパッと切ったように穴が空いている。そいつを放り出して別のを拾い上げてみたが、こいつも同じように穴が空けられていて、中は空っぽだ。そこで手当たりしだいに調べてみたが、例外なくみんな抜け殻ばかりだった。
急に興が冷め、僕は手にした椰子の実を海に投げ込んだ。結論を先に言うと、これは要するにゴミが流れ着いたまでのことなのだ。どこかこの近くの浜辺や川の上流で、飲んだココナッツ・ジュースの殻をみんながポイポイ投げ捨てる。「遠き島より流れて来た」のでも何でもない。食い散らしのゴミが浜に流れ着いただけのことだ。そのゴミを見て感慨に耽っていたとは……。
気分を取り直して浜辺の散歩を再開すると、今度は砂浜の上の方の乾いた砂の上に、蟹が打ち揚がっているのを見つけた。まさかこれも裏返してみたら、肉を食われたあとの甲羅だけじゃないだろうな、と疑いながら拾い上げてみると、蟹はかすかに動いた。しかしぐったりしていて、もう瀕死の状態だ。
ドジな蟹だなあ、と思いながらも波打ち際まで持って行ってやった。ところが波が寄せて来て、引いたかと思うと、裏返しにひっくり返ってしまった。それでまた立ち直らせてやったが、また波が引いたあとひっくり返った。それを何度も繰り返す。海水に触れているうちに徐々に脚を蠢かすようになってきたから、元気になってきたのだろうとは思ったが、何度やっても波でひっくり返ってしまう。カナヅチの蟹なのか。
しょうがない蟹だなあと業を煮やし、最後には、波が引いたあとに蟹を持ったまま走って行って、できるだけ遠くの海の中に投げ込んでやった。生き返っただろうか? 「今日は動物愛護をした。俺もたまにはいいことするなあ」と自己陶酔しながらホテルに戻ると、ボーイが「キングフィッシュもう焼けてるよ」と言うので、「おお、キングフィッシュの謎が解けるぞ」と勇んで二階のレストランへと向かう。
しかしキングフィッシュとは別に謎な魚ではなかった。鯛の尾頭付きだった。大きいの丸ごと一匹、あとフライドライスとポテトチップ、野菜で、75ルピー。これは安い。宿がコヴァーラムのように安ければ、長居できるいい所なのだが。逆にコヴァーラムは食べ物が不味くて高かった。両方揃ったリゾート地はないものだろうか?
それにしても獲れたての鯛は旨い、旨い。浜辺でさるかに合戦したあと獲れたての魚介類に舌鼓を打つのはもう最高だなあ。
5月19日 晴 マハーバリプラム
今日はマハーバリプラムの観光ポイントを見物に行ったが、五つの石彫寺院は砂が灼けてただ地面が熱いだけだった。海岸寺院もレリーフもしょぼかった。浜にいるところに絵はがき売りが近づいて来て、やたらに売り込んで来る。何枚か見ているうちに、『クリシュナのバターボール』というのを見損なっているのに気づいた。今日は暑いから明日見に行こう。これは写真では、まん丸の大きな岩が岩山の斜面で止まっている。どうして止まっているのか好奇心がある。
絵はがきは買わずに済んだが、同じ所に物乞いもいて、待ち伏せていた。浜にいる婆さんと、煙草をたかってくるおっさんには、今日も出会ってしまった。猿回しには気づかれないように上手くすり抜けたが、ここは人口密度が低いのですぐ顔を覚えられてしまう。一度でもおいしい目に遭わせると、同じ場所でずっと待ち伏せされるのだ。
そして今日は新たにガキ姉弟が加わる。弟は飯粒だらけの掌を突き出しながら金をせびりに来た。それがあまりにも凄まじい光景で様になっていて、こっちは唖然としたまま、気がつくとそのぼうずの掌に小銭を載せていた。
今日は不思議な出来事があった。見物に行くついでにはがきを出そうと持って出たのだが、村の繁華街(というほどのものでもないが)へ行けばポストくらいあるだろうと、たぶん近道になるはずの裏道を通って行くと、途中の路地裏から突如仔馬が飛び出て来た。
こんな路地裏で何してるんだろうと少しばかり不思議に思ったが、仔馬は僕について来た。いや、僕の前を歩き出したので、厳密には僕がついて行ったことになるが、珍しかったので、冗談半分に、「ポストはどこだ?」と日本語でその仔馬に訊いてみた。馬耳東風。馬の耳に念仏。仔馬は何の反応も示さず、相変わらずポクポクと蹄を鳴らしながら歩いて行く。
やがて角を曲がると広い道に出た。宿や店が並んでいる。店の売り物を眺めながら、もう一度念のために「ポスト」と仔馬に行き先を言ってみたが、またもや念仏扱いされた。
そのうちバス停の所まで来た。この田舎の村では一番賑やかな場所だ。と、仔馬は何を思ったか、マラソンランナーのようにくるりとUターンして、元来た道を相変わらずポクポクとのんきそうに引き返して行った。
「朝のお散歩だったのかな」と思って馬からふと視線を戻すと、目の前にポストがあった。不思議だ! 馬は賢い! インドの馬なのに日本語がわかるなんて! 感動しながら僕は絵はがきをポストに放り込んだ。
ここでは動物と縁がある。昨晩、ホテルの裏手にいた三匹組の野良犬と仲良くなった。インドにはどこにでも野良犬がたくさんいるが、インド人たちは石ころのように相手にしない。それで野良犬の方も同じように人間たちを空気のように無視している。ところが本当は非常に人なつっこく、一旦かまうと蜘蛛の糸のようにまとわりついてくる。
今晩はビスケットをお土産に買って帰ると、ホテルの門前で待っていた。よしよし。あとで裏門から出ると(僕の部屋は裏門のすぐ近く)、そこにも三匹いて、まとわりついてきた。さっきの門前にいたのは犬違いだった。そう言えば二匹しかいなかった。もうお土産ないよ。
昨日は浜で瀕死の蟹を助けたが、今日は浜を猛烈なスピードで横に走る小蟹を脅して遊んだ。水の中を進むとなぜか蟹は気づかない。それから砂浜に揚がってダーッと走る。すると蟹たちは海の中か砂浜に開けた穴のどちらかへと逃げ込もうとする。すばしっこくて追いつかないのだが、ところがどっちへ逃げようかと右往左往している間抜けな蟹もいて面白い。啄木の、『我一人蟹と戯れる』というのがこれだろう。
今日あったもう一つ不思議な出来事――砂浜が広く、遠くで霞んでいるので、どこまで続いているのか見に行ってやろうと思って行ってみたが、どこまで進んでも果てが見えない。マドラスまで続いているのかもしれない。
どうせこうなるだろうとは予想していたものの、諦めて引き返したが、途中でばててしまい、浜に座り込んでしまった。近くで家族連れが一組だけ海水浴をしている。男が海パンを履いているのは珍しくはないが、奥さんと娘が水着を着ていた。日本の大正時代みたいな水着だけど、インドでは初めて見た。インドの女の人はサリーを着たまま海水浴する。泳ぎもしない。沐浴という感じだ。ハイカラな家族なんだろう。大正時代の日本の海にタイム・トリップしたような気分になった。
「腹減ったなあ」
しかしかなり歩いたみたいで、食い物屋のある辺りまではまだまだある。するとどこから湧いて出たのか、子供が後ろから近づいて来た。さっきまで海水浴を楽しんでいる四人の家族連れ以外は猫の子一匹見かけなかったはずなのに、不思議だ。だだっ広い砂浜以外、何もない所なのに。
おまけにその子はサモーサーを売りに来たのだった。小さなサモーサーで、二個で1ルピーだと言う。食べてみると、今まで食べた中で一番美味いサモーサーだった。そこで四個2ルピーで買うと、一個おまけにつけてくれた。
腹減ったなあと思った途端に現れるとは、何とタイミングのいいことだろう。それもこんな何もない人もいない場所で。もしかすると昨日助けた蟹が恩返しに人間の子供に化けて、浜に開けた穴からサモーサーを持って這い出て来たのかもしれない。
浦島太郎は亀を助けた恩返しに竜宮城に連れて行ってもらった。伊井田褐太は蟹を助けた恩返しにサモーサーを売ってもらった。2ルピー払ったのはインドらしいので、まあいいだろう。浦島太郎は竜宮城で何をご馳走してもらったのだろうか。踊りを終えた鯛やヒラメの刺身だろうか。
まるでおとぎ話の世界にいるみたいだなあ、などと感動しながらホテルに戻ってレストランへ行くと、今日は小エビが五十匹ほど出て来た。食べているうちにその小エビが昼間の小蟹に見えてきた。口の中で横這いにササーッと走っては、体の中に潜り込まれそうな気がした。
5月20日 晴 マハーバリプラム
午前に『クリシュナのバターボール』というのを見に行ってみたが、写真のようにまん丸ではない。そういう角度からわざわざ撮っているようだ。昨日すぐそばを通ったはずなのに見落としたわけだ。たまたま崩れ落ちた岩がそこで止まったのか、わざと置いたのか、どちらにしてもさほどのことはない。日がカンカン照りつける中で、山羊たちの日よけになっている。更にインド人の観光客たちがやって来てその山羊たちを追い出し、自分たちの休憩場所にしてしまった。
浜辺にスラムがあるが、そこから女の子が片足を引きずりながらやって来た。見ると、片足にゴム草履を履き、もう一方の足には布を巻いて砂の上を歩いている。どうしたのだと訊くと、「とても熱い」と答えた。片足に履いている草履は拾って来たものなのだろう。僕の方は「片方の草履はどうしたのだ」という意味で訊いたのだが、女の子は「砂が灼けて熱いから足を覆っているのだ」という意味で答えたみたいだ。それ以上訊くのはやめにした。
昼は散歩、うたた寝、また散歩。子供の頃に戻ったように、砂浜で貝殻を拾って回った。あとは犬と遊んだだけ。夜はイカが出た。今日は書くことがない。書くことがないということは、明日出発するということだろう。
5月21日 晴 マハーバリプラム 〜 マドラス 〜
朝マハーバリプラムを出てマドラスに戻った。アーンドラプラデーシュの海岸沿い行きのバスがほとんどない。夜九時半発の旅行社のバス、ヴィジャヤワダ行きが250ルピーもする。仕方ない、それしかないのだから。
それまでマリーナビーチへ行って時間をつぶしたが、じっとしているだけで面白い。日暮れが近づくにつれ、人がどんどん押し寄せて来て、いろんな物売りが次から次へとやって来る。夕涼みの時間になると、人の多い街は毎日がお祭だ。おまけに近くのスタジアムでクリケットの試合があったようで、試合が終わると観客が夕涼みに浜までどっと繰り出して来た。
馬に乗せる商売というのもあった。案の定、そのうち僕の所にも来て、乗ってみないかと誘ってきたが、さっきから様子を見ていたので、高すぎる値段を聞いてあっさり断った。客を前に乗せて波打ち際までを往復するだけ。二、三分でおしまい。
海辺に座って、海水浴をしている子供たちを眺めていると、サラリーマンの兄弟というのがやって来て長い間話をしていたが、この兄弟が、僕の両膝が破れたジーパンに興味を示し、「それはスタイルか?」と訊く。これまでも出会った人からたまにこういうことを訊かれた。わざと破けたジーパンを履くというのは日本にはあるけれど、これはローカル・バスで一晩汗みずくになり、床に膝を抱えて座っていたためいっぺんに両膝が裂けただけのことだ。しかし一々それを言うのも馬鹿々々しいので、「たぶんそうだろ」とだけ答えることにしている。
夜にバスが出発。ここからガイドブックにもないアーンドラプラデーシュのベンガル湾沿いをバスを乗り継いで行く。インドにいられるのはあと十六日しかない。ちゃんとカルカッタまで戻ることができるのだろうか、非常に不安だ。というのは大ウソで、そろそろ焦らなくてはならないはずなのに、ちっともそういう気分にならない。ほとんどインド化してきていて、時間にルーズになっている。良く言えば「おおらか」になってきたし、悪く言えば「だらけて」きたというのが自分でもよくわかるのだ。
 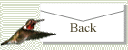
|