|
7.悪しき者には天罰を! 嘘なんかついたことない奴
4月15日 晴 アーマダバード
ここではホット・シャワーなんかいらない。暑すぎる。特にこの独房などは、土の中に埋められているのと何ら変わりはない。シャワーから氷水が出て来てもいいくらいなのに、こういう暑い場所に来た時に限って断水だ。インドでは停電はよくあるが、断水は辛い。と、げんなりしながら何気なく水道の蛇口をひねったら、今朝はなぜか水が出た。ちょっと模範囚になってきたので、水だけは出してやろうということなのか。
午前は独房から脱獄して、ダーダ・ハリ・ニ・ヴァン(階段井戸)へ行った。リクシャーワーラーに地名を言っても知らないみたいで、地図を何度も見せながらのろのろと進んだ。それらしき辺りまで来てみると、屯してぺちゃくちゃ喋っていたオバサンたちがいた。井戸端会議をしているということは、まさにここに階段井戸があるのかもしれない。そこでワーラーがぺちゃくちゃオバサンたちに尋ねてみたが、やはりダーダ・ハリ・ニ・ヴァンだった。
そこで降ろしてもらうと、すぐそばに地下へと下って行く階段が見つかった。オバサンたちは揃って階段を指差して、「ダーダ・ハリ・ニ・ヴァン」と言っている。早速階段を下りてみたが、写真で見たのとはまるで違う。階段を真っ直ぐ下りてくとすぐに行き止まりで、そこには井戸があるから、確かに階段井戸には違いなかろうが、釈然としない僕は、また上まで引き返して行って、虎の巻を開くと、そこに載っている写真を井戸端のオバサンたちに見せてみた。
写真を見たオバサンたちは、今度はまたもや揃ってある方角を指差すと、ぺちゃくちゃと何か喋りだした。何を言ってるのかさっぱりわからなかったが、そこにはオバサンたちにサリーの生地をセールスしていた(商売そっちのけで駄べってるだけに見えたが)二人の若い行商人の兄弟がいて、弟の方が少し英語ができるみたいで、オバサンたちのぺちゃくちゃのグジャラート語を通訳してくれた。写真の方は『大階段井戸』で、こっちは『小階段井戸』なのだそうだ。いや、それ以上は、オバサンたちが言っている大階段井戸までの道順を上手く訳せないみたいで、結局兄弟で道案内してくれることになった。
道々遊んでいる子供たちに訊きながらしばらく歩くと、大階段井戸に着いた。そこには人っ子一人いなかった。カンカン照りで暑くてたまらない。涸れ井戸なのだが、こちらはかなり大きな建造物とでもいった感じだ。井戸の底まで真っ直ぐ下りてく(鉛直方向に真っ直ぐ下りるわけではない)階段と、螺旋階段がある。兄弟も井戸を上がったり下りたりして見物していた。
この井戸にはなぜ二種類の階段が設けられているのだろうか? 恐らく螺旋階段はあとから造ったものだろう。ここにはつるべみたいな物はないようだ。元々は人間がのんびりしていて、正面の長い階段をゆるゆると下りて行きながら、水を汲むにものんびり時間をかけていたと思われる。それが人間がせっかちになってきて、できるだけ急いで水を汲もうと考えるようになり、井戸の真横から急降下で下りて行く螺旋階段をあとから造ったのではないだろうか(螺旋と言うほど形は整っていない)。
螺旋階段を底から上ってみたが、かなり急で、すぐにへとへとになってしまう。これだとうっかりして、しょっちゅう水瓶をひっくり返していたに違いない。親切な行商の兄弟とは記念撮影をしてお別れした。
ぶらぶら歩いているとバス停があったので、バスでホテルまで帰ろうと待っていたが、通りかかった若者が、バスはなかなか来ないぞというようなことを言い、それまで話でもしようと、近くのコーヒー屋から(ほんとは何屋なのか不明)コーヒーを持って来て奢ってくれた。インドに来て他人から奢ってもらったのはこれが初めてのことだ。
ここは外国人がほとんど来ないみたいで、実際一人も見かけなかったが、余所と違い、金目当てで寄って来るのではないからいい。変わった奴がいるぞ、見物しよう、といった感覚なのだろうか。とにかく見返りを狙った親切ではないので、こっちも気分がいい。
それでコーヒー屋を写真に撮ろうとしていると、おやじが気づいてありったけの人数をかき集めてきた。二十人ほど集まり、みんな並ぶと、カメラに向かって直立不動の姿勢でかしこまっている。しょうがないから写したが、修学旅行の記念撮影になってしまった。なんでインド人はカメラに気づくといつもいつもこうなんだろう。こっちは普通の風景のスナップ写真を撮りたいと思っているだけであって、記念写真なんか欲しくないんだけどなあ。
今朝は駅に切符を取りに行った時、行列に並ぶ気力が湧かなくて、またあとで来ようと諦めたのだが、そこで本物のシェイクを初めて見つけて飲んだ。インドで「シェイク」を頼むと、ミルクに砂糖を入れてシェイクしただけの物(これこそまさにシェイクなんだろうけど)が出て来て裏切られる。この本物の方は、「シック・シェイク」になっている。インド人なら「ティック・シェイク」と発音するのだろうが。
街を歩いているとすぐ喉が渇く。フレッシュ・ジュースを飲み、またちょっと歩いてサイダーを飲み、またちょっと歩いてソフトクリーム、余計に喉が渇いてコールド・ミント・ティー。これは懐かしの三角パックだったので思わず買ってしまった。冷たい紅茶はインドではなかなかないので、これは正解だった。
他に変わった飲み物は、フレーバー・ミルク。ビニールの袋入りで、一旦ストローを突き刺すと、飲み終わるまでずっと手に持っていないといけない。それからサトウキビ・ジュース。街角のそこらじゅうにいて、やけにでかい機械で歯車に竹を挟んでばらしているからすぐわかると思うが、これが砂糖黍から汁を搾り出しているのだ。これに氷を入れて1ルピーとかの安値で売っているのだが、「どうせ砂糖水だろう」と期待しないで飲んでみると、全然違う。暑いインドには適した飲み物だ。椰子の実も安くて、中には意外にもジュースが一杯入っているが、こいつは端っこをなたで切って、その穴からストローで飲むだけなので、生ぬるくて美味くはない。味はほとんどない。
とにかく喉に流し込んだ液体は胃に辿り着くまでにみんな蒸発してしまう。たまらないのでホテルに引き返した。そいでまたボーイにコーラを持って来てもらった。チップをやると、冷たい水を盆に載せ、次から次へと持って来る。昨日持って来いよ! 別のボーイまで頼んでもいないのになぜかチャーイを持って来るようになった。そこでそいつにもチップをやった。するととめどもなくチャーイを持って来た。もう知らん顔してほっといたら、テーブルの上がコップだらけになってしまった。
夕方になってから、気合いを入れて(気合いが必要なのだ)列車の予約に駅まで行った。その前に駅の近くにあるスィディ・バシール・モスクに寄ろうとしたのだが、ここのリクシャー・ワーラーはさっぱり道を知らないみたいで、停まってはその辺の人に道を訊いている。駅のそばなのに、さんざん迷ってからやっと着いた。
例の虎の巻『○○の○き方』に、このモスクのミナレット(小さな塔みたいな大きな柱)は押すと揺れると書いてあったので、揺らしに来たのだが、押してもビクともしない。あらゆる方向からうんうん押していると、モスクの前で夕涼みしていたイスラム教徒たちが何だ何だと寄り集まって来た。
揺れるはずなのにいくら押しても揺れないんだと僕が言うと、みんなでわいわい言いながら押し始めた。誰も知らないのだろうか? はったり書いてあっただけか? すると座って見ていた一人が、「押しても駄目なら引いてみな」と言った。「なるほど!」そこでみんなでミナレットをうんうん引き始めた。というのは嘘で、そんなことは言わなかった。ほんとは「ロックしてあるんだ」と言ったのだった。足元を見ると、確かに鍵が掛かっているのがわかった。
「夕方になったら鍵掛けちゃうんだよ」
みんながっかりして押すのも引くのも諦めた。そこで今度こそ気合いを入れて駅に切符を買いに行ったが、案の定、何日も先まで満席だった。仕方ない、怖いけど、また空飛ぶバスに飛び乗ろう。
今日のお料理。晩めしはメニューから謎の食べ物を選んでみました。マドラスィ・ディッシュというのはこれはいける。マドラスに行ったら本場物を食べてみよう。と言っても、マドラスではこんな呼び方はしてないだろうな。もう一つ、カシュミール・プラーウ、なんだかどちらも地名がついてるから選んだだけなのかもしれないが、こっちはひどい食べ物だった。甘いピラフで、これはちょっと食えた代物ではない。
さて、明日は早いとここの暑い暑い暑いアーマダバードから脱出するとするか。でないと熱中症と脱水症状でくたばってしまいそうだからなぁ。
4月16日 晴 アーマダバード 〜
灼熱地獄から早く逃げ出そうと、朝には看守マネジャーに賄賂を手渡し監獄ホテルから出所した。そのまま地図を見ながらバス・ステーションまで炎熱の道を歩いて行ったが、ここも英語が通じないのだ。もちろん日本語が通じるはずがない。身振り手振り、いろんなポーズを取ってるうちに、ここからは市内バスしか出ていないということがわかってきた。地名だけは通じるみたいで、結局インドールへ行くのがいいだろうということになった。
8Tバス・スタンドとやらへ行けということみたいだったので、また猛暑の中を干からびながらふらふらと歩いて行った。バス・スタンドのおじさんに「あっちだ」と言われてその辺に停まっているバスの所まで行くと、時刻表があったが、グジャラート語なのでさっぱりわからない。地名も一つとして読み取れないし、数字さえ読めない。グジャラート語に限らず、僕はインドの文字は全く読めないのだけれど。
一度どこかで子供からヒンドゥ語の数字を教わったが、これも得体の知れない謎の文字なのだ。0と2だけ「0」「2」というアラビア数字に似ているが、あとは全く違う。1は「q」に似てるし、7は「6」と書くので勘違いしてしまう。このガキが間違えてるんじゃないかと思ってそう言ってみたが、やっぱり7は6だと言い張った。とにかく数字は見ても数字だとはわからない。
すると近づいて来た警官が時刻表を読んでくれた。インドール行きは午後八時発だと言った。えー! まだまだじゃないか。監獄ホテルをチェックアウトしてこなければ良かったと思ったがあとの祭り、夜までどこかで時間をつぶさなくては……。重い荷物を背負い直すと、どこかくつろげる場所を探すことにした。
地図を見て、カンケリア湖という所へ行ってみた。ため池みたいな湖だ。とりあえず湖岸に腰を下ろして休む。何人か人が寄って来た。若いのが二人で水の中に何か投げ込んでいる。「何投げてんだ?」と訊いてみると、「ローティーだ」と言って、僕のとこまで来ると、おまえも投げてみるか、とローティーというのをくれた。小麦粉を練ったチャパティの素みたいだ。そいつをちぎって水の中に投げてみると、魚がたくさん寄って来た。
しばらくローティーを投げたり、僕と同じく暇を持て余しているらしいこの若者二人と駄べったりしながら暇つぶしした。このアーマダバードという街はおかしな所で、バス・ターミナルとかホテルとか、観光客の要所に当たる場所では全く英語が通じないのに、その辺をぶらぶらしてる奴には多少なりとも英語が通じるのだ。牛乳屋のおじさんなどは流暢な英語を喋ってた。
三時頃までそうして暇つぶししていたが、まだ五時間もある。近くにあるカフェテラスへ行って休憩。休憩って何の休憩だろう。さっきからずっと休憩してるのに。午にはここで子供のボーイお薦めの『マニパン』というのを食べてみたが、カレーと違い、普通のパンにチリソースみたいなのをつけて食べるのだった。
今度はフレッシュジュースを飲んでみる。「これ」と果物を選ぶと、ミキサーに入れて目の前でジュースにしてくれる。インドにはこのフレッシュジュースの屋台もよく街角で見かける。日本では僕はあまりジュースは飲まないのだが、暑いインドではこれが痺れるほど美味いのだった。
やっと夜になり、バス・スタンドに戻ると、運転手がいるバスを回って、「インドール?」「インドール?」と一々訊いて回ったが、どれも違ってて、まだインドール行きのバスは来ていないみたいだった。
昼間に警官に読んでもらった時刻表の前で待っていると、またもや警官が現れた。ところがこいつは昼間の警官とは違い、何人も手下を従えてて偉そうな態度のおっさんだ。他にもバスを待ってる客が何人もいるのに、僕にだけ「おまえここで何してんだ」と食ってかかってきた。
「インドールへ行くんだ」
とムッとして答えたが、するとこの偉そうな警官、外人嫌いなのか、
「インドール行きのバスなんかない。とっととどこかへ失せろ!」
「あんたの仲間がここから出るって言ったんだぞ」
と言い返したが、
「そんなバスはないない! どっか行け!」
と虫を追っ払うような態度だ。ここにいて何が悪いんだと言ってやろうとしたが、それも詮ないことで、僕は現実問題を考えた。次はアジャンタ、エローラへ行くつもりだったから、インドール経由コースがないのなら、一旦南下してボンベイ経由コースを取るしかないかな、と迷っていると、僕の口にした「インドール」という地名だけはわかったみたいで、周りにいた人たちが向こうの方を揃って指差した。「インドール」「インドール」と言っている。
すると一人の客引き風の若い男が飛び出して来て、
「インドール・バス・カモン!」
と片言の英語を喋りながら僕を引っ張って行こうとした。僕は振り返りながら、
「インドール行きのバスはあるらしいよ。あんた何も知らないんだねえ」
と権威主義警官どもに言ってやった。偉そうな警官はムッとして黙った。
僕はその客引きにインドール行きバスの乗り場まで連れてってもらったが、もうバスが着いていて、乗客も何人か乗っていた。
僕が客引きに、「あんた客引きか?」と訊いてみると、「そうだ」と答えた。客引きはさっさとバスに乗り込むと、三人掛けの席を確保した。僕を窓際に座らせ、自分は隣に腰を下ろす。少し話をしたが、片言もいいとこで、ほとんど単語しか喋れない。
「ホテルは?」と訊くものだから、どうせ僕を自分のホテルに連れてこうとしてるのだろうと思っていた。
それから少しして、彼は「席を取っといてくれ」と言ってバスから降りて行った。僕にはそう聞こえた。更なる客をカモりに行ったのだろう。それからふと見ると、窓の外に立っているではないか。あれ? そこでじっと僕の方を見ている。
「行かないのか?」
「席を取っといてくれ」
また同じことを言った。うーむ、取っとくことは取っとくけど、営業活動はしないのかぁと思っていると、バスが動き出した。客引きの彼は他の乗客を見送りに来た人たちと並んで手を振っている。あれれれー? 僕は手を振り返すだけで精一杯だった。バスはあっと言う間に角を曲がって本道に出てしまった。
納得がいかない。うーん、としばらく考えていたが、結局、彼は単にインドール行きのバスに案内してくれて、夜行だから横になって寝られるようにと三人掛けの席を取ってくれただけだったのだという結論に達した。
そうすると凄い後悔の念が湧いてきた。ろくに礼一つ言えなかった。彼から純粋に親切にしてもらったという感謝の思いもあるが、自分のことが凄く悔しくてならなかった。僕が訊いた時、彼は
"Take the sheet" とだけ言った。せめてその前に "I" とか
"Only" とかつけてくれていれば、僕にも彼がバスから降りてじっと立ってる時にすぐわかったのに……。
僕は他の多くの日本人旅行者ほど警戒したり、偏見を持ってインド人を見ていないつもりだった。だけど、客引きだからどうせ裏がある、と無意識に構えていたようだ。「その人の職業や肩書きでその人自身を判断することはできない」ということは昔から百も承知のことだったのに、インドに来て次から次へとひどいリクシャー・ワーラーや客引きにばかり出くわしているうちに、いつの間にか[リクシャー・ワーラー
= 悪人]、[客引き = 悪人]という公式が出来上がってしまっていた。素直に人に接するというのは難しいことだと改めて思い知った出来事だった。
僕は自分に自分のプライドを傷つけられ、恥じ入りたい心境だった。なんで彼に素直な態度で接することができなかったのだろう。たとえ騙されて詐欺に遭ってたとしても、これほど悔しい思いはしなかっただろうに……。彼は僕のことを「薄情な日本人」だと思っているだろうか? いや、見返りを期待して親切にしたわけではない彼は、そんなことは思いもしないだろう。だからこそ、余計に悔しくて自分のことが情けなくなってしまった。
バスは真っ暗な中をデカン高原へと上って行く。開け放った窓から吹き込んで来る風が嘘のように冷たくなってきた。僕は見ず知らずの彼が取ってくれた三人掛けの座席に横になった。道がひどいのか、このバスもたまにジャンプした。それでも是が非でも
"Take the sheet" の三人掛けで寝て行ってやろう。今の僕にできることはそんなことしかない。天井を睨んだままじっと考え込んでいると、涙が出てきた。
4月17日 晴 〜 インドール 〜
バスがジャンプする度に目が醒める。客引きの彼が三人掛けを取ってくれたお蔭で、途中から横になって寝ることができた。しかし道がひどいのか、それともバスがボロいのか、滅茶苦茶揺れる。全ての振動が体に伝わってくる。
やけに陽気な奴が話しかけてきた。何を言ってるのかあまりわからないが、独身かと訊いてきたので、そうだと答えると、「俺の村のウジェインに来て、村の娘と結婚しろ」といきなりそんなことを言う。適当にはいはいはいと返事してると、途中で男はバスから降りた。
真夜中だというのに、バスから降りてもまだ窓の外にいて話しかけてくる。ライター貸してくれと言うので貸してやったら、煙草に火を点けないでずっとぐずぐず話してる。やっとバスが発車したと思ったら、やっと火を点けた。バイバイと手を振っている。あっ、やられた。ライターちょろまかされた。
インド人の男は初対面の人に向かっていきなり結婚してるかどうかよく訊いてくる。インド人の女はどうなのかまでは知らない、出歩いている奴はほとんど男ばっかりなので。名前とか歳とか尋ねる前にまず結婚してるかどうかだ。初対面の男にそんなことを訊かれるとゾッとする、こいつ、あの気があるのかぁって。
バスは八時頃に終着駅に着いた。しまった! どうやらインドールを通り過ぎてしまったようだ。最近は無の境地でい過ぎるなあ。折り返しのインドール行きを教えてもらって飛び乗った。92ルピーで来たのだが、行き過ぎた分、14ルピーと時間を損した。いや、時間はあり余っている。別に損もしてないか。
八時半頃になると急に暑くなってきた。デカン高原に上がったので、少しは涼しくなるかと期待もしていたのに、朝っぱらからこれじゃ、ちっとも灼熱地獄から抜け出られてはいないようだ。太陽に近づいただけなのかもしれない。先が思いやられる。
インドールのバス・スタンドに着くと、旅行店の客引きが寄って来た。無の境地でそのままついて行く。ここは次の目的地、アジャンターまで行く直通がないので、単なる中継地点に過ぎない。クソ暑いし、早く離れるに越したことはないだろう。
店まで行くと、店主が出て来て、
「ジャルガオンまで150ルピーだ」
「高い。ローカル・バスで行くよ」
ちなみにアジャンターまで真っ直ぐ行くバスはないのか訊いてみたが、やっぱりないらしい。
「俺はアジャンター、エローラへ行きたいんだ」
「それならアウランガバードへまず行くんだね」
そのコースがあるのは知っている。
「バスはあるのか?」
それに対して店主はなぜか、
「うちのがある」
と言った。
「いくら?」
「170ルピー」
と言って、店主は値段表を指差した。決して安くはないのだが、アーマダバードからの脱出に苦しみ、これからも乗り継がなければならないことを考えた僕は、それでも心を動かされた。アウランガバードを拠点にして、アジャンター、エローラを見に行くという方法もある。
「よし、それ買った」
「ちょっと待ってくれ」
予約を取ると言って、店主は早速電話した。
「OKだ」
今夜七時半にこの店の前を出て、明日の朝七時にアウランガバードに到着するということだ。ラッキーだ、こんなに簡単に移動ができるとは。アーマダバードのあの苦戦は何だったんだろう。あとは晩になるまでゆっくりして過ごそう。まだ年端もいかない店主の息子が店の使いっ走りをさせられている。この子に10ルピーやって荷物を見張らせることにした。
身軽になり、時間もできたことで、久しぶりに日本に絵はがきを出そうと切手を買いに郵便局へ。郵便局から出ると、暑さにうんざりしてきた。どこかぶらぶらと見に行こうと思っていたのだが、もうめげてしまった。
インドールにどういった見所があるのか情報不足のためわからないので、まあいっか、どうせここは通過地点なんだから、と街の中心部へと引き返す。実際にはこのインドールの近くにはウジェインというヒンズー教の聖地があり、前出のライター泥棒の故郷だが、ここに寄って来ればよかったのかもしれない。
と言うのは、のちに僕がインド半島一周をほぼ終えかけ、プリーという所にいた時、インドにのめり込んでもう一年以上もあちこち放浪しているオーストラリアの若者に出会ったのだが、僕がどこそこを通って来たと一々地名を上げていると、彼は『インドール』という地名にだけ大いに反応を示した。インドールがどうというのではなく、そのそばにあるウジェインの祭は凄いんだ、行きたい、行きたいと熱弁をふるっていた。
ふーん、じゃあ村娘を口説かないにしても、インドールじゃなくてウジェインを経由してくれば良かったかなあと思ったものだが、考えてみると、僕は祭というものには感動しない人間なのである。ああいうこの時とばかりに発散する集団ヒステリーの類は嫌いだ。そもそも、インドの街というものは、どこでも毎日お祭をやっているように見えて仕方がない。もういい加減静かな場所でゆっくりさせてくれー、と最近は思うようになってきた。だからウジェインを通り過ぎたことは正解だったということにしとこう。
レストランで時間をつぶし、カフェでまた時間をつぶす。冷房なんか入ってないのだが、扇風機があり、日陰になっているだけ外よりはましだ。その間に絵はがきを十数枚も書き終えてしまった。僕が日本で書くおよそ三年分の年賀状の数に相当するではないか。こんなにいつまでも店に居座っている客もいないだろう。それでも嫌な顔一つされず、ウェイターは笑顔で注文の品を持って来てくれた。インドのコーヒーはどれもミルク・コーヒーなので、何杯も立て続けには飲めないが、僕にとってはチャーイを何杯も飲むよりはましだ。
新聞にどこかの大学教授か誰かのインド論が載っていたので、その時ちょうどインドに行く直前だったこともあって、たまたま読んでみたのだが、何のことはない、ちょっと数日旅行会社のインド・ツアーに参加して、それだけで「インドはこういう国だ」と安易に決めつけている安直偏見論なのだった。なぜかこの大学教授の全身写真まででかでかと載っていた。そんなもの誰が見たいんだよう。
その中に、「インドでは郵便物は八割方届かない、インドは全く遅れている」と書いてあったので、そうなのかと警戒し、どっちでもいい人はともかく、特定の友人には何枚も絵はがきを出したものだが、結局日本に帰ってみると、みんな絵はがき届いたよと言っていた。数十枚の絵はがき、一枚残らず届いたのだ。
八割届かないどころか、十割ちゃんと届いてるじゃないか。どうせこのじいさんがもうろくしてて、八割方宛名を書き間違えてただけなのだろう。子供が書いたみたいな僕の汚い字でもちゃんと届いたのに、この大学教授じいさん、よっぽど字か下手くそなんだろなあ。自分のへまをインドの郵便局のせいにするなよなあ。
それでもまだまだ時間が余ってたので、新聞を読むことにした。例の『リグ・ヴェーダ』はやっぱりちんぷんかんぷんなので、数分読むともうめげてしまい、時間つぶしには使えない。英字新聞だから、これもすらすらとは読めない。「昨日新彗星が発見された」とかいう類のちっちゃな記事がいっぱいあって、日本の新聞とは趣が違う。写真を多用しないせいもあるのか、おとなしめでアカデミックな感じがする。
そうやって眺めていると、『昨日の最高気温』という欄があった。各主要都市名とその最高気温がずらずらーっと並んでいる。そして見出しは大きく、「第一位はハイデラバード、41.7℃!」といったふうなものになっていた。そんなこと自慢するなよなあ。こんなの見てるインド人たちは、「今日こそはうちが一番暑くなってやるぅ!」などと、競争心を燃やして熱くなっているのかもしれない。
ようやく時間が来て、旅行店の子供に案内されてバス乗り場まで行くことになった。客の荷物をみんなリヤカーに積み、何人かの子供が引っ張って行く。小さな女の子までついでにリヤカーに積まれた。
ところが待合所に着くと、様子がおかしい。待合所の係の事務員が僕のチケットを見て、ここじゃないと言っている。どういうことか訳がわからないので説明してもらうと、僕のチケットはジャルガオン行きになっていて、値段は140ルピー。その二カ所だけがヒンドゥ語で書かれていて、僕には読めなくなっていた。
アウランガバード行きの170ルピーを買ったんだと主張してみたが、そうは書かれてないんだと言われ、それっきりだ。予約も入ってないと言う。旅行店のおっさんにまんまと騙された。
「俺をなめんなよお!」
こんな手が通用すると思ってんのか! ムカッ腹を立てた僕は、そのまま旅行店まで引き返して行った。店主の息子が驚いて僕について来た。店まで来ると、手下だけがいて、神棚に線香を上げている。
「おい、おまえの主人はどこ行った。あの詐欺野郎出せ!」
手下はこういうのには慣れているのか、ちょっと待って、と奥に入って行った。少しして戻って来ると、
「今いないよ」
「早く呼べ!」
「もうちょっと待ってくれ。もうすぐ帰って来る」
僕の怒っている様子を伝えに行ったのか、少しすると詐欺師店主が表から入って来た。たぶん計略を考えたあとに裏口から回って来たのだろう。
「おい、こら! これは何のつもりだ!」
僕が怒鳴ると、ニヤニヤ笑ったまま、
「ちょっと待ってくれ。これからお祈りの時間だ」
僕を待たせたまま、神棚に貼ったシヴァ神の肖像画に向かって拝み始めた。「上手くこの場を切り抜けられますように」とでも拝んでいるのだろう。悪人が祈ってどうする? 天罰が下るがいい。
やがて祈り終わると、顔に愛想笑いを浮かべたまま僕の方を向いた。
「どうしたんだ?」
「なにとぼけてやがんだ! これはなんて書いてあるんだ? 俺を騙しやがってぇ!」
僕はチケットのヒンドゥ語の部分を指差しながら詐欺店主に食ってかかった。
「騙してなんかないよ」
「嘘つけ!」
「俺は生まれてこの方、嘘なんか一度もついたことない」
とことんしらばっくれるつもりだ。
「よーし、そこで待ってろよ。嘘ついたことないかどうかはっきりさせてやる」
僕は店を飛び出すと、黄昏の雑踏の中を探し回った。戻って来る時に、所々に警官がぼけーっと突っ立ているのを見て知っていたからだ。あいつらにもたまには働かせてやろう。早速一人見つけて事情を説明してみたが、こいつはまだぽけーっとしている。英語がほとんど通じないようだ。
「騙されたんだ、騙されたんだ。とにかくついて来てくれ」
と言って、僕は警官を旅行店まで引っ張って行った。
警官を連れて来たのを見て、詐欺店主は猫なで声になって何かヒンドゥ語で言い始めた。
「170ルピー払ってアウランガバード行きの切符を買ったのに、こいつはわからないようにその部分だけヒンドゥ語で『140ルピー』『ジャルガオン』と書きやがったんだ。俺は金をだまし取られた挙げ句、バスにまで乗りそびれたんだぞ。こいつを死刑にしてくれ!」
警官に向かってチケットを示しながらわめき立てたが、ちっともわかってないみたいだ。店主の方は僕の言っていることがわかっているので、慌てたのか、益々猫なで声になり、更に更に愛想笑いを作ると、警官にヒンドゥ語で何だかんだ言った。さっきから呆気に取られていただけの警官はふむふむと頷くと、
「まあまあまあまあ」
と僕をなだめようとした。
「何がまあまあまあまあだ。こいつをここで今すぐ死刑にしろ!」
警官のおじさんはちんぷんかんぷんだったのかもしれないが、店主はびびったみたいで、急いで電話して、新たに予約を取り直す。新しいチケットに、『ジャルガオン』『160ルピー』と今度は英数字で書き込むや、10ルピーをつけて僕に差し出した。
「なんだこの160ルピーってのは、ジャルガオンは140ルピーじゃなかったのか、え?」
「余所のバス会社の特等席だから、ちょっと高いんだよ」
詐欺店主はチケットに『特等席』と英語で更に書き加えると、愛想笑いを崩さずに、僕の顔を見上げた。この期に及んでまだ人をなめてやがる。怒りは収まらなかったが、これに乗らないともう一日無駄になるだろうとも思えたので、こいつを獄門首にできずにこの地を去るのは悔しいが、仕方なく妥協することにした。
店主は自分の息子にこの人をまた連れてけみたいなことを言ったようだった。唖然として事態を見ていた子供が僕をまた案内しようとする。
「今度騙したら承知しないぞ! 今度こそ死刑だ!」
腹立ち収まりやらぬ僕は捨て台詞を吐いて出て行こうとした。
「インド人は正直者だ、神に懸けて!」
詐欺店主はシヴァ神に向かってしゃあしゃあとぬかしやがった。こいつめ、とまた腹を立て、
「そうさ、インド人は正直者だ。おまえ以外はな」
吐き捨てるように言って店から出た。店主はへへへと笑っているだけだった。詐欺師とはこういうものだ。何を言われようと腹を立てた様子を見せない。
またさっきの待合所まで来て、置き去りにしてきた自分の荷物をつかむと、リクシャーが表にやって来た。あらかじめ詐欺店主が連絡してあって、こいつに乗って別の乗り場まで行くということだ。
リクシャーに乗り込むと、詐欺店主の息子と、もう一人、トラブル発生の時に気を利かせて係に掛け合ってくれた、バスを待っている正義漢の乗客のおじさんがいて、二人揃ってリクシャーの中まで首を突っ込んできては、
「あなたは払わない! あなたは払わない!」
「あなたは払わない! あなたは払わない!」
と二人して必死に叫んでいる。このリクシャーに料金払うな、払う義務はない、と言いたいのだとわかったので、
「払わないよ、安心しな。ありがと」
二人に手を振った。リクシャー・ワーラーはエンジンをかけて急いでリクシャーを出した。後ろでいつまでも「あなたは払わない!」と二人が叫ぶ声がしていた。あの子は小学生くらいだったろうか、子供心にも自分の父親があくどいことをしていると薄々勘づいているのかもしれない。
荷物運びをさせられていた詐欺師の息子と、単に居合わせただけの見るからに人が善さそうな正義漢のおじさん、動き出そうとするリクシャーに二人して顔を突っ込みながら、「あなたは払わない!」と叫んでいた光景は、なぜか未だに忘れることができない。
乗り場はかなり遠かった。そこはプライベート・デラックス・バスが発着するスタンドだということだ。バスが何台も停まっていて、どれに乗ればいいのかわからない。リクシャー・ワーラーに尋ねると、ついて来いと言う。近くの売店のような所に入った。そこには男が三人待ち受けていて、ワーラーが親分格らしき太った男に何事か告げた。太った男はふむふむと聴いていたが、やがて、
「あんたはこの人に20ルピー払うべきだ」
と僕に向かって言った。ははん、さっきのやりとりから、どうせ要求しても払わないだろうと踏んで、加勢を頼みやがったのか。
「なんでだっ!」
と大声で言ってやると、太った男はびびったのか、口をもごもごさせて何か言った。ふん、頼りない親分じゃないか。
「何だって?」
僕はまだ怒りやんでなかったので、脅すような口調になっていた。親分は急に腰が低くなり、説明を始めた。
「この人はあんたをリクシャーに乗せた。労働したんだから、当然報酬をもらわないと……」
「それならあの旅行店に言ってくれ。俺の知ったことか」
「だけどなあ……」
とまだぐずぐず言っている。しかし僕にも弱みがあった。どのバスに乗るのか、このワーラーに教えてもらわなくてはならない。理不尽なことではあるが、20ルピーのことでいつまでもトラブってても仕方がない。
「しょうがない。払ってやるわ」
20ルピーをつかみ出すと、ワーラーに押しつけた。
「どのバスだ?」
ワーラーはバスまで案内した。乗り込んでチケットを見せると、指定席で、車掌が僕を席まで連れてった。
やっとのことでバスが発車する。バスが走り出すと、急にいろんな色の豆球が点滅しだした。なんだこりゃ? このバスはクリスマスツリーかよ。何が『プライベート・デラックス・バス』だ。派手派手なだけじゃないか。
途端にテレビが点いてインド映画が始まる。言葉はわからないが、見てるだけで筋がわかる他愛もないものだ。60年代の日活映画を彷彿とさせる、ヒーローが悪漢どもと闘い、美女を救い出すという、子供騙しもいいとこだ。テレビがまだ普及しきっていないインドでは、この手の映画が馬鹿受けするのだ。そしてインドのヒット曲と言えば、まずこの手の映画の挿入歌なのだそうだ。
しかし一つ笑えるのは、ドラマの途中でいきなり歌って踊り出すところだ。ヒーローとヒロインが掛け合いで歌ってるかと思ったら(歌っているのは別人の歌手だということだが)、突如ダンサーがぞろぞろといっぱい現れて来て、全員で派手に踊り出す。やっつけられたはずの悪漢どもまで一緒になって踊ってたりする。
今日はゆっくり眠れそうだ。何しろ派手派手バスの『特等席』なのだそうだからな。
4月18日 晴ちょっと曇 〜 ジャルガオン 〜 アジャンター
ぐっすり眠ったあと、四時半頃目が醒めた。そのうちみんなバスから降りたので一緒に降りて、そこにいたリクシャー・ワーラーに訊いてみると、「ここはジャルガオンだけど、アジャンターへ行きたいなら、バス・スタンドまで戻らないといけないよ」という返事だった。旅行会社のバスは変な所に到着するのだ。また行き過ぎで、リクシャーに金を払うはめになった。
アジャンター行きは六時半発だったので、結果的には時間のロスはない。このローカル・バスも八時前にはアジャンターに着いた。調子いいぞと思ってたら、これまた行き過ぎてた。このバスはアジャンター行きではなかったのだ。途中のフォルダプルで降りれば良かったのだ。インドのバスはややこしい。
そこにある食堂のおっちゃんや、新聞売りの少年たち、バスを待ってる客などが寄って来て教えてくれる、ジープは高いから乗るなとか、ミニ・バスは八時に出るんだとか。ふんふんと聴いていたが、ふと思い出した――今乗って来たローカル・バスの料金を払っていない。終点で客が降りるのと同時に、運転手も車掌もさっさと降りてどこかへ消えてしまったのだ。
その辺を眺め回してみたが、もう見つかりそうもない。とうとう只乗りをしてしまった。ローカル・バスの只乗りなんかしたくない。リクシャーだったらいくらでも只乗りしてやるんだが。
ミニ・バスに乗ってアジャンターには九時前に着いた。とりあえず腹ごしらえ。ホテルの一階のレストランで朝めしを食うと、そのままそのホテルにチェックインして身軽になる。ここには宿泊施設がほとんどないみたいだ。
州が経営しているこのホテルは、設備がひどいのに値段は高い。125ルピーだった。殿様商売してる。廊下も暗くてしんとしていた。泊まり客はほとんどいないのではないだろうか。アジャンターはゆっくり見てやろうと思い、すぐ近くに泊まることにしてたのだが、実際には半日もあれば充分なので、フォルダプルで泊まった方がいいだろう。
早速石窟を見に行く。なかなかここに来られなかったので、石窟が見えた時には感激した。「とうとうアジャンターに来たぞ!」ライト券を買って入る。入ると言っても、石窟はたくさんあって、その崖に沿って造られている小道の前に来たと言うことだ。そこには横断幕が掲げられていて、『世界遺産記念日』とあったが、だからと言って、特に何も変わった様子はない。見物客は結構多い。
アジャンターの石窟というのは、U字型の川が地面を削ってできた切り立った外側の崖に、谷を取り巻くようにたくさんの洞窟が掘られていて、暗い洞窟の中には数々の壁画が描かれている、古い遺跡だ。この深い渓谷の景観だけでも見応えがある。
ライト券というのは、ほとんどの洞窟内は暗くて、壁画を見るために弱い光のライトは燈されているのだが、写真を撮るにはそれだけでは暗すぎる。しかし壁画に良くないとかいう理由で、フラッシュを焚くことが禁止になっていて、代わりにこのライト券を出して反射板で外光を洞窟内に入れてもらうために必要な切符なのだそうだ。
しかし僕のシンガポール製最新型安物カメラでは、どうしようと自動的にフラッシュが焚かれてしまうのだった。ああ、アジャンターの世界文化遺産である壁画を劣化させるのに一役買ってしまった。
石窟群を見終わると、ホテルのレストランへ行き、石窟で知り合った日本人女性二人と一緒に食事した(ここには食う所も泊まる所もほとんどないのだ)。その時ふと思い出し、『蓮華手菩薩像』と『金剛手菩薩像』を見なかったなあと言ったら、入ったとこの一番最初にあったよと言われた。
これは例の『○○の○き方』に書いてあったのだが、法隆寺金堂壁画の原型なのだそうだ。僕はインドに来る前に、写真でだが双方を見比べて、これはよく似ている、アジャンターへ行ってその謎を解き明かしてやろうと思っていたのだ。
飛鳥時代の頃の仏教建築・美術などは、まず百済からの亡命者などの渡来人の手によるものであるはずだ。そうするとその絵は百済など、朝鮮半島の仏寺にあったもの、または中国(当時だと隋・唐初期)の仏寺にあったものを見てきてモデルとしていると考えるのが妥当だ。そのまた原型はインドで見てきたか、インドから招かれて絵描きが描きに来たかだろう。
この法隆寺金堂壁画とアジャンターの壁画を見比べると、似ている。似ているが違っているところもある。思うに、これは壁画家のアドリブで変えたのではないだろう。当時はスケッチなどはしていないと思われる。あくまで仏教画家は敬虔な仏教徒であり、自分の脳裡にモデルを焼き付けていたはずだ。
原型から逸脱しないようにという意図があったはずで、だからかなり似ているのだが、それでも違っているところもあるのは、人間の脳という曖昧な場所にスケッチされて運ばれて来たというところにあるのだろう。それもかなりの時間的間隔を置いてから再現しようとするので、更に記憶は薄れている。
それがまた何人かの画家によってリレーされるうちに、更にずれが生じてくる。小学生の頃、教室で伝言ゲームというのをやったが、渡された紙に書かれた内容を前の席の人の耳に囁く。また前にいる人の耳に囁く。そうやって最後に一番前まで来てから発表してみると、元の紙に書かれた文句は一つだったのに、各列が言ってることがてんでバラバラになっているのだ。
小学生とはいえ、短い文でほんの数分でもこれなのに、それを考えると、インドから日本に来るまでのこの壁画のずれというのは、違ってきたと言うよりは、よくぞ狂わなかったと言った方がいいのではないだろうか。
しかしそんなことを前もって考察していながら、いつものこととはいえ、またも肝心な時になって肝心なことをすっかり忘れて見落としていたのだ。しまったとは思いながらも、僕は壁画研究家でもないので、また引き返して入場する気にもなれない。まあいっか。
と言うか、ここの数々の壁画は、たいていぼろぼろになっていて、期待外れだった。僕みたいに無神経な観光客たちがフラッシュをバシバシ焚いたせいなのだろうか。しかし形ある物は必ず滅びる。『無常無我』である。それも仏の教えに適っているではないか。壁画がどうのこうのと言うことより、信仰のために崖にこんなにたくさん穴を掘って絵を描いたという、そっちの方こそ僕には驚きで、一見する価値があったと言うものだ。
石窟群の入口の手前に唯一の繁華街があり、いや、繁華街などと言う代物ではなく、市が立っているという感じで、土産物屋が少しばかり並んでいるだけだ。ここには観光客相手の商売人以外、人は住んでいないみたいだ。ホテルに部屋を取ってしまったからしょうがない、ここに明日の朝まではいなくてはならない。もう行く所もないので、ぶらぶら土産物屋でも覗くことにした。
店の人も暇みたいで、結構しつこい。いらない、いらない、見てるだけ、と言っても、やっぱり必死で土産物を売ろうとするが、僕が買わない様子なので、例の如くどんどん値が下がる。ここは外国人観光客も多いみたいで、ドル売りなんかしてるが、知らん顔してると、そのうちルピーになり、更に値がどんどん下がる。
原石を割ったのがあり、中が空洞で、水晶の結晶ができている。割った二つを合わせると、ただの石ころにしか見えない。へー、と珍しいので、5ルピーとか10ルピーまで下がってからいくつか買った。重いと邪魔になるから、小さいのにしてもらった。
「こいつは10ドルとか20ドルとかで売ってるんだけど、日本人ならそれでも安い安いと言って買って帰るぞ」
土産屋はそう言った。悪かったね、ケチな日本人で。すると暇なのか、隣の土産屋や籠かきのおっちゃんまで寄って来て駄べり始めた。日本人はお人好しでいいカモだとか、日本人の僕を前にして言っている。
そのうちどこで覚えてきたのか、土産屋二人で変な日本語を喋りだした。やばいこと言ってはげらげら笑う。
「アナタノ○○○○ニ△△△ヲ×メテアゲル」
「アナタノ○○○○オイ◇ソウ、ホ◇イホ◇イ」
と、伏せ字にはしたものの、この手のあまりにも露骨なフレーズを二人して大声で掛け合い漫才のようにわめきだした。
「それは言っちゃいけない言葉なんだぞ」
とたしなめてみたが、なおさら面白がって叫びまくる。意味わかって叫んでるのだろうか。それはこうこうこういう意味なんだぞ、と教えてやると、二人とも急に黙り込んだ。
「良くない言葉だ……」
とぽつっと呟くと、二人とも急に悄気てしまった。日本人から教えられたということだ。これまでにもそういうのを何人か見てきた。街角につっ立って、「ナニイウテマンネン」と関西弁をぶちかますおっさん、道で日本人に出くわすと、挨拶代わりに、「ボクハアホバカマヌケデス」と言って笑う子供。ろくな日本語を教えちゃいない。
うーむ、日本人の恥だ、と苦々しく思っていると、やがてこの二人、もっとやばい別のフレーズでわめき立て始めたではないか。その四つか五つのフレーズがローテーションして繰り返され、二人でお下劣な輪唱をおっ始めやがったのだ。なんだ、こいつら人をからかってやがんのかぁ。
籠かきのおっちゃんはいい人だった。これからどこ行くんだと訊くので、展望台に登ろうと思ってる、と目の前の小山(U字になった谷川の内側)を指差してみせると、夕方には展望台には登るなと言う。コブラが出るのだそうだ。
「だから明日の朝連れてってやろう」
うげっ、そんじゃもう登るのはよそう。朝だからコブラは出ないなんて保証があるわけでもなし。
しょうがないから早々にホテルに戻り、早めに晩めしでも食うかと思ってレストランに行くと、もう終わっているではないか。フロントとかその辺も探してみたが、誰もいない。洗濯おばさんだけいて、洗濯してやろう洗濯してやろうとうるさい。
この洗濯おばさんに訊いてみると、五時になったらここはみんな閉まるんだということだった。みんな村から出勤して来てて、村に帰ってしまうそうだ。窓から外を見てみると、『繁華街』もみんな店が閉まり、人っ子一人いない。それにしても、いくら公営だからってホテルまで五時に閉めるなよなあ。けしからん!
「俺のめしはどうしてくれるんだっ!」
レストランの椅子に一人ぽつんと座ったまま叫び声を上げてみたが、誰もやって来はしない。しんと静まり返っている。幽霊屋敷の山姥のように、洗濯おばさんだけがまたもや「洗濯してやろう」と言い寄ってくるのだった。
 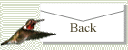
|