|
6.おまえが逮捕した! いばらの道の脱出行
4月10日 晴一時曇俄雨 〜 ウダイプル
白人の女はバスの中でも平気でブーブーと洟をかむ。学生の頃、とある西洋かぶれの英語教授の授業を受けていた英文科の友人が文句を言っていたのを思い出した――冬になると静かな教室内では洟をすする音があちこちでちらほらと聞かれるようになる。冬の風物詩とでもいったものだと思うのだが、すると西洋かぶれ教授、はたと講義の手を止め、
「そこっ!」
と指差されたと僕の友人は腹を立てながら言うのだった。何を言われるのかとビクッとしたところ、
「西洋では洟はかむものです」
そう言ってまた講義を続けようとしたらしい。そいつはまだ血気盛んな学生盛りなもんでムッとして、
「ここは日本ですよ」
と思わず反論したらしい。するとこの西洋かぶれ教授、いい歳して大人げない人だったのか、
「今この教室内は西洋です」
としたり顔でのたまわれたそうだ。そのためか授業終了までもう洟をすする音がパタリとやんでしまったそうだが、授業が済んで教室から出て来た大学生たちの顔は、小学校一年生みたいに洟たれ坊主だらけになっていたかもしれない。
しかしインド人は手洟をかむ。女でも平気でバスの中で手洟をかむし、窓からも「くわーっ! ぺっ!」とたんを吐き飛ばす。『郷に入っては郷に従え』紙で洟をかめと言われればそれくらい僕にだってできるが、かぶれ教授の理論によると、ここは仮でもなんでもなく現実にインドのバスの中だから、まさしく手洟をかまなくてはならないということになる。これはちょっと難しかろう。地面に洟をきれいに飛ばすには、ある程度の修練の必要がありそうだ。それまでには顔じゅう洟水まみれになってしまっているに違いない。無論、それは法律でも義務でもないのだから、僕の場合は『郷に入っても郷に従う』とは限らない。
インドでどうしても郷に従えなかったことは、「排便後の後始末」である。インドの宿には、相当な高級ホテルでもない限り、どこにでも大きめのビニール製のカップが置いてある(いや、実はどんな高級ホテルだろうと、インドのホテルなら必ずあるのだとあとで教わったのだけれど)。そこには水道の蛇口があるか、なかったらバケツに水を汲んで置いてあったりする。知らずにインドへ行った日本人で、この『カップの謎』を解ける人はまずいないだろう。
そしてトイレットペーパーというものは備え付けられてないから、持ち込まなかった人は、クソを出し終えたあとで当然「どうしよう」という問題に突き当たることだろう。その辺の売店で売ってるから、旅行者はトイレットペーパーを買って持ち歩けばいいのだが、インド人は習慣としてペーパーではなくカップを使うらしい。
ここまで言えば、勘のいい人はもうどうするかなんとなく想像がついたとは思うが、要するに『謎のカップ』の答は『手動ウォシュレット』なのだ。インド人は右手に水を入れたカップを持ち、ケツにひっかけながら、不浄の左手でこすり落とすらしい。だから握手や食事、物の受け渡しにはこちらの手はまず用いない。電動ではないにしても、ウォシュレットはインドには何千年も前からあったというわけだ。もちろん、こうやってやらずもがなのことをつぶさに解説してはみたが、決して僕はその様子を実地に観察したわけではない。あくまで伝説である。
しかしこの伝説の技を用いようとした日本人もいた。カジュラーホーからデリーまで一緒だった富豪高校生、銀孫クンである。これもまた、銀孫がケツを出しているところを僕が実地に覗き見して目撃したわけではないから、これまたあくまで伝説の域を出ないのだが、ある時、二人で一緒に必需品(煙草とか)を買い物している時、「スポンジはないか」と彼は売り子に訊いていた。
何軒か店を回ってそれを繰り返していたのだが、あいにくとスポンジは見つからず、結局彼はナイロンたわしを買った。食器でも洗うんだろうと気にしていなかったが、考えてみれば僕も銀孫クンも外食しかしないから、食器を洗う必要はないし、銀孫クンは別に何に使うとも言わない。じゃあたわしで体洗う気かあ、と一応勝手に納得しといたが、ある時、トイレにそのナイロンたわしが置いてあるのに気がついた。
「うーん、これは銀孫のたわしじゃないか……」
しゃがんだままそのたわしを見つめていた僕は、変な想像が頭に浮かんだ。
「まさか……」
こうして新たに銀孫伝説が誕生した。右手にカップ、左手にたわしかよう……。そう言えば、あいつ、トイレットペーパー持ってないなあ。若い頃というのは何をやらかすかわからない。インドにかぶれて習慣まで合わせようという『郷に入っては郷に従え』精神は見上げたものだが、さすがに素手は抵抗があったみたいだ。しかし何もこのような折衷案を考え出さなくたって……。このあと彼は痔になったに違いない。まあ、若者の特権だ、それはそれでいいだろう。
話は最初から逸れたが(話が最初から逸れたというのは厳密には間違った言い方かもしれない)、バスは朝の五時半にウダイプルに到着した。まだ空は真っ暗だ。それでバス停のベンチに腰を下ろし、最近身に着けた『無の境地』でしばらくいると、やはりここでもリクシャー・ワーラーが接近して来た。『無の境地』など、インドではなかなか続けられるものではない。
こいつは今までのワーラーとは少し趣が違っていた。僕があんまり反応しないでいると、ホテルの名刺を次から次へと出しては、値段がいくらとか場所がどうとか一々解説しだした。まず選択権をこちらに与えるなど、ワーラーっぽくないなあと思い、少し訊いてみると、学生で、休み中のバイトでリクシャー・ワーラー兼ホテルの客引きをしてるんだと言う。僕は与えられた選択権を早速行使して、ここが良さそうだなあ、とババぬきのようにホテルの名刺を一枚抜き取った。学生ワーラーは喜び勇んで僕をリクシャーに乗せ、ホテルまで連れてった。
ホテルに着くと、番犬が一頭、吠え立てながら僕を出迎えてくれた。人はまだみんな寝てるみたいで、学生ワーラーのCがインターホンでわめいてボーイを起こしてくれた。眠くて面倒だからなのかもしれないが、マネジャーがまだ寝ているので、それまで空いてる部屋で待っててくれと、部屋を用意してくれた。僕はそのままその部屋で午まで寝た。
目が醒めて部屋から出てみると、もうフロントに人がいた。そこで早速チェックイン。150ルピーのダブルルームを、一人なので80ルピーに負けてくれるそうだ。インドの安宿にはシングルルームは滅多にない。個室に泊まりたければたいていダブルルームしかない。だがこういう割引をしてくれる所もたまにあるので、一人旅には嬉しい。
もっといい部屋にしてやろうということで、仮に寝させてもらっていた部屋から隣の部屋へと移った。パハディ・ホテルというのだが、部屋は広くて綺麗だし、シャワーも熱い湯が常に出るし、これまで泊まった安宿の中では一番いいホテルだと思った。湯が出るのがどうしたんだと思われるかもしれないが、シャワーから熱い湯が出るということは、インドの安宿では驚くべきことなのである。
湯どころか、僕の知り合いがかつてインドへ一人で行った時、空港で客引きに強引に連れてかれたホテルなんかでは、顔を洗おうと水道の蛇口をひねったら、水の代わりに得体の知れない虫がざわざわと流れ落ちてきたそうだ。しかしホテルの善し悪しを何によって判断しているのかと考えてみれば、設備なんかよりも、結構そこの従業員の態度にかなり重点を置いて「いいホテル」「良くないホテル」と決めているような気もする。
そこで気分を良くした僕は、湖の町として知られているウダイプルの綺麗な湖を眺めてもっといい気分になろうとホテルから出た。しかしここには湖がたくさんあるが、町の中心部近くにある湖は、どれもこれも『綺麗な湖』なんて代物ではなかった。
ピチョラー湖というこの辺で一番大きくて、町の顔みたいになっている湖などは、それはもう『巨大などぶ』と別称を与えてもいいくらい水が汚かった。
インド人は水があればそこは体の垢を擦り落としたり、汚物を流し込む場所だと決めつけているみたいで、人がたくさんいる所では、それがたとえ海でも綺麗な水などは期待できない。ましてや内陸部で綺麗な淡水を見たければ、その上流部をも含めて人がほとんど住んでいないような湖水を探さなければならないだろう。さもなければミネラルウォーターのボトルでも眺めながら、美しい湖で泳いでいる自分を想像するしかない。
このピチョラー湖の東岸が町の中心部らしく、湖岸にシティ・パレス(王様の宮殿)がある。虎の巻によると、ここの王は『マハラジャ』ではなく、『マハラーナ』と呼ばれるらしい。違いは、かつてイギリスに降伏したか、しなかったかで、降伏しなかったマハラーナはマハラジャより誇り高い王なのだそうだが、今となってはどっちでも同じことだろう。ここも拝観料に加え、宮殿の一部をホテルやレストランにして生計を立てているようだ。
せめてレストランだけでも王様の気分に浸ろうと行ってみたという人から聞いたが、さすが宮殿の一角だけのことはあって、豪華な部屋だし、高そうなので、この人はビール一本だけ頼んだそうなのだが、そうすると着飾ったインド美人がビールを捧げ持って来て、傍らに侍りながら、飲み終えるまでずっとお酌をしてくれたということだ。まあ、そういうので感激するかどうかは人それぞれだと思うが、僕なんかは見ず知らずの人に付きっきりでいられると気詰まりになってしまうだろうし、却って迷惑に思うに違いない。
それどころか、宮殿の中を見物しようと入場券を買おうとしたら、今つりがないから大きな札では切符を売れないと言われ、もうそれだけで札を崩してまた戻って来るのも面倒になり、じゃあいいやと、結局宮殿の中にも入らずじまいだった。
そこで、ぶらぶらと近くにある土産物屋を覗いていると、ある男が近づいて来て、
「絵を描いてるんだが、見てくれ」
と声をかけてきた。暇つぶしにその男の店の中に入って見てやることにした。この店の主、自分で描いて自分で売ってるのだと言う。僕の前で絹に描いた細密画を拡げるや、
「ディス・イズ・100ルピー。ベェーーリベリ・グッド・ワン!」
と変な節を付けながら、頭のてっぺんから絞り出すようなかん高い声でいきなり売り込みを始めた。僕が興味のなさそうな顔をしていると見るや、すぐに次の絵を拡げ、またもや、
「ディス・イズ・200ルピー。ベェーーリベリ・グッド・ワン!」
とやらかした。その調子で、
「ディス・イズ・300ルピー。ベェーーリベリ・グッド・ワン!」
とだんだん熱が籠もってきたが、どれも100か200か300かだった。まさに『自画自賛』だ。僕は暇つぶしだったから、
「じゃ、あれはいくら?」
と、主の後ろの壁に掛けてある大きな絹布に描かれた絵を指差して訊いてみた。大きな絹だからさぞかし高いんだろうと思っていると、
「ディス・イズ・50ルピー」
今度は『ベェーーリベリ・グッド・ワン』がついていなかったし、主の声の調子もこれには熱が籠もっていない。思うに、細密画家だから、大きな絵は本人にしてみれば駄作なのかもしれない。そこで今度は試しに一番小さな布に象の絵が描いてあるのを指差して、
「これは?」
と訊いてみると、
「10ルピー」
と、もっと素っ気ない返事をした。確かに絵の端っこに『10Rs』と鉛筆で走り書きしてある。布が小さいからと言って、値段が高いわけでもない。要するに筆致が細かいかどうかで細密画の値打ちを決めているみたいだ。そこで僕は10ルピーの象さんの絵を手に取ると、
「これはなかなかいい絵だなあ。これもらおう。ディス・イズ・10ルピー。ベェーーリベリ・グッド・ワン!」
と称賛してあげた。主はムッとした顔でしばらく黙り込んだ。あはは、じょーだんよ。そこで100ルピーの絵を何枚か買ってやることにしたら、絵描きの自画自賛おやじは途端に機嫌を直し、またまた「ベェーーリベリ・グッド・ワン!」とやりだした。あとはもう面倒になってきたが、毎度の値引き交渉。絵の値段なんてあってないようなものだから、五枚で四枚分の値段ということですんなり折り合いがついた。最後に主は、
「ベェーーリベリ・グッド・ワン!」
と皮肉っぽく言って、10ルピーの象さんの絵をおまけにつけてくれた。別にこっちは本気でそう思って言ったんじゃないんだけどなぁ。それともからかったから仕返しのつもりかぁ。
この日はホテルへの帰りに道に迷ってしまった。と言うより、迷わされた。よくあることだが、ガキどもが勝手に道案内を買って出て来て、最近よく無の境地でいる僕は、何の疑いもなくガキどもの言いなりに進み、そうすると日が暮れてしまったのに、どこだかさっぱりわからない場所を歩いていたのだ。さんざん人に訊きまくって、ようやくホテルに辿り着いた時にはもう遅くなって、僕もくたくたになってしまっていた。この日は途中で知り合ったメキシコ人みたいな日本人と食事する約束をし、あの学生ワーラーCにもお祭に連れてってもらう約束をしていたのだが、どちらもすっぽかしてしまうことになってしまった。
「不可抗力なんだから許せよ」
と、僕は反省しない質なもので、自ら納得して済ませることにした。
それにしてもインド人のガキの道案内ほど当てにならないものはない。なることはまずないと思うが、万が一インドで迷子になってみたい気分になったら、迷わずその辺にいるガキに道を訊くといいだろう。必ず迷える。それにも関わらず間違って正しい道を行けたとしたら、それはよほどの強運の持ち主なのか、さもなくば、何かに呪われているのに違いない。またもやインドの新格言――『迷えば迷わずガキに訊け』
4月11日 晴 ウダイプル
朝、近くにあるファテー・サーガル湖へ散歩して、ホテルに帰って庭で朝食をとっていると、昨日の学生ワーラーCがやって来た。別に昨日僕が約束をすっぽかしたことなど何も言わない。友達からバイクを借りてきたので、それでココダ湖へ行こうと言う。ここは水が綺麗なのだそうだ。ガソリン一リットルの金を出してくれればいいというので、一緒に行くことにした。
この借りてきたというバイク、自転車のペダルがついていて、馬力がないので上り坂になるとすぐエンストしてしまい、ペダルをこいでエンジンを助けてやらなくてはならない。もう日本にはないので、若い人は見たこともないと思うが、これが原付の語源になった、本物の『原動機付自転車』なのだった。僕は小学生の頃、どっかのおばさんが公園で楽しそうに乗り回しているのを一度だけ見たことがある。
これは二人乗りすると非常に厳しい。長い急坂はとうとう上りきることができなかった。帰りに運転させてもらったが、インドでは自動車はおろか、バイクにも乗らない方が無難だろう。田舎道ならいいが、街中を日本人が無事故で通り抜けるなど、まさに至難の業だ。信号なんかないし、右折する時などは、バイクは片手を出して曲がることを合図する(インドは日本と同じで車は左側通行)。それで対向車が止まってくれることもない。自動車、バイク、自転車、歩行者、馬車、牛車、象、牛などが自分勝手に進んでく隙間に向かって、清水の舞台から飛び降りるつもりで覚悟を決めて突っ込んでくしかない。
しかしとにかくインドへ行って車を運転しようなどとは考えない方がいいだろう。大平原の田舎道ならいくらでもすっ飛ばせるから気持ちいいだろうが、街は駄目だ。何度もインド人同士が事故ってるのを見かけたが、インドの交通の無秩序状態に慣れていない日本人ならなおさらのことだ。そして、もし事故って怪我をしたとすると、輸血が危ないらしい。インドの売春婦を買うのも危険だろうが、輸血用の血液をちゃんと検査していないらしくて、インドで輸血されると、八〜九割の確率でエイズに感染してしまうそうだ。それを聞いていたから、伝染病も怖いが、僕は何よりも怪我だけはしないように気をつけていた。
ココダ湖はピチョラー湖などよりは水が綺麗だったが、この程度の湖水なら日本で簡単に見ることができる。近くに人家などないので、ゴミが浮いていないという程度のものなのだが、これでもインドにしてはかなり綺麗な湖水には違いなかろう。
その辺りをゴム草履で歩いていると、テトラポット型のでかい棘が突き刺さり、それが足の裏にまでチクチクと当たって痛い。このいばらか何か正体不明の棘が次から次へと突き刺さってくるので、何度も何度も立ち止まっては、ゴム草履の裏からこの棘を引っこ抜かなければ歩けなかった。このウダイプルには至る所にこの灌木が生えていたが、この棘に覆われた木をものともせず少ない葉を食い尽くしてしまう奴がいた。山羊である。山羊の目というのは他の動物とどこか違っているのだが、こういうのを見ていると、エイリアンではなかろうかと思えてきたりした。
僕が景色を写真に撮っていると、やがてCが出しゃばってきて、いい景色だからここを写せ、あそこを写せと指図しやがる。余計なお世話だ。ところがお義理で数枚撮ってはみたのだが、その度に一々Cが自主的にカメラの前にニタッと笑いながら立ちはだかってくる。景色を写せと言いながら、実は自分を写せというわけか。熊みたいな面でしゃしゃり出て来やがって、せっかくのいい景色が台なしじゃねーかよぅ。
と思っていたら、途端にカメラが動かなくなった。たぶん電池が切れたのか、それともカメラも化け物を見て麻痺してしまったのか、いずれにしろグッド・タイミングだ。――神は我を見放さず!
「あ、カメラ壊れちゃった」
と熊面のCに言うと、僕はさっさとカメラをバッグにしまい込んだ。
その後、別に頼んでもいないのだが、僕はCにあちこち連れ回された。まず生まれ故郷だと言って連れてかれた村で、Cの幼なじみにチャーイを作ってもらった。これは山羊の乳を搾るところから始まった。一杯のチャーイを飲むのにこんなに待ったのは初めてだ。Cはこの娘にチャーイを作らせている間はずっと寝転がっていて、できたチャーイを飲み終わると、次へ行こうとさっさと出て行った。
それから叔母さんちだと言って連れてかれた家では、昼寝をしていたおばさんをCが叩き起こし、ここでは井戸水を嫌と言うほど飲まされた。でも嫌とは言えず、胃がタップンタップンというくらい水を飲んだ。一杯目は冷たくて旨かったのだが、こんなに飲むと溺死しそうだ。それに生水はやっぱり不安がある。
続いて行った村では、同級生のうちだと言って連れてかれた家で、イギリス式のアフタヌーン・ティーをご馳走してもらった。なんだか立て続けに水分ばっかりとらされている。ここのおばさんはクリスチャンだと初めに聞かされたのだが、帰りに僕はお礼にヒンズー式に両掌を合わせていた。おばさんも同じようにして答礼してくれた。Cがそれは違うと横から言ったので、ああそうかと、慌てて十字を切り直したら、おばさんは笑っていた。なんともおおらかな人だ。
しかしこの翌日、当のCの家に招待されたのだが、そこでは何ももてなしを受けたわけでもなく、Cからやたらに「何かくれ、何かくれ」と品物をせがまれただけだった。こいつ、他人のうちで招かれざる客のもてなしをさせといて、自分は物をせびるだけという、なんと見下げ果てた野郎なんだろう。
それでもあちこち連れてってもらったから、別に感謝なんかしてないけど、Tシャツをやった。それでもまだ何かくれとうるさい。ドイツ人の友達からはあれをもらった、これをもらった、そして自分はタイプライターの練習をしていて、代筆屋になろうと思ってるんだと、口から出任せを言ってるのはわかっていたが、じゃあ日本に帰って思い出したらタイプライターを送ってやろうと、こっちも口から出任せを言った。得意の日本式口約束である。誰がそんな物送るものか。
この日は昨日すっぽかしたメキシコ人みたいな日本人に会いに行こうとした。メキシコ人みたいというのは、顔がそうなのではなくて、麦わら帽子をかぶり、このクソ暑いのにポンチョを着て歩いていたからだ。インドにいると、周りのインド人がそうだからか、日本ではできないような奇抜な恰好をして表を歩いている日本人旅行者も多い。日本ではできないから、こういう恥の薄れる国に来てから変な恰好をしてしまうのかもしれない。
昼に昨日待ち合わせたホテルのレストランに行った時は、予想通りメキシコ日本人はいなかった。諦めのいい僕はいつもならそこで諦めてしまうのだが、ここで不吉な寄せ書きを見てしまった。「インドに来たからといって急に楽しいことがあるでもなし、未だに友達もできません……。何もする気がなくなってしまいそうな感じです。あーあ……」という日本語の文章が書かれていた。このホテルは日本人客が多いみたいで、ノートをパラパラとめくってみても、日本語で書いてある寄せ書きだらけだ。
そしてこの不吉な文章の日付は昨日になっていた。うーむ……。この時の僕は、昨日出会った別の日本人から、インドに来ていた日本人大学生がつい最近自殺したという話を聞かされていたところだった。これを書いたのはもしかして、昨日のメキシコかもしれない……。昨日の約束を僕にすっぽかされたので、とうとう人間不信にダメを押され、この書き置きをして出て行ったのならどうしよう……。
「早まるな、メキシコ!」
僕は屋上レストランから駆け下りると、Cの原動機付自転車の後ろに乗ってメキシコを探しに行った。
「自殺するかもしれない」
とCに言って、自分では飛ばすことはできないが、Cにバイクをすっ飛ばさせた。
「それでどこへ行けばいい?」
バイクを精一杯走らせながら、Cが後ろの僕に言った。うむ、やみくもに探し回ったところで、ここは結構広いし、人もそれなりに多いから、おかしななりをしていて目立つとはいえ、簡単にはメキシコを見つけ出せないだろう。そうだな……、
「湖を探してみよう」
最後に湖の町に辿り着いたということから、入水自殺を考えていたということは大いにあり得る。
「湖の周りを走れ!」
「OK!」
とCは心得て、バイクを楽しそうに走らせ、僕は目を皿のようにしてメキシコ風日本人はいないかきょろきょろと見回していた。「それにしても湖の夕暮れ時は綺麗だなあ」、と景色に見とれている場合ではないのだが、結局見つからずじまいで日がとっぷりと暮れてしまった。
しょうがないからもう一度例の屋上レストランに行ってみると、いた。空港のストで日本に帰りそびれて引き返して来たという奴と呑気そうに話してる。あーあ、心配して馬鹿を見た。メキシコはCに向かって、
「カメハメハーってどういう意味かわかんないんだけど教えてくれない?」
と、Cをからかっている。Cは知ったかぶりがしたい性格みたいで、
「ちょっと待て。なんとなくわかる」
と言って、マジになって考えている。あーあ、こんな奴が自殺するはずないな。骨折り損のくたびれもうけだった。しかし僕が次にアーマダバードへ行くつもりだと言うと、ちょうどアーマダバードで仕立てたパジャーマーを受け取りに行くので、一緒に行こうとこのメキシコが言い出した。じゃあ一緒に行こうとまた約束したのだが、その後ウダイプルを去る時までこの約束もすっかり忘れていて、またもやメキシコをすっぽかしてしまったのだが、ウダイプルを出てからふとそのことを思い出した時は、
「あ、忘れてた。でもまあいっか」
と、もうすっぽかしたことも気にならなくなっていた。
そのあとホテルに戻ると、無駄骨折りの自殺者探しだったのだが、ねぎらいとしてCに晩めしを奢ってやることにした。奢ってもらえると聞いたらこいつ、食うわ食うわ、次から次へとボーイに料理を注文した。痩せてるくせに、こんなにどこに入るんだろうと呆れるほど食った。食ったと言うより食い散らかしていたと言った方が正しい。全ての皿を食い残したまま途中で下げさせ、また次を注文する。
とことんケチなくせして、他人の懐から出るとなればとことん贅沢をしようとする。遠慮なんか全くない。ありがたいともちっとも思ってはいないようだ。人をもてなすのに別の人の懐を当てにし、その見返りは全部自分で独り占めしてしまう。他人も友人も親戚も、こいつにとっては利用するためだけに存在している。人はみんな自分のために生まれてきたと思って少しも疑いを持っていないようだ。こいつは詐欺師と言うよりたかり屋だ。
奢ってやったら益々図に乗り、僕の部屋まで入って来た。ベッドに寝転がり、さっきまで一人でさんざん猥談をして喜んでいたかと思うと、そのうち寝てしまった。憎めない奴なのだが、鬱陶しいったらありゃしない。僕はこいつのことを『寄生虫』と名付けることにした。
僕の部屋にはなぜかもう一人居候がいる。このホテルの飼い犬のシェリーだ。僕が初めて来た時には吠え立ててたくせに、もう初日から僕の部屋を犬小屋にしてしまった。しかしこの犬は入口の所でおとなしく寝ているだけだし、食べ物をねだることも決してない。それどころか、ゴミが床に落ちたらすぐさま拾って外へ持ってってくれる。邪魔なだけのどこかの人間型寄生虫とは大違いである。
ただ僕は暇つぶしに、たまに野球ボールを部屋の壁に当てて一人キャッチボールをしていたのだが、ボールを取り損なって床に落とした時まで、親切にもすぐさまボールをくわえて捨てに行ってくれるのには閉口した。忠犬シェリーよ、どうせなら『おじゃまむC』をくわえてゴミ溜めに捨ててきてくれないか。
4月12日 晴 ウダイプル
インドに来て一月近くになるが、これまで一日たりとも一人でのんびりできた覚えがない。この湖の町ウダイプルでは保養をしようと考えていたのだが、ここでもインド人はなかなかそうはさせてくれない。デリーのような人の多い都会では、人間が結構淡泊で、ほっといてはくれるのだが、保養できるような所ではないし、両方の条件を満たしている所はこのインドではなかなか見つからない。
もうすぐ三角形の一辺、北インド横断が成り、旅の行程の三分の一が終わろうとしているのだが、まだまだ魑魅魍魎どもが足元から這い上がって来るような難行苦行の旅が続きそうだ。だが楽な旅というのはあまり記憶には残らないものであって、話のネタになるようなことも起こらないのだから、とそう考えてみると、腹を立てながら続けている旅の方があとから自分の利益になるに違いない。ま、今はそういうことにしておこう。
Cもやっぱり金欲しさで僕に、と言うより外国人観光客につきまとっているのだった。最初からどうせそんなことだろうとは予想していたものの、少しがっかりした。友達を作りにインドに来たわけではないのだが、なんでこんなに詐欺師やたかり屋ばかりが僕に寄り集まって来るのだろうか? 『類は友を呼ぶ』と言うが、そうするとこの僕はその手の人間だと言うことなのか。
そんなことはない。確かに日本では類が友を呼んでいるのはよく目にすることだが、インドにおいてはこのことわざは当てはまりそうもないな。これはインターナショナルなことわざではなかろう。インドにおいては、『善者は悪者を呼ぶ』これがいい、これにしとこう。
今日湖畔で夕涼みしてる時、やっぱり『おじゃまむC』はつきまとって来たのだが、次はアーマダバードへ行くと言うと、ついて行くと言う。それどころか、その次の目的地、アジャンタ、エローラまでついて来ると言い出したもんだから、
「金かかるぞ。金あんの?」
と言ってやった。自分で勝手についてくことにしといて、只で連れてってもらえると勝手に決めている。食い物を奢ってやると、これでもか、これでもか、と食道から直腸まで詰めに詰め込もうと貪り食う。テーブルの上に煙草の箱を置いておくと、勝手にどんどん吸って空にしてしまう。自分が吸い尽くしといて、煙草が切れたみたいだから買ってきてやるよと、金をせびる。人の部屋に入り込んで来て勝手に泊まる。僕の持ち物を欲しがる。あんた、きっと長生きするよ。
この日、タイガー湖という所へ行ったのだが、この時日本語を教えてくれと頼むので、そういう殊勝なところもあるのか、やっぱり学生なんだな、と思っていたが、教えてくれとCが言った言葉が何かと言うと、「こんにちは」「みずうみ」「きれい」「やすい」、あとは数字だった。もうそれでいいと言う。何なんだと思っていると、翌朝早く出て行って、ホテルに戻って来ると有頂天になって言うのだ。
「早速日本語で日本人客を捕まえてきたぞ、ひひひひひ」
「あー?」
「コンニチワ、ミズウミ、キレイ、ホテル、ヤスイ、ハチジュウルピー」
その日本語の単語を並べて狩ってきた日本人が隣の部屋に泊まったと言うのだ。こいつにとってはありとあらゆる全てのものが、己れの金儲けのためにしか存在していない。まあ、こういう頭の造りをしている奴は日本にもいるから特に珍しくもないのだが、こういう奴は嫌いだから、もう相手にしないことにした。
あとはどうやって縁を切るかだ。最初からビジネス丸出しで寄って来た奴は簡単なのだが、こういう中途半端な奴とある程度知り合いになってからスッパリ切るというのは、日本人にはなかなか難しいものだ。
おじゃまむCは今夜も僕の部屋でベッドに寝転がり、またもや好みの猥談をしながら、にやけた顔して一人で受けている。
「明日チットールの恋人のとこに行くから、一緒に行こう」
と、やたらにしつこい。行きたきゃ一人で勝手に行けばいいだろ。勝手はあんたの得意技じゃなかったのかい。
「なんでおまえのデートに俺がついてかなきゃなんないんだよ。一人で行け」
「19ルピーあればバスに乗れるし、チットールの女は20ルピーで買えるんだぞ、えへへへへ。外国人なら40ルピー出せばOK、うしししし」
なんだ、よく自分の恋人の話をするけど、売春婦のことだったのかよ。しかしこの時いいアイデアが浮かんだ。その手を使っておじゃまむCの呪縛から逃れよう。蜂がたかって来たら、持っている甘い物を遠くに投げてやれば蜂はそっちへ飛んで行く。その隙にこっちはスタコラサッサと逃げればいいのだ。相手が人間だろうと同じことだ。「あの時そんなこともあったなあ」と、あとは思い出にしてしまえばいい。人をすっぽかすのは僕の得意技なんだし。
4月13日 晴 ウダイプル
朝、Cに100ルピー渡し、チットールの女のとこで二泊してこいと言って上手く追っ払うことに成功した。Cは金をつかむと喜び勇んで出て行った。今日はのんびりできそうだ。
朝の散歩、サンセット・ポイントへ。ここよりもっと南へ足を伸ばすと静かでいい場所がある。景色も綺麗だが、ほとんど人は来ない。牛と水牛と山羊ばかりだ。昼の散歩、サヘリヨン・キ・バディ(侍女たちの庭園)へ。侍女らしき人は一人もいなかった。入場料を払って入って来た見物客ばかり。夕方の散歩、ピチョラー湖西岸へ。
暑いので、その間毎回ばててホテルに戻り、休憩しては出直す。やはり『リグ・ヴェーダ』は読んでもさっぱりわからないのですぐにやめてしまい、最近はもっぱら暇つぶしには壁当ての一人キャッチボールだ。この部屋でエラーをすると、名球拾いがいるので真剣になってくる。それでもたまに落球すると、それまで寝そべっていた名球拾いが素早く起き上がってボールをくわえ、ササーッと部屋の外へ持ってってしまう。
「こらこら、シェリー! ボール返せ!」
エラーすると罰として、僕までベッドから起き上がってシェリーを追っかけなければならない。これは自業自得なのだが、その度にフロントにいるボーイまで一緒になって追っかけることになり、さぞかし迷惑だったろう。まあ、暇だったみたいで、喜んで追っかけてたみたいだったから、僕も遠慮することなく壁当てをやめようとはしなかった。
夕方ピチョラー湖の西岸に行った時は、向こう岸から湖を挟んで宮殿の写真を撮ろうと思いついた。ところがここは空き地を防壁みたいな塀で囲んであって、それを乗り越えたり、破れ目を見つけたり、なかなか進むのに苦労する。その石の塀が何重にもなっているし、例のまきびしのようなどでかい三角の棘がいっぱい落ちてて、少し進むと棘がゴム草履にいっぱい突き刺さり、痛くて歩けないのでしばらく棘を抜く作業に手間取らされる。塀を乗り越えたり、棘を抜いたりの繰り返しで、なかなか進まない。
うんざりして水辺に座り込んでいると、向こうから角が泳いで来た。角だと思ってたら、顔が現れ、体が現れ、やがて大きな水牛たちが一列になって僕の目の前に上陸して来た。塀もいばらも何のその、水牛たちの行く手を阻むことはできなかったようだ。しかし僕は水牛ではないので、こんな汚い湖を泳いで渡る気にはなれず、またもやあくせくと塀を乗り越え、いばらの棘を抜き、そんなことを何度も繰り返し、ようやく宮殿が正面に見える場所まで辿り着いた。
さあ、あとは水際まで行って写真でも撮ろうか、と腰を下ろし、ゴム草履の裏から棘を抜きながら一休みしていると、「なんでこんな所にいるの?」と言いたくなるような人もいない辺鄙な場所に、警官が二人、突如ニュッと姿を現した。ここの警官も水牛も、ビックリ・ショーがお好きみたいだ。
僕のそばまで近づいて来て、
「おまえが逮捕した」
と片方の警官がいきなり言った。
「あ?」
あとはなんだかんだ言ったが、インドの言葉なのでさっぱりわからない。それから僕の持ち物を調べようとする。持ち物と言っても、カメラと文庫本と煙草とライターしか持って来ていない。そのカメラをやたらにいじくり回す。マトゥラーでは手癖の悪い警官にあわやカメラを盗まれかけた経験があるから、こいつらもそうか、と疑ってみたが、どうやらそうではないみたいだ。警官がみんな泥棒だったらたまったものではない。
宮殿の方を指差したり、カメラを指差したりしてなんだかんだ言ってる。ここから宮殿は撮影禁止だと言いたいのだろう。写真を撮ってるのを警察に見つかるとフィルムを抜き取られる国とかよくあるみたいだから、何となくそう思い、
「わかった、わかった。まだ一枚も撮ってないよ」
と言ってやり過ごそうとしてみたけど、向こうもこっちの言うことがわからないみたいだ。身振り手振りでいろいろ説明も試みてみたが、石頭みたいで、ちっとも理解しようとしない。こっちは撮影禁止だと察したのだが、それがわかったんだということをこの二人の警官にちっともわからせることができない。
意志疎通が全くできないというのは非常に疲れるものだ。手を変えようと思ったわけではないが、僕は煙草を一本抜いてくわえると、「あんたたちもやるか」と警官に箱を差し出した。途端に二人ともニヤッとして、それぞれ煙草を抜き取り火を点けた。急に警官の態度が軟化した。警官の買収なんてた易いものだなあ。しかし煙草一本ずつで上等だ。おまえらに金なんかビタ一文くれてやるものか。
「サヘリヨン・キ・バディで撮っただけだ。サヘリヨン・キ・バディ、サヘリヨン・キ・バディ!」
その地名は通じたみたいで、フィルムを取り替えたばかりだったので、枚数表示が四枚にしかなっていなくて、そこを指差してまたもや、
「サヘリヨン・キ・バディ! サヘリヨン・キ・バディ!」
と強調してみせると、どうやらこの石頭どもにもやっと呑み込めてきたのか、今度はカメラを持って僕に向けた。そこを押すんだと言って、もちろん言ったって通じないが、シャッターを指差してると、いきなり押した。あとで現像した時には、僕の首なしのパノラマ写真ができあがっていたものだ。
そこで表示が五になったので、どうやら警官は納得して僕にカメラを返した。なんとか僕の無実が証明できたみたいだ。だけど馬鹿だなあ、前の四枚はここで撮ったかもしれないじゃないか。まあ、そんなことは言うまい。しかしなんでここから宮殿を撮っちゃいけないんだ? どこから撮ったって同じじゃないか。
「あるいは――」
と僕は考えた。この何重にも張り巡らされた無駄な塀と言い、一面にばらまかれたいばらの棘のまきびしと言い、このエリア自体に何か秘密が隠されているのではなかろうか。いばらをどけると秘密の入口が現れ、そこから地下へと下りて行くと、核爆弾が製造されているのかもしれない。
しかしそのことをここで探る気はない。そんなモノを発見したところで、一文の得にもならないからな。核兵器を密売するルートなんて僕は知らないし、そもそも僕のリュックでは小さすぎて核爆弾は収まりきらないだろう。スパイだと間違われたら一大事だ。僕はへらへら笑いながら石頭警官たちにバイバイした。歩いているとまたもやいばらの棘がズブズブとゴム草履を突き抜けてきて、痛くてたまらなかったが、痛さに飛び跳ねながらも、僕はスタコラサッサとこのいばら地獄から逃げ出した。
ここまで来れば大丈夫だろうと、宮殿が正面にはならないのだが、増水でもしたら湖の底に水没してしまうだろうというくらい水辺ぎりぎりの場所にホテルがあったので、そこでまたカメラを取り出して湖と宮殿を写そうとしていたら、またもや邪魔者がしゃしゃり出て来た。その水没ホテルのおやじと娘らしい。泊まれ泊まれとやけにうるさい。明日ウダイプルを出るんだと言っているのに、じゃあ明日、今泊まってるとこチェックアウトしてからうちに泊まりに来なよ、と無茶なことを言う。ここは話の通じない奴らばかりで困る。じゃあまた、と言って水没オヤジからも逃げ出した。結局『宮殿と湖』の写真は撮れなかった。
町の中心部に戻って来ると、着飾った女の人たちがパレードしていた。女のお祭なんだ、と見物していた子供が教えてくれた。土産物屋を覗いていて、あちこちの絵はがきがあったので適当に何枚か買った。ジャイサルメールの砂漠の絵はがきを見ていると、行きたくなってしまった。
日が暮れてから、橋の上で湖の写真を撮った。宮殿は写せなかったが、宮殿の代わりに、湖に浮かんでいるホテル、もちろん水の上にプカプカ浮いて漂っているわけではないけれど、レイク・パレス・ホテルという超豪華ホテルで、ここに灯が燈ってなんとも綺麗だったので、これを写真に撮った。
エリザベス女王もこのホテルにはたまげたとガイドブックには書いてあるけれど、部屋の写真を見てみると、王宮もまっつぁおという感じで、確かに凄まじいホテルには違いないのだろう。僕なんかには縁もゆかりもない場所だ。
やっぱりインドは安宿が一番。だいたいこの湖に浮かぶホテルの綺麗な景色は中にいる客には見えないし、どうせ眠ってしまえば部屋の中の飾りなんか見ないんだし、たまたまこういう超高級ホテルに泊まった夜に、野宿している夢でも見てしまったら大損だ。おまけにここだってちょっと増水したら水没ホテルと化すに違いない。そしたら土左衛門になって二度と超豪華ルームの装飾を目にすることもできないじゃないか、と、泊まれないから負け惜しみを言ってみる。
明日は売春ツアーから戻って来る『おじゃまむC』にまた捕まるとまずいので、早めに逃げ出そう。しかしこのウダイプルでは逃げてばっかりいるなあ。『逃げるが勝ち』――これはきっとインドのことわざなんだろう。
4月14日 晴 ウダイプル 〜 アーマダバード
ホテルをチェックアウトする時、請求額が思った以上に多かった。おじゃまむCが遠慮なくガツガツと食いまくったからなあ。「遠慮せず食え」なんて僕は一言も言わなかったのに。くそーぅ……、これでは宿泊費を負けてもらった意味がない。ルピーがたちまち予想外の欠乏だ。
オーナーが両替できるよと言ったので、飛びつくことにしたが、闇両替のようで、T/Cはできないらしい。わずかに米ドル紙幣も持っていたので、それを替えてもらうことにした。ところが行きの空港でわざわざ細かい10ドル札にして持って来たというのに、100ドル札がいい、細かい札だと率が悪いのだとオーナーが言う。どうも解せない。
ぶらぶらとバススタンドまで行くと、十四時三十分にエクスプレス・バスが出るとのこと。ちょうどいい時間だ。久しぶりに昼のバスに乗ったが、景色がいい。泊まりをケチって夜行バスや夜行列車に乗るということを何度かしたが、よくよく考えてみると、その方が損だとだんだん思えてくるようになった。
インドは二十一世紀になると中国を抜いて人口が世界一になるそうだが、人口が偏りすぎている。都市には人がぎゅうぎゅう詰めになっているが、都市と都市との間はがらんとしていてだだっ広い無人の平原がどこまでも広がっている。インド人は何にしても極端を好む民族のようだ。
そもそもが僕はファンタジー・ワールドを肌身で味わおうと、いわゆる取材旅行を第一の目的として来たのだから、こういう人もろくにいなさそうなだだっ広い平原を二本足で歩いてみるべきなのだろうが、人がいないとかなり不便な目に遭いそうで怖い気もする。RPG並みに荒野やジャングルでコブラや虎や謎のモンスターに襲われ、闘ってみるべきなのだろうが、そんな恐ろしいことはできそうもない。だからバスの窓から景色を眺めて想像をかき立てるだけに留めておこうではないか。
夕方うとうとしていると、バスが突然ジャンプして、いっぺんに目が醒めた。アスファルトの舗装道なのだが、何のつもりなのか、所々にわざわざ突起をこしらえてある道が少なからずあって、そういう道になると、定期的にバスが何度も宙に浮くので、慣れていないと口から内蔵が飛び出しそうになる。慣れてしまっても眠っていると、その度に起こされる。やっぱり夜は、地面にくっついてじっとしているホテルで寝るに越したことはないだろう。
とにかくインドのバスは飛ばす飛ばす、時速200kmはいってないとは思うが、直線はメチャメチャだ。この日の運転手はマトゥラー〜デリー間の時の運転手に勝るとも劣らない飛ばし屋だった。クラクションをひっきりなしに鳴らしながら反対車線に出ては、前を行く車をどんどん追い越して行く。対向車が来ててもちっとも気にせずクラクションを押しっぱなしのまま真っ正面から突撃して行く。こんなチキンレース狂の運転手に出くわしたのが運の尽きなのだろうか。おお、神よ! 我を守りたまえ……。
「うわっ、死ぬうぅぅぅ!!!!」
「あーー、死んだあぁぁぁぁっ!!!」
「もうダメだおしまいだ終わりだ…………」
何度叫びそうになったことか。やっぱりバスの中では寝てる方がいいのだろうか? しかし寝たら寝たで、たまにバスが空を飛ぶ時、離着陸の衝撃で一々起こされる。インドに暴走族がいない理由がまたしてもわかった。暴走族にならずに、バスの運転手になっていたのだ。
あんたが衝突死するのは勝手だが、客が乗ってんだぞ、こらっ! 人権侵害で運転手を訴えてやりたいくらいだ。よくもインドのバスで一度も死なずに生きていられたものだ。これなら荒野でキングコブラと死闘を演じていた方がましだったかもしれない。
このあともやむを得ぬ理由から移動はバスばかりだったが、何度も同じ目に遭わされたものだ。あの時の、インド恐怖バス旅行を終えたばかりの僕の肉体と精神を持ってすれば、スペースシャトルなんぞ朝飯前で逆立ちしながらでも乗れただろうし、頼まれればスタントマンだって空中ブランコだって、目隠ししたままでも平気でやってのけたに違いない。
とにかく死ぬことがあまり怖くなくなった。「一度は死んだ身だ」なんて台詞があるけれど、そうすると、僕なんかインドのバスでもう五千回は死んでるからな。それとも死に対する悟りが開けたのかもしれない。インドで悟りを開くとはこういうことだったのか、なるほど。
ウダイプル〜アーマダバード間、64ルピーはお薦め。夜行のデラックス・バスより速いし安いし、時々空も飛べてスリル満点、ジェットコースターに何時間も乗れると思えばいい。おまけに悟りまで開けてお得です。ちんたら走って高いだけのリクシャーに乗るのが馬鹿々々しくなる。
更にはのちのことだが、別の路線にはホラー・バスというのもあって、運悪くそれに乗ってしまった。夜行バスで、これも夜間飛行をするのだが、着陸した時に顔の前にいきなり鉄棒が飛び出して来る。眠っていてうっかり串刺しにされるところを、すんでのところで目を覚まして難を免れたのだが、ジェットコースター+お化け屋敷といったところか。
インドの長距離バスは途中で休憩がある。恐らく恐怖で縮み上がった心臓をほぐすために設けられているのだろう。食事時はこの休憩時間がそれなりに長い。長いか短いかは、そんなことどこだろうと教えてくれるとこはないので、他の客の様子を窺いながら、自分で見当をつけなければならない。それで乗客たちがぞろぞろとどこかへ歩いて行くようだったら、ちょろちょろとあとからついて行くといい。
そうするとレストランみたいな所に何人か入って行ったので、僕も入って行って注文した。注文したと言っても、ターリーしか置いてないみたいだ。まあ定食屋みたいな店だろう。おまけにそこは純インド大衆食堂だったようだ。インド人の習慣では、手でつかんで物を食べる。米でも手づかみだ。それでも外国人観光客が行くような場所にあるレストランでは、必ずと言っていいくらいスプーンを付けて料理を出してくれるものだが、ここには珍しくスプーンも置いてなかった。
こういう店でも洗面所くらいあるから、食べる前には必ず手を洗うべきだ。幼稚園の先生みたいなことを言うようだが、『食べる前には必ず手を洗う』これがインドでは金言だ。ちょうどおじさんが洗面所でゲロゲロ吐いていたので、この時僕はそこで手を洗う気になれなくて、そのまま手づかみでターリーを食ったのだが、これがいけなかったのかもしれない。これが原因だと特定はできないが、のちに僕はひどい目に遭うことになるのだ。
ゆっくり食事して戻ってみても、まだバスは発車しない。おまけに荷物を次から次へと屋根の上に積み始めた。若い人夫が窓をもっと開けろと言ってるみたいだったので、開けてやると、窓枠に裸足の足を載せ、でかい荷物を屋根にどんどん積み上げ、ロープで縛りつけてしまった。乗客輸送だけでなく、このバスは貨物運搬までやっているみたいだ。こんなバスの屋根に荷物なんか積んでるけど、いいのかなぁ。途中でみんな転げ落ちてしまうぞ、きっと。
途中の大きな街でバスはまた停車すると、乗客は全員降りてしまった。休憩だと思ってそのまま座っていたが、ウダイプルとアーマダバードの間にこんな大きな町があったのかなんて思ってると、終点のアーマダバードだ、と車掌が僕に言った。それならそうと早く言ってくれよ。僕は自分の荷物をつかんで急いでバスから降りた。
もう恐怖バス旅行のために身も心もへとへとになってたので、お決まりの『招かれざるお出迎え』のリクシャー・ワーラーに適当なホテルへ連れてってもらうことにした。着いたホテルはシングルルーム100ルピーで値段こそまあまあだったが、ここは英語が全く通じない。ホテルの正面から入って来たんだから、泊まりに来たのに決まってるのに、部屋を取るのに非常に手間取った。
おまけに部屋に入ってみると、水道の蛇口から水が出ない。虫が出て来ないだけまだましだが、ひねってもひねっても何も出て来ない。アーマダバードは滅茶苦茶に暑い。これまで行った所では一番暑い。シャワーを浴びて冷やそうとしてみたが、シャワーも出なかった。フロントまで文句を言いに行ったが、これがまたてんで通じなくて、文句を言っているのだとわからせることさえできない。
それでも何とかボーイを部屋まで引っ張って来て、水道の蛇口をひねって実演して見せた。ああ、水が出ないね、って感じで、そのまま行ったっきり戻って来ない。そのままいつまで経ってもボーイは戻らない。諦めて寝ることにした。眠って暑さを忘れよう。
冬至の日に風邪をひいて洟水を垂らしながらペンギンを抱いてフルちんで白クマにまたがり南極点の氷山を冬山登山して木枯らしと吹雪に遭い凍死しかかって垂らした洟水が樹氷になりかけながらも最後の食料であるかち割り氷を頬張ったので虫歯に凍みて冷や汗をかいているという涼やかな夢でも見るとするか。
うううううっ、眠れないぃーっ!
体じゅう汗の大洪水だ。こんな熱帯サウナの中で眠れって言うのか、えっ! 見渡してみると、この狭い部屋はまるで独房ではないか。廊下に面して小窓が一つあるだけで、そこに鉄格子がはまっている。天井についた大きな扇風機(インドの扇風機はこれが普通だ)が熱風をかき混ぜている。これじゃ映画で見た『アルカトラズからの脱出』よりひどい。ホテルと刑務所を間違えて入って来てしまったのではなかろうか、などという妄想が浮かんできたりもした。もしかするとフロントで払った100ルピーが罰金で、そのあとこの独房に閉じ込められたのかもしれない。
このホテルはイカれてる! インドは狂ってる! 世の中は不条理に満ち満ちているっ!
冷房付きの部屋というのはインドでは値段がかなり高くなる。ひどい所だと、冷房が付いているというただそれだけのことで料金が倍になる所もある。この一月近くの間、ずっと冷房なしの部屋で踏んばってきたが、今日はさすがにめげそうだ。今日だけ「竹の中」にしとこうかな。
いやいやここで挫折して初志を貫徹しなかったら、冒険者失格であろう。いばら地獄、恐怖バス地獄、灼熱地獄、何するものぞ!
でもやっぱり暑いものは暑いぃー! ううー死ぬぅー……。
 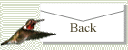
|