|
5.くたばれ詐欺師ども! J・マフィアの逆襲
4月5日 曇のち晴 デリー
昨日つれなくしたのは悪かったかなと思い、隣の部屋の花街さん母娘に声をかけ、一緒に朝めしを食べに行った。このお母さんはよく喋った。今夜日本に帰るそうだが、その前に土産を買って、残り時間でデリー観光すると言う。そして店から出際に、
「それじゃあ、ラール・キラーで会えたら会いましょう」
と言った。
「僕はこれから行くから会うはずないでしょう」
と答えると、それがなぜか会うものなんだと花街の母はしたり顔で力説した。 窓の外に赤ん坊を抱いた小さな女の子がいて、そっちを見ると頻りに口に手を持って行く。ドアを開けて残り物をやったら、お礼をして去って行った。食べ残しを恵んでやるとは、何とも言えない後味の悪いものだった。
コンノート・プレイスの先の方で高級な土産物を買うべく、花街さん母娘はニューデリー駅前のリクシャー乗り場でプリペイド・チケットを買った。それを持ってリクシャーに乗りに行ったが、案の定、誰も乗せてくれようとしない。プリペイドは客がリクシャーやタクシーにボられないようにするために作ってあるそうなのだが、実際のところ、役に立っていないばかりか、買うと二重取りされたり、ちゃんと目的地まで行ってくれなかったりで、却って損をすることになる場合がほとんどだろう。
その辺にリクシャーはたくさん停まっているのだが、みんな相手にしない。そんな安い値段ではとても乗せられんよとでも言いたげに、一発拒否だ。女だからなめられてるのかもしれないと、僕も手伝ってリクシャーに掛け合ってみたが、なかなかうんと言う奴がいない。やっとのことで行ってやるぞというリクシャーを捕まえたので、花街さん母娘を呼んで乗せた。そこでバイバイして、リクシャーは走り去った。そのまま目的地へ行ったものとばかり思っていたのだが……。
のちにある人から教わった話によると、プリペイド・チケットには番号があり、乗るリクシャーが指定されてあるのだそうだ。指定されたリクシャー以外に乗ると、チケットが無駄になってしまうのだ。
僕はホテルに引き返してカメラを取って来ると、リクシャーを捕まえて、
「ラール・キラーへやってくれ」と言った。
「50ルピー」
「高すぎるぞ。30に負けろ」
「30だったらラホール門までだな」
「ん?」
と、僕は地図を確かめてみた。ラホール門はラール・キラーの入口ではないか。この20の格差は何なのだ? と不思議に思ったが、まあ30ならいいだろうと、それで行かせることにした。
デリーの渋滞はひどい。動いたかと思うとまた停まるの繰り返しだ。車道は車が走る所という決まりがないようで、サイクル・リクシャーだろうが牛車だろうが、何でもごちゃ混ぜになって走っている(停まっている?)。おまけにみんな我先に前へ出ようとする。野良牛が道の真ん中までやって来てどっかと座り込む。これなら歩いた方が早いくらいだ。
デリーのリクシャー料金が高いのは、この渋滞も一因だろう。ワーラーは時間の浪費とガソリンの消費で運賃を割り出す。しかし身勝手な話だ。乗客の側にしてみれば、遅いから余計に金を払うということになってしまうではないか。おまけに排気ガスをたくさん吸わされて鼻の穴の中が真っ黒けになる。インドの街中にいると、とにかく鼻の穴が真っ黒けになるのだ。
少し走ってから、
「もう歩いた方が早いぞ」
とリクシャー・ワーラーのおやじが言った。
「あそこを右手にもう少し行った所だ」
と指差す。また渋滞して動かなくなっているので、それもそうだと30ルピー払ってリクシャーから降りた。ずっと歩いて行ったが、ラール・キラーらしき建物が見当たらない。別名デリー城だから、でかい城のはずなのだが……。
近くの人に訊いてみると、「あっちだよ」と、確かに向かっている先を指差す。んー、なんで見えないんだろう? 向こうにはそんなに高い建物はないのに……、もしかして、デリー城とは平屋建ての城なのか?
更に歩いて行ってまた訊いてみたが、「あっちだ」とまだ先を指差された。一体どうなってんだ? もしかして、ここはもうラール・キラーの内部なのか? うーむ、わからん……。ちなみに、「ここはなんてとこだ?」と訊いてみると、
「チャンドニー・チョウクだ」
『チャンドニー・チョウク』……、聞いたことがあるような名前だ……。そこで僕はガイドブックを開けて地図を見てみた。ふむふむ、チャンドニー・チョウク……、あったぞ。道の名前じゃないか。デリー城へとまっすぐ続く、オールド・デリーのメインストリートか。今はこの通りのどこにいるんだろう、と地図を見ていて、「おや?」と思った。
確かにこのまま東向きに行くと、ラール・キラーがあり、入口のラホール門に出くわすはずだ。だがしかし、逆向きに辿って行っても、『Lahori
Gate』と書いてあった。何じゃこりゃ? ラホーリ・ゲート? ははあ……。途端に全ての疑問が解けた。つまり、『ラホール門』ではなくて、ずっと西にある『ラホーリ門』で降ろされたというわけだ。まさに難事件解決の糸口をつかんだ名探偵の心境だ。
「やったあ!」何を! 冗談じゃねえよ! この地図だと、ラホーリ門からラホール門まで2キロメートルはあるじゃねーか! まぎらわしい名前つけやがってぇっ! いや、『Lahori
Gate』はそのまま『ラホール(パキスタンのインド国境の町)の門』という意味だろう。じゃあ同じ名前じゃないか。クソッ! やられた、うううう……。あのおっさんがラホール門なら30だと値下げした訳が今わかった。20ルピーの格差はこの2キロメートルもあるチャンドニー・チョウクの差だったのか。チキショーめ!
もっと地図をよく見てみると、今リクシャーに乗って来た距離はこの2キロメートルと同じくらいの距離だ。渋滞してたから時間はやけにかかったが、半分乗って半分歩きかよ、これなら乗らなきゃ良かったぜ。
もう1キロメートルくらいは歩いたに違いない。こうなったらこのまま歩いて行ってやろうと、ぶらぶら行ったが、道端でいろいろ変な物を売っていて、飽きずに歩いて行けた。
そのまま行くと道が分かれていて、どっちへ行けばいいのかわからなくなった。ちょうどその角に交番があった。ここの警官もカメラを取り上げようとするだろうか? と考えながらも、
「ラール・キラーはどっち?」
と尋ねてみると、若い警官が出て来て、
「この道を○○メートルほど行ってから、こっちに曲がって……」
と親切に一生懸命教えてくれた。どこかの不届きエロ警官とは大違いだ。
という訳で、ラール・キラーにようやく着いたのだが、何のことはない、でかいだけで、味も素っ気もないつまらない所だ。やれやれ、苦労して来たかいがなかったというものだ。せいぜい中にある博物館の展示品がちょっと面白かった程度だ。
それでサーッと歩いて、サーッと出たが、帰り途にジャマー・マスジットという大きなモスクがあるので、ついでにそこへ寄ってくことにした。しかしもうそろそろ僕も観光に飽きてきたようだ。
このモスクでは、カメラ持ち込み料10ルピー、靴預け料10ルピー取られた。ムカついたのは、裸足で入らなければならないので、入口で金を払って履き物を預けるわけだが、順番を待って並んでいると、あとから来た西洋人観光客を、入口の番人たちが優先して入れようとするのだ。
別にこの西洋人たちが図々しいわけではなくて、後ろに並ぼうとしてるのをわざわざ西洋人に限ってこの卑屈な番人どもが前に回すのだ。外国人観光客にサービスしているのでもなく、単に白人を優先しているだけなのだ。
カッカしながら歩いていると、小さな石ころが足の裏に当たって痛い。益々腹が立ってきた。でかい堂の中に入ってみると、なんにもない。壁しかない。要するにモスクとは、イスラム教徒たちが壁に向かってひれ伏して拝む建物というだけだ。ここで拝んでいるところは写真に撮ってはいけないということだった。
「何言ってやがんだ! ここを写さなきゃ他にどこ写せってんだ! カメラ料まで取っときながら、この詐欺寺め!」
と益々ムカついてきて、イスラム教徒の祈りをバシバシと撮りまくった。そのうちフィルムの無駄遣いをしていると気がついたから途中でやめて、外の景色ばかり撮った。
西洋人観光客が多かったが、こいつらはみんながみんな、イスラム寺院など見物しようとはしないで、向こうに見える巨大なラール・キラーの外観だけ眺めて喜んでいるようだった。そもそも異教徒の寺院になど興味はなく、ただ、城が見渡せる高い場所を求めて入って来ただけなのかもしれない。そういうところが西洋人は観光上手だなあと感心し、元を取ることだけ考えて余計な写真を撮ってしまった自分を反省した。そこでとりあえず西洋人たちに並び、ラール・キラーを写真に撮った。旅はやっぱり楽しまねば……。
さあ、あとは街を見物して帰ろうか、と寺院の反対側辺りまでやって来たちょうどその時、少し先にサイクル・リクシャーが停まった。見覚えのある日本人女性二人が降りて来た。こんな人の多い場所で、偶然にしては偶然すぎる。
「だからまた会うもんだって言ったでしょう」
花街ママが得意気にのたまわった。まさか僕を尾行してたんじゃないだろうなぁ。お土産用の紅茶をたくさん紙袋に入れて持っている。
「ああ、お土産買えて良かったスねぇ」
「そうじゃないのよ」
と花街ママは怒りだした。てんで違う場所で降ろされたと言うのだ。
「デリーのリクシャー・ワーラーはクズばかりですねえ」
と相槌を打つと、母娘揃って堰を切ったようにリクシャー・ワーラーの悪口をまくし立て始めた。もの凄い早口だ。僕にリクシャー・ワーラーの苦情を言われたって……、僕はインド首相じゃないんだし……。
「これから観光ですか」
僕は話を逸らそうとしてそう言った。
「僕の方は今日の見物はもう終わりましたよ」
「もう時間ないから、一つだけ見ようと思って。ラール・キラー行こうかなあ」
「ラール・キラーはもう少し先だし、中は広いから時間かかりますよ。今から見るならここくらいでしょう」
と僕は階段の上のジャマー・マスジットの門を指差してみせた。
「そうでしょう。だからこのモスク見ようかと思って」
と花街の母は同じく階段の上のジャマー・マスジットの門を指差した。
「ああ、ここはねえ、何もありませんよ。入るだけ金と時間の無駄。見るんだったらラール・キラーの中の博物館くらいしかないですねえ」
無責任なことを適当に言うと、僕は花街母娘と別れ、街を見物しながらぶらぶらと歩いてホテルに戻った。
晩めしも花街母娘と一緒に食べたが、ドタバタと帰り支度をしてホテルをチェックアウトしたあと、レストランでは余裕をカマしている様子だった。帰りの便の時間は聞いていたので、
「そろそろじゃないですか」
と心配してみても、
「まだまだ大丈夫」
とマダム花街は余裕しゃくしゃくでいる。
「あー、もう早く日本に帰りたいって思ってたけど、今となってはもっとインドにいたいわぁ」
好き勝手なこと言ってたが、突如花街マドモワゼルの方が、
「電話するの忘れた」
と慌てて国際電話をかけに行った。戻って来ると、
「並んでるし、つながらないし」
とやきもきしている。すると今度はマダム花街の方が忘れ物したと急に言い出してドタバタと慌てだし、
「あんたのせいよ!」
と母娘で醜い罵り合いになった。やがてそれはいつの間にかホテルのせいになっていた。
結局取りに帰る暇もなくなり、「まあいいや」ということになったのだが、別れ際に僕に餞別をくれた。それが何かと言うと、使い終わって黒焦げになった蚊取り線香入れだった。
「腰からぶら下げたまま歩けるし、いいわよ、これ〜♪」
とマダム花街はその素晴らしい廃品をもったいつけて僕にくれたのだった。
「じゃあ遠慮なく頂いときます」
二人が帰ってからホテルの部屋に戻ると、僕は花街の母の遺品をゴミ箱に捨てた。こんなモノは乞食にやったってもらってはくれないだろう。それにしてもあの二人はちゃんと帰りの飛行機に間に合ったのだろうか? まあ、仮に乗りそびれてたとしても、「もっとインドにいたいわぁ〜♪」とおっしゃるマダムのご希望が叶うわけだし、どちらにしたってめでたしめでたしでいいじゃないか。
それにしても着いた時はデリーは面白そうだと思ったが、もう飽きてしまった。ろくな見所はないし、物売りは淡泊で張り合いがないし、ここは便利なだけだ。こんなとこ、『魔のトライアングル』の名に値しない。この僕が称号を剥奪してやる。おまけに、ああ、『リグ・ヴェーダ』は今夜もやはり一文も解読することができない……。
4月6日 晴 デリー
朝は一人でコンノート・プレイスという所へ行ってみたが、何もないただの公園でつまらない。芝生に腰を下ろして休憩していると、変な奴らが寄って来た。そいつらが耳掃除をする、マッサージをする、サンダルの裏貼りをすると、勝手に仕事を始めた。ガキまでやって来て、「コーラ買って来てやるよ」とお節介を焼く。まるでしけた王様の気分だ。知らん顔してさせておいたが、あとで耳かき屋が、
「料金500ルピー」
とぬかしやがった。
「ふざけんな」
と一蹴しようとすると、
「じゃあこれを見てみろ」
と手帳を取り出して僕に見せた。見なくていいのに、見てみると、『この耳かきはとても気持ちよくて、600ルピー出す値打ちはあります』とか、『この耳かきのおじさんは正直で親切な人です。600ルピーなら安いと思いました』とか、同じような日本語が何ページにもわたって書いてある。理不尽なべた誉め文句ばかりなので怪しいとは思ったものの、筆跡も注意して見てみたが、どれも別人の手になるもののようだ。
「コンノート・プレイス辺りに来る日本人とは、底なしの馬鹿どもばかりか」
と呟くや、
「こんな日本人は俺は知らん」
と言ってやると、
「金払え、金払え」
とうるさい。そこで、
「50ルピーやろう」
と折れてみたのだが、
「そんなの話にならん。500ルピーだ!」
とわめき立てる。
「知らんなあ」
としらばっくれていたが、
「薬を使ったから、その薬が高いんだ」
などといろいろ筋の通らない屁理屈をつけてくる。僕はあくまで50ルピーにしようと、ポケットの中を探ってみたが、あいにくと50ルピー札が一枚もなかった。小銭以外はみんな100ルピー札ばかりだ。
「しょうがない。負けたよ。特別に100ルピー払ってやろう」
ともったいつけながら、100ルピー札を一枚取り出すと、ゴミでも捨てるように芝生の上に放り投げてやった。こういう態度を取られても何とも感じない卑しい奴らどもだ。もっとも、インドでは物を放り投げるという行為は別に粗野な行為だとは見なされないようだ。
昔、エア・インディアに乗った時、サリーを着たスチュワーデスに搭乗券を渡し、座席まで案内してもらったことがある。インド人スチュワーデスは笑顔で、座席までは丁重に案内してくれた。ところがフィニッシュが悪かった。
「ここです」と言うや、僕の座席の上に搭乗券をポイッと放り投げ、そのままスタスタと行ってしまったのだ。まあ、実際にバカにされていたのかもしれないのだが。
耳かき屋が真っ先に100ルピー札をつかみ取った。ところがマッサージ屋と裏貼り屋が金払えとわめき立てる。
「全員で100だ。勝手に分けろ」
と言ってやると、
「俺たち全然関係ない。今日会ったばかりだ」
と口々にわめき立てた。煩わしくなってきたので、必殺技を使おうと思ったが、『俺はジャパニーズ・ライターだ。おまえの悪口ガイドブックに書き立ててやるぞ』という殺し文句は、こういうごろつきには通用しないし、何度も使って飽きてしまっていたから、今度は、
「俺を知ってるか? 俺は実はジャパニーズ・マフィアだ。俺を怒らせない方が身のためだぞ」
と、新キャッチフレーズを作り、怖い顔をして凄んでみせた。それを聞くと、途端にこの蠅どもはぶんぶん唸るのをやめてしんとなった。耳かきのおっさん、ニヤッとして僕の肩を叩くと、そのまま100ルピー持ってどっかへ行った。マッサージ師とコーラのガキがあとからついて行って、「金分けろ」と言い争いしているようだったが、裏貼り屋の若者だけが立ち去らずにいる。こいつにはちっとも応えていないみたいだ。
実際、あとから考えてみれば、まともに金払えるような労働をしたのはこのサンダルの裏貼り職人だけで、あのごろつきどもとも関係なかったのかもしれない。こいつにはマフィアもへったくれもない。代金あるのみだ。僕のサンダルを手に取ってみせ、
「裏貼りしたから50ルピーくれ」
と暗い顔して言う。僕もその時はもう頭に来てたもんだから、
「こんなモノ貼ってくれなんて誰も頼んでないぞ。耳かき屋に金もらえよ」
と言ったが、全く聞かない。暗い顔のまま、
「50ルピー払ってくれ」
としつこい。
「こんなモノいるか!」
と僕は怒鳴って、サンダルの裏貼りを剥がしてやると、すぐにまた貼りやがる。剥がすともう一方のサンダルに貼ってしまう。それはもう名人芸の域に達していると言ってもいいほどだ。しばらく二人でイタチごっこを繰り返し、やっとのことで二つとも剥がすと、サンダルを手につかみ、急いでその場から立ち去った。
昼めしを食ってから、インド門の方にでも行ってみようか、とぶらぶら歩いて行くと、方角を間違えてしまったようで、天文台に着いてしまった。天文台と言ってもどうってことはない。児童遊園みたいなとこだ。
そこに見るからにイカつい日本人が三人いたので、逃げ出すことも適わず、恐る恐る声をかけてみた。そのうちの二人は信濃山兄弟といって、プロレスのタッグコンビみたいな今時の日本では珍しいくらい逞しい体格の持ち主だった。二人一緒に秤に乗ったら、300kgはありそうだ。見るからに、『動かざること山の如し』である。それで、群がって来る物乞いやインド人詐欺師どもをどうやって追っ払うかという話で盛り上がった。
「グラサンかけて肩で風切って歩いてたらみんなビビッて道開けた」
と信濃山兄弟が自慢げに言うので、
「あんたたちを見たら、日本でだって誰でも避けて通るよ。グラサンなんかかけなくたって、あんたたちならレスラーパンツ一丁で充分だろ」
と誉めてあげたのに、すると、僕のことを怪しいインド人だろうと言ってやり返してきた。
「俺のどこがインド人なんだ? どう見たって純日本人だろが。日本語ペラペラ喋ってるし」
と反論すると、
「いや、インドに帰化した怪しい日本人だろう。そういうのの方がもっとタチ悪いって聞いてるからなあ」
とひどいことを言いやがる。もう一人の葡萄クンまで僕のことを警戒し始めた。おい、いい加減にしろよ。この葡萄クンはまだ来たばかりで、インドのことがよくわからないらしい。何でもうんうんと真に受けてる。それでホテルを捜しているところだったのだが、信濃山兄弟は今夜帰るので、そこがいいからそこに泊まれと薦めていた。値段を訊いてみると、800と言っている。葡萄クンが躊躇っているので、
「そんな高いとこ泊まる馬鹿がいるもんか。泊まるとしたら、インドを怖がってる腰抜けくらいだろう。なあ、信濃山兄弟、俺のとこなんか140だぞ。メインバザールの方へ行けば安いとこあるよ」
と僕が言うと、「おおっ!」と葡萄クンはどうやらケチんぼみたいで、心を動かされたようだったが、信濃山兄弟が、
「あ、やっぱり怪しいインド人だあ。変なとこ連れてかれるぞー」
と兄弟揃って囃し立てた。くそー、800ルピーの部屋に泊まってるくせに物乞いを恐れる臆病者相撲取り兄弟め。
そこで信濃山兄弟とバイバイして、早速葡萄クンをメインバザールまで拉致して行こうと引き返すと、コンノート・プレイスまで来た時、
「よ、ジャパニーズ・マフィア!」
と声をかけてくる者がいた。見ると、午前中のマッサージ野郎だ。
「ジャパニーズ・マフィア! ジャパニーズ・マフィア!」
とニヤニヤしながら何度も聞こえよがしの大声で呼ばわる。葡萄クンがリュック背負ったバックパッカーのなりそのものだったので、一目瞭然でばれてしまったみたいだ。
「ジャパニーズ・マフィアはな、道案内したり、いろいろと親切なこともするんだ」
とあしらおうとしたが、この野郎、大人げない、コンノート・プレイスの外れまでずっとついて来て、後ろから「ジャパニーズ・マフィア! ジャパニーズ・マフィア!」と囃し立て続けた。
メインバザールでホテルを見つけ、葡萄クンはそこに泊まることにし、フロントで宿帳を書く段になってから、
「え、何それ?」
と連発している。葡萄クンは片言の英語もできないらしい。それで代わりに手続きしてやってから、二人で街をぶらついた。この葡萄クン、長期休暇を会社から取らせてもらって来てるそうだが、全く行き当たりばったりの人みたいだ。
デリーからインドに入ったそうだが、着いていきなり怪しげな旅行代理店に捕捉され、飛行機に乗せられ、ジャンムー・カシミール州のシュリナガルへ連れて行かれた。
カシミールとは、知ってる人は知ってるだろうし、知らない人は知らないと思うけれど、インド、パキスタン、中国の三国が自分の領土にしてしまえとしのぎを削っている三国志みたいな地域だ。その後、インドとパキスタンが一触即発状態となり、いや、もう政府軍同士の小競り合いがあったみたいだが、この時点でもとうの昔にやばい状況になっていて、カシミールを独立させようとか、イスラム教国のパキスタンに付こうとかいったゲリラが市街地で銃をぶっ放してインド政府軍と交戦したり、無差別爆弾テロをやったりで戒厳令が布かれるなど、危険極まりない所らしい。
シュリナガルには『ハウスボート』という面白い家があって、インド・ファンには人気のある場所だ。しかしこの頃では普通、インドへ行く人は下調べの段階で、『シュリナガルへは行ってはいけない』ということを知るのだが、この葡萄クンは知らぬが仏である。高い金ぶったくられて飛行機に乗ってから、どんないいとこだろうとガイドブックで『シュリナガル』の項目を読んでいると、だんだん冷や汗が出てきたそうだ。現実はガイドブックでは知ることができないくらい緊張したものだったそうで、動けば200メートルおきに検問に遭い、持ち物を片っ端から検められたそうだ。
だが幸いにも葡萄クンは銃弾に貫かれることもなく、爆弾で吹き飛ばされることもなく、生きてデリーに戻って来た。そういうものなのかもしれない。ここでホッとしたところで怪しい帰化日本人に騙され、身ぐるみ剥がれて土左衛門になり、ヤムナー河を流されて行ったというのなら、さぞかしドラマチックな展開なのだが、あいにくと僕は親切な純日本人なので、そういうドラマチックな展開は望めそうにもない。
しかし僕も葡萄クンのことを笑っていたものの、ちょうどこのデリーにいた頃、デリーでも一般のバスがこの系統のイスラムゲリラによって爆破されたのだった。そのことはのちになって知ったのだが、『知らぬが仏』はお互い様だろう。
晩になったので、この脳天気葡萄クンとめしを食おうと歩き回り、結局はホテルのすぐ近くにあるレストランに入った。前のテーブルで日本人と思しき女性二人が食べていたので、日本語で声をかけると、日本語で答えてきた。
「こっちで一緒に食べましょう」
と誘うと、
「こっちに来てよ」
と言われたが、
「そっち狭いから」
と屁理屈つけて、(皿を持って動くのが面倒なだけだった)こちらに呼んだ。他のテーブルはみんな西洋人だ。食事しながら楽しそうに笑っている。どうもこういう時は英語でげらげら笑えるほど英語力がないのが寂しくなる。そこでこういう場所では日本語で喋って笑いたくなるものだ。
英語を母国語とする英米人、オーストラリア人などは、日本人と見ると、その英語の下手さに合わせてゆっくり丁寧に喋ってくれようとするのだが、それが却ってつまらない。こっちはペラペラ喋りたいのである。
それで結局日本人が固まる。つまり日本人のテーブルか、欧米人のテーブルかに分かれる。たまに鼻の下伸ばした白人のあんちゃんが日本人の女の子を口説いているテーブルもある。このテーブルは面白くて、男の方は意志疎通させようと必死になり、英語をいろいろと他の英語の言い回しで言い換えているから、聴いていると英語の勉強になるかもしれない(正しい英語は期待できない。あくまで、英語でどう口説くかの勉強)。
しかし僕は語学留学に来たわけではないのだから、四人の日本人でペラペラと日本語を大声で喋った。この一人はちょっとおばさんっぽいが、香港在住の美人の主婦で、旦那をほったらかしにして半年インドで遊ぶそうだ。もう一人は子供っぽく見えるが意外に歳がいってる人で、フリーターだからやめて来たそうで、貯めた金が尽きるまでインドで遊ぶことにしているそうだ。実にあっぱれな二人の日本人女性ではある。最近はあらゆる分野において、日本人男性は日本人女性に押されまくってると思うのだが、どうであろう?
インドを旅行していると、変わった日本人に出会う確率が非常に高く、僕などは標準レベルに格下げされてしまうのだが、もしかすると、そういうレールから脱線してしまった人というのは目立たないだけで、日本にも結構いるのかもしれない。日本国内ではもう本来の自分を発揮できないと見切りをつけ、海外へ出てパァーッとやろうという気持ちはわからないでもない。
レストランを出ると、
「アヌープ・ホテルの屋上にあるカフェは素敵よ」
と逆に誘われ(ドキドキ!)、行ってみると、風がびゅーびゅー吹き抜けて、夜の見晴らし(?)と言うのだろうか、眺めが気持ちよかった。ここでも周りは全て英語テーブルだったので、四人でまた日本語をペラペラと喋った。
この二人、インドに来てまだ三日目だそうだが、やはり葡萄クンと同じように、インドに来ていきなりニューデリー駅前の旅行店に捕らえられ、半日軟禁状態にされるや、やがて出てきたチャーイを飲むと急に眠くなってきたので、死に物狂いで脱出したということだった。ニューデリー駅前に並んでいる旅行代理店は悪評が高く、デリーから初めてインド入りした人は、メインバザールの入口に当たるここでたいてい捕まってしまう鬼門らしい。
アーグラー城前での免疫のためか、僕にとってはもうこんな奴らは全く相手にはならず、ふぬけ詐欺師以外の何者でもなかったが。『政府』と看板に書いてあるのは全くの嘘で、この辺りでは
"government" という英語は『詐欺師』とか、『怪しげな』という意味で用いられているようだ。
話は戻るが、この成り行き任せ葡萄クン、また行き当たりばったりに、この香港主婦の方に一目惚れしてしまったらしいのだ。
4月7日 晴 デリー 〜
朝は葡萄クンと日本人の溜まり場というゴールデン・カフェでうだうだと過ごした。午過ぎにそろそろ両替をしておこうと、コンノート・プレイスの近くで両替屋を捜し、それからまたぶらぶらしていると、地図を見ながらうろうろしている日本人らしき人を見かけたので、親切にもからかってみたくなり、声をかけてみると、観光局を捜しているのだと言う。
この犬皮クン、インド舞踊を見て目醒め、プロの舞踊家を目指してインドに渡り、マドラスの舞踊家に弟子入りして一ヶ月になるという。今は師匠の舞台がデリーであるのでついて来て、二日間だけ自由時間がもらえたので、観光しているところだそうだ。インドに来る目的は人それぞれだ。ゴールデン・カフェならたぶんわかるということだったので、夕方そこで待ち合わせることにした。
近くにインドでは珍しい『○○ドナル○』があったので、葡萄と二人でそこに入った。日本にいる時はハンバーガーなんか食べたいと思うことはないのに、インドの極端な味にげんなりしていた僕は、この時、味気ないハンバーガーが無性に食べたくなったのだ。
しかしインドではこういう西洋式のファースト・フード店の方が客に対して口うるさい。客はたくさんいたが、金持ちそうな奴らばかりだ。実際、何の変哲もないただのハンバーガーなのに、インドの物価からすると高すぎる値段だった。それに、僕が椅子の上に片膝立ててると、(もちろんサンダルは脱いでいたのに)すぐに警備員がやって来て文句を言われた。おかしな国だ。
それからホテルへ引き返すと、僕は今日デリーを発つのでチェックアウトしたが、葡萄クンは頻りに僕の泊まっていたシングルルームを羨ましがった。そこでホテルの人に言って、僕のあとがまとして即葡萄クンが入ることにしてもらい、荷物はそのまま部屋に置かせてもらった。しかし葡萄クン、またもやさっぱり手続きができなくて、横で一々通訳していると、ボーイが呆れて、
「英語できないのか?」
と訊いた。それも通訳してやると、葡萄クンはボーイに向かって、
「イエス、イエス、ノー、イングリッシュ。ベリー、ベリー、ノー」
とか言ったので、ボーイたちみんなが笑った。葡萄クンもこれは通じたと思って笑顔になったが、できないということだけは相手にはわかってもらえたのだから、結果として通じたということになるだろう。
夕方になると待ち合わせ場所のゴールデン・カフェへ一人で行った。ネパールから出稼ぎに来ているボーイのD(僕たちは「愛ちゃん」と呼んだ)をからかって時間を潰した。やはり日本人の溜まり場というだけあって、日本人の客が多かったが、何と言うか、見るからに『インドに染まりきってしまった』という雰囲気の人ばかりで、喋っていることは他愛もないことばかりだったが、ちょっと話しかけるのは躊躇われた。
やはり一番ゾッとする奴は誰かと言うと、信濃山プロレス兄弟が言っていたように、『インドの怪しい日本人』だろう。この頃になると、もうかなりの数の日本人ツーリストに出会ってきたが、同じ日本人のせいか、日本人なら一見しただけで二種類に分類できるようになっていた。『前向き』か『後ろ向き』か、『チャレンジ』か『エスケープ』かの二種類で、日本にいてはいつまで経っても見分けなんかつかないのに、インドにいる日本人は不思議と一目瞭然なのだ。インドとは人間が剥き出しになる国なのであろうか。例外として、僕みたいな無機的な日本人ツーリストもたまにはいるが。まあ、人にはそれぞれのインドがあるようだ。
そう言えば、インドにやって来た日本人の反応も二種類に分かれると聞いたことがある。「こんな国、二度と来るもんか!」と大嫌いになる人と、逆にインドに魅入られ、取り憑かれてしまう人があるそうだ。
この国にいる間にそういう噂のいくつかも耳にしたことがあるが、その取り憑かれ方がどんなものかと言うと、ちょっと一週間ほど旅行会社のツアーで来たつもりが、図らずもインドの虜となり、仕事も捨て、妻子も捨て、財産も捨て、日本に残してきたもの全てと縁を切り、パスポートも捨てて当てもなくインドを彷徨う。
なぜパスポートまで捨てるかと言うと、強制退去させられないようにだ。つまり自分が何者なのかという証拠を隠滅してしまうのである(と、これは『まえがき』でも述べたことの繰り返しだけど)。それで村から村へと渡り歩いていると、何とかそのままやってけるらしい。面白半分でできることではないだろう。
そこまでしなくても、ビザ切れになるのを交わすため、パキスタンやバングラデッシュ、ネパールなど、周辺の国を往ったり来たりする。そうやってビザが切れる度に取り直して居続けようとするそうだ。で、何をしているかと言うと、ただ放浪しているだけらしい。それが『魅入られて』しまったということなのだそうだ。インドの目的は人それぞれだ。
そうしていると、日本人の若者が一人やって来て、目が合った。
「座っていいですか?」
ときたので、
「どうぞどうぞ」
この人は目が死んだ魚ではない方のタイプだったので助かった。今回でインド三度目の弓外クン、無職だそうだが、旅行する時はスポンサーがついて資金を出してくれる、言わば『プロの旅行家』だ。今回はマドラスから入り、バンガロール、ゴアに長いこといたあと、ゴアからデリーまで四十時間列車に乗り続け、今日着いたところだそうだ。インドには人それぞれのインドがある。
しばらくすると葡萄、犬皮と順にやって来た。愛ちゃんが近づいて来て、耳元で、
「ビールにする?」
と言った。なんでこの国ではビールの注文取る時は耳元で小声で囁くんだろう? どうせビールをどーんと持って来て、テーブルに置いて飲むんだから、耳元で囁く意味がないではないか。
「旦那、お上ご禁制の秘密のナニがありやすぜ、いっひっひぃ」みたいな言い方するなっつうの。こっちまで悪いことしてるみたいな気分になってくるじゃないか。
犬皮クンは指をくにゃくにゃ折り曲げたりして、インド舞踊の技を頻りに見せびらかすと、マドラス郊外にある道場の住所をメモして、「良かったら見に来てくれ」とさりげなく、それでもかなりしつこく何度も繰り返し頼んでいたが、結局マドラスへ行った頃にはすっかり忘れてて、行かなかった。
旅行家弓外クンが、
「今回はブッダカヤーに長くいようと思うんですが」
と言ったので、
「あんなとこ一日いたら飽きてしまうよ」
とまたもや人がこれから行く所をけなしてあげた。
「それともネパールへ行ってみたいとも思うんですが、ガイドブック捜してるんだけど、どこにもなくて……」
没になったが、僕は元々ネパールへも行くつもりでガイドブックも持って来てたから、
「俺持ってるよ。もういらないからあげるよ」
と言うと、イブン・バトゥータ・弓外急に晴れやかな顔になり、
「訊いてみるもんですねえ」
いらなくなったガイドブックと引き替えに、旅行家からビールを奢ってもらうことになった。
ホテルまで取りに来てもらい、ネパールのガイドブックを渡すと、もう出発の時間になっていた。正確にはそろそろ出発しようかとしていただけ。
それで葡萄クンの部屋から荷物を取って来ると、ホテルの前の路地で三人で記念撮影してお別れしたのだが、葡萄クンは昨日は僕についてジャイプルへ行くと言ってたのに、今朝になって気が変わり、あの香港妻を追っかけて東へ行くことにしたそうだ。「恋の力は偉大なるかな……!」
やれやれ、あの時の思い詰めた表情を思い出すと、その後どうなったのか気になる。消息は今もって知らないが、心配だ。と言うのは嘘で、まあ好きにやってくれ。インドの目的は人それぞれなのだし。
サイクル・リクシャーを捕まえ、
「長距離バス・スタンドへ行ってくれ」
と言って地図を見せると、
「ジャイプル行きなら、もっと近くにあるよ」
と、地図にはない近い方のバス・スタンドへ行ってくれた。しかしここも結構大きいバス・ターミナルで、どこへ行けばいいのか見当もつかない。すると、ここはインドだ、困った時にはすぐに救いの手(ほんとかよ?)が差し伸べられる。僕の目の前に、スウーッとアラジンの魔法のランプみたいにインド人が出現した。10ルピーで切符売場と目的のバスまで連れてくと言う。10ルピー要求するところは、アラジンの魔法のランプと違い、いかにもインドの普通の物乞いだなあ。
「じゃあ、連れてけ、アラジンよ。但し、ローカルバスだぞ」
「オーケー、オーケー、ローカルバス!」
そうして連れて行かれた切符売場で並んだが、表示がヒンドゥ語みたいなので、ちっとも読めない。アラジンを疑っているわけではなかったのだが、一応前に並んでいるおじさんに、
「ジャイプル行きはこの窓口でいいんですか?」
と尋ねてみると、おじさんは、
「僕もジャイプル行きに乗るから、買ってあげよう」
と切符を買ってくれた。しかしその窓口はローカル・バスではなくて、デラックス・バスの切符売場だった。ちょっとだけ高いが、列車より安いんだし、これでいいだろう。これも天命と思って諦めよう。まあ、結果としてはこれで良かったのだ。ローカル・バスに乗っていたら、僕はテロリストに爆破されていたかもしれないのだから。
前のおじさんの方が信用できそうだと思った僕は、こっちに寝返ろうと思い、インドのアラジンに10ルピー札渡して即刻クビにした。
十一時過ぎになってバスは出発したが、この巨漢のおじさんは親切にもいろいろと僕の面倒を見てくれた。荷物のことから始まって、スナック菓子まで奢ってくれた。新しいアラジンに寝返って良かったなあ。
スーツ姿で、見るからにそう見えるが、バンガロール(南インドの都市。インドのシリコン・バレーと呼ばれるくらいハイテク産業が盛んらしい)のビジネスマンだそうで、仕事でこれからジョードプル(ジャイプルより先にある、砂漠の町)へ行くそうだ。
「ジョードプルのお城は見なきゃね」
「うん。ジャイプルの次に行くつもり」
しかしまたもや綿密な計画が崩れ、ジョードプル(あとでここへ行った日本人から聞いたが、この城はほんとにいいらしい。インド一の城だとか)を初めとするラジャスターン州の砂漠の町々は諦めることになってしまうのだが(非常に残念)。
「どっかいいとこは?」
と訊くと、おじさん、
「ゴアの海は綺麗だよ」
と言う。弓外クンもゴアの海は綺麗だと言ってた。
「あとディーウもいいねえ」
「ふうーん」
「行ったことないけど」
「なーんだ」
僕はインドで目にする最初の海にこだわっていた。西へ向けて抜けるのだから、当然それはアラビア海になるのだが、問題は初めて見るアラビア海をどこにするかだ。日本にはないスケールの長い陸地を何日もかけてあくせくと横断し、初めて海に出た時は、「おー! 海だあ! 地の果てだー!」と、そこには日本では味わえない感動があるに違いない。これは海と陸とでは逆になるが、コロンブスが大西洋の果てで陸地に出会った時の感動と通じるものがあるのではなかろうか。
まあ、こっちはあると最初からわかっているから、そこまで感動はしないだろうが、しかし実際、今デリーからジャイプルに向かっているところだと聞かされても、地図上はここだと頭では理解できるのだが、一体自分が今地球上のどこにいるのかちっとも実感できないというのが正直な実感だ。その切れ目に行ってこそ初めて、自分がいたとこが大陸だったんだと実感できるとでも言うか……。
「で、他にはいいとこない?」
とおじさんにまた訊いてみたが、新アラジン、ありゃまあいつの間に、もう「グー・スカ・ピー」と、大音量のいびきを鳴らして眠りこけているのだった。
4月8日 晴 〜 ジャイプル
「わっ!」
いきなり巨漢がのしかかって来て、僕は襲われるのかと顔を引きつらせたが、そうではなかった。バンガロールのビジネスマンのおじさんが、「ジャイプルに着いたよー」と起こしてくれたのだった。僕はまだ寝ぼけた頭のままバスから降り、係員にトランクから荷物を引き出してもらった。こいつがまた要領が悪く、「荷物が見つからない」などと言うと、すぐに諦めようとした。するとビジネスマンのおじさんは、「見つかるまで捜せ!」と係員を叱咤してくれたので、不真面目な係員は渋々ながらもようやく奥の方から僕の荷物を引きずり出した。
おじさんはタラップの所にずっといて、バスが出るまで別れを惜しんでくれた。やがてバスは暗闇の中へと走り去って行った。僕はしばらくバスに向かって手を振っていた。親切ないい人だったなあ。あのバンガロールのビジネスマンこそ、魔法のランプから出て来た魔神かもしれない。
「さらば、アラジンよ!」
空を見上げると真っ暗だった。時計を見てみるとまだ四時だ。バス・ステーションといった雰囲気の場所ではない。後ろを見ると、ベンチにしては高くて広すぎる何かの長い屋根付きの台があり、オレンジ色のライトがいくつも点いていて、台の上を明るく照らしている。台の上には乞食たちが、魚の干物みたいにずらりと並んで寝ていた。
しかしここにも例外なく、リクシャー・ワーラーと客引きどもが待ち受けていた、こんな時間だというのに……。バスから降りた客は僕一人だ。客引きどもは待ってましたとばかりに、
「わわわわわわわぁー!」
と僕に群がり寄って来た。口々に何かわめき立てているが、僕が外国人なのは一目瞭然なので、少し英語が話せる奴は、唾を飛ばしながら英語でわめきまくった。僕は寝起きが悪いもんで、「あん?」とろくに返事もせず、乞食を干している台の上に上がって腰掛けた。急いで考えるにはまだ時間が早すぎる。
客引きたちは「うちに来い」と口々に言ってせかそうとするが、僕は言葉がわからないふりをして、ミネラルウォーターを飲み、煙草に火を点け、おもむろにリュックから虎の巻を取り出して開いた。ジャイプルに早く着くことは、おじさんから聞いて知っていたので、さてさてどうしたものかと考え始めた。
そうして眉間に皺を寄せたままじいーっと地図を睨んでいると、ワーラーたちは案の定、焦れ始めた。こいつらは必ずと言っていいくらい人間がせっかちにできている。一種の職業病なのかもしれない。開いたガイドブックの地図に赤線が引いてあるのを見つけると、
「ここへ行きたいのか。30ルピーだ」
と勝手に話を作り上げていく。
「じゃあ、ここはどっち?」
と初めて僕はまともに口をきいた。地図で観光ポイントを指差す。するとワーラーたちは、登校拒否の中学生が心を開き始めたのを喜ぶ熱血先生のように「わぁーっ!」と歓声を上げるや、「あっちだ、あっちだ」と力説しながら指差すではないか。
「んー、じゃあ、ここはどっち?」
「どれどれ――そこはあっちだ!」
こうやって迷子のふりして訊いているうちに、ここが地図上でどこなのか、だんだんと見当がついてきた。そうするともう僕にはこの熱血客引きたちが無用になってきた。彼らはまたもや「うちのホテルに来い」と争奪合戦をおっ始めだした。そうするとまた鬱陶しくなってきたので、僕はさも生活に疲れ果てて『どこか知らない土地へと旅してみたい』人生の敗残者よろしく、哀しげな眼を客引きたちに向けると、「はぁーー」と一つ長い溜息をつき、またそのまま黙り込んだ。
さすがのジャイプルのリクシャー・ワーラーたちも、ここまで反応の鈍い奴に疲れを覚えたのか、パラパラと次々に去って行き、そうするとあっと言う間に誰もいなくなってしまった。乞食たちも死んだように、寝返り一つ打つ奴もいない。静寂だけが残った。
僕は迷っていた。このバス停は地図には載っていないが、ここがシティ・パレス(マハラジャの住居)の近くだということまではわかった。このまま起きといて、夕方まで観光してからホテルを探そうというつもりでいたのだが、シティ・パレスが開くまで五時間近くある。乞食の干し台の上でずっと待つのは退屈だし、それになんとなくまだ眠くて、夕方までリュックを背負ったまま歩き回る気力が出て来そうにない。
そういう僕の気分を見透かしたわけではなかろうが、新たに一人のリクシャー・ワーラーが近づいて来て、
「二十四時間制のホテルはどうだ。200ルピーだよ」
と笑みを浮かべながら穏やかに声をかけてきた。もう僕のインドにおける決まり文句みたいになってしまったのだが、
「高い」
と一言言うと、
「150ルピーに負けよう。そこに泊まってくれたらリクシャー代も只にしとくよ」
一応地図を見せて場所も教えてもらったが、そういうことをしなくても、ゆっくり眠りたいという欲求が先程から頭をもたげてきているところだった。二十四時間制のホテルというのはインドには結構多い。たいてい何時にでもチェックインできるし(絶対とは言わない)、チェックインしてから二十四時間以内なら、いつチェックアウトしようが値段は同じだ。お得なのだが、これがもし二十五時間泊まってしまったとしたら、二泊分の金を取られるのが通常のルールになっている。交渉すればもっと上手に泊まれるとは思うが。
つまり、僕は葛藤の最中だったのだ。今から泊まると、ぐっすり眠れるが、明日夜明け前にホテルを出なければ二泊分金を取られて損する。ワーラーは焦ることなく、ニコニコ顔で僕の決断を待っている。さっきのワーラーたちより上手みたいだ。
「んーむ……」
この時の僕には、ここであと五時間も待ってられる根性がなかった。結局リクシャー・ワーラーにホテルまで連れてってもらい、部屋に入るとそのまま爆睡してしまった。
目が醒めると午だった。ジャイプルは暑い。たぶんこの暑さで目が醒めたのだろう。部屋から出たとこがレストランで(インドの安宿のレストランは安食堂なので便利だ)、そこで朝昼めしを食ってからジャイプル見物に出かけた。
しばらく歩いてオート・リクシャーを捕まえ、
「シティ・パレスまでやってくれ」
と言うと、「50ルピーだ」と、とんでもない値段をふっかけてきた。ムカついたので、またもや、
「ジャパニーズ・マフィアをなめんなよ」
とドスの利いた声で脅してやったが、そうするとそのワーラー、
「あ、そ、ジャパニーズ・マフィア、ジャパニーズ・マフィア――」
と言いながら足元からでかい石を拾い上げた。いい歳して何する気だ、と自分のことも棚に上げ、なんだこのヤローと突っかかっていくと、
「あはは、じょーだん、じょーだん」
とこの野郎、石を足元に捨てた。それでもちょっとだけ負けてくれただけだった。そもそも相場自体が高いのかもしれないが、デリーとこのジャイプルは、他の土地に比べてリクシャーの値段が高すぎると思う。
リクシャーから降りて、ちょっとムカッ腹を立てながらシティ・パレス入口の入場券売場へ行くと、入場料35ルピー、カメラ持ち込み料50ルピーと、ふざけた値段だ。カメラは持っていたが出さないで、入場券だけくれと言って100ルピー札出すと、この切符売りのマハラジャの家来、手元にサッと100ルピー札を引き寄せ、素早く入場券と10ルピー札一枚、5ルピー札一枚を返して寄越した。
「おい、50ルピー足りないぞ!」
怒鳴りつけてやった。するとマハラジャの手下、
「今もらったのはこれだ」
と、手元に前もって用意してあったのだろう50ルピー札をすかさず持ち上げてみせた。
「それじゃない。渡したのは100ルピーだ!」
こういう姑息な奴は怒鳴りつけるのが一番いい。案の定、素直に諦めて50ルピーをあっさりと返してきた。このクズ野郎め、とカッカしながら宮殿の中へと入って行ったが、あとで思い返してみると、僕の方は元々カメラ持ち込み料50ルピーをチョロまかしていたのだった。儲けたなあ、うししし。
期待通り、宮殿の中はつまらなかった。補修もままならないのか、壁が今にも崩れそうなままだ。しかし高いカメラ持ち込み料取っときながら(払ってないけど)、武器と細密画のコレクション(これだけはなかなか良かった)は撮影禁止で、写真に撮るようなものがない。こんなことだろうと予測して、カメラを隠し持って入ったのだ――と言い訳。
そこで、中庭でマハラジャの家来をモデルにして写真を撮った。この家来、親切にも僕と交代してカメラのシャッターまで押してくれたのだが、そうするとあとでしつこくチップを要求してきた。マハラジャの家来など腐り切ってる。王様の家来だなんて誇りはもうかけらも見受けられない。
それはそうなのだろう。『マハラジャのように』とか、豪勢な暮らしをしている者の喩えに使われたりするが、実際のマハラジャとは、かつてイギリスに降伏して王のままでいることを許された弱虫諸侯の成れの果てで、インドがイギリスから独立して以来、徴税権もインド政府に奪われ、今ではこのように宮殿を観光客に見せたり、宮殿の一部をホテルやレストランにしたりして、辛うじて食いつないでいるといった踏んだり蹴ったりの存在なのだそうだ。そのまま家来たちを養っていこうとすれば、当然台所は火の車だろうと同情したくなる。まあ、こんなクズ家来ばかりで、僕は同情する気も失せてしまったが。
シティ・パレスを出てぶらぶらしていると、リクシャーがあとからつけて来て、メーターで行ってやると言ってしつこい。そうだな……、丘の上にあるフォート(砦)に行ってみたいと思ってたから、雇うとするか。ワーラーは「ナハルガール・フォートがいいぞ」と勧めてきた。じゃあそこへ行ってくれ。
途中で一度休憩したあと、道が上りになってきた。ジャイプルの郊外の眺めはなかなか素敵だ。ここは砂漠の外れにある町で、池に白いイスラム風の宮殿が浮かんでいたりする。
ところが坂道の途中でリクシャーがエンコした。リクシャーというのは乗ってみればすぐわかるのだが、ほんとにボロくて馬力もさっぱりない。馬一頭より力がないと思う。スピードもあまり出ない。ちょっと大型のリクシャーもあり、ちょうどこの時でっかい西洋人六、七人で相乗りしてる(無茶な!)のを見かけたけど、やっぱり帰りに丘の頂上でエンコしていて、みんなでエンジンを押しがけしていた。エンジンなどかけずに、「坂道を転げ落ちながら帰った方が早いんじゃないの」と思ったりしたもんだ。
僕のリクシャーの方は頂上に辿り着く前に壊れた。ワーラーのおっさん、頻りに謝りながら修理を始めた。僕は「いいよ、いいよ」と言って道ばたに腰を下ろして待つことにした。カンカン照りで、汗がだらだら出てくる。僕は水をがぶがぶ飲んだ。おっさんはそんな僕に、「ダンネバート、ダンネバート」と何度も言った。『ありがとう』という意味だが、この「ありがとう」、滅多にインド人の口から出ることはないそうだ。僕もこのあと一度だけどこかで立ち聞きした覚えはあるが、インド一周中、なるほど耳にしたのはその二度だけだ。しかしこのワーラーのおっさんの『ダンネバート』は相手を油断させる策略の一つだったのかもしれない。
ようやくリクシャーも直り、丘の頂上に着いた頃には日が西に傾いていた。丘の頂にはさほど大きくもない砦が忘れ去られたように寂しく立っている。砦の先端へ行くと、灯りが点り始めたジャイプルの広い街が一望に見渡せた。眼下の崖下には小さな砂漠があり、ぽつんぽつんと点在する民家から人が出て来て歩いているのまではっきり見えた。
ポンコツリクシャーがエンコしたお蔭で、最高の時間帯に着いたようだ。街の向こうに夕日が沈もうとしている眺めが素晴らしくて、なんとも形容のしようがない。人もほとんどいないので、静かだし、このロケーションも貸し切り状態だ。
更に気に入ったことには、この砦自体がレストランになっていた。特に改造も何もしていなくて、テーブルと椅子が置かれてあるだけ、建物の一つを厨房にしているみたいだが、目立たないようにしてあり、外観を少しも損なっていない。中世そのままの城で食事している気分に浸れる。厨房がかなり離れているのでコーヒー一杯でも時間がかかったが、おじいさんのボーイがとことこと歩いて砦の先端のテラスまで持って来てくれるのんびりとした光景がまたいい。
市街地にはこれと言ったお薦めできる観光ポイントがないが、時間の関係でジャイプルの砦はここだけしか行けなかったけれど、ジャイプルはその周囲の丘の上にあるいくつかの砦へ行くことがお薦めだ。特にこういう夕方の時間帯に、できれば恋人と二人で来るとロマンチックな雰囲気に浸れることは請け合おう。ただ、バスで来ると交通費まで大いに浮かすことができるのだが、バスは早い時間になくなってしまうので、やはり丘の砦の黄昏時を味わうにはリクシャーを雇い、少々奮発しなければならない。
僕はもちろん写真家でもなければ、写真の趣味も持っていない。しかしたまたまカメラを持って来たというだけのことで、今回インドでは、それまでの人生で撮った写真の合計枚数を遙かに上回る枚数の写真を撮った。それだけインドで目にした光景が珍しく、そして素晴らしかったということだ。悲しいかな、腕前が腕前だけに、帰国してから現像してみると、おおーっと思ってシャッターを切ったはずの写真のほとんどは、迫力のないありきたりな画像に変わってしまっていて、僕が目にした感動をそのまま再現できていなかったが。
コーヒーのグラスを片手にジャイプルの黄昏の光景に見とれていると、斜め前のテラスにいつの間にか小さな子供が二人、やはり夕焼けを眺めているのに気づいた。「これはいい絵だ!」と感銘を受けた僕は、急いで子供と夕景色をカメラに収めた。インドで撮った数多くの写真の中では、これは数少ない「なかなかいい出来」の写真だと思うのだが。
あとでこの子たち二人の兄妹に、お礼のつもりで駄菓子をやろうと差し出すと、この小さな兄の方が首を横に振って頑としてモデル料を受け取ろうとしない。もっと小さな妹の方は少なからず気があるみたいで、手こそ出さないがお菓子から目が離せないでいる。妹のそういう気持ちを察してか、いや、同時に自分にも同じ気持ちがあるからこそなのだろうが、「もらうな」というようなことを言い、小さな兄はもっと小さな妹を制止していた。
正確な英語を流暢に喋るし、身なりからして金持ちのおぼっちゃまに違いなかろう。この後も度々あったが、子供と見ると、僕は小銭よりもお菓子をすぐやろうとする癖があって、そういうことを何度もやったが、汚ならしい恰好をしているガキは、ダボハゼのようにすぐに餌に飛びついてきたものだが、ちょっと身なりのいい子だなあと思える子は、必ずお菓子を知らないおじさんからもらうことに躊躇した。知らない人から物をもらうなと親から躾けられているのだろう。この時何となくわかったような気がした僕は、この小さなプライドを尊重して駄菓子をすぐに引っ込めると、二言三言言葉を交わしたあと、この誇り高き小さな兄妹とバイバイした。
暗くなってきたことだし、そろそろ戻ろうとリクシャーの所に引き返した。近くで西洋人の若者たちがワイワイ言いながら、楽しそうに大型リクシャーを押しがけしている。
「いつまでもやってろ」
僕の方のワーラーのおっさんが嘲笑った。しかしここからは僕とワーラーのおっさんとの戦いの幕が上がるのだった。
「ここからは貸し切りだ」
とおっさん、メーターを倒してさっさとリクシャーを走らせ始めた。まあ、勝手にしろ。リクシャー・ワーラーと喧嘩するのはもう僕の日課となりつつある。僕にとっては、本日もこれからナイト・ゲームの一戦が待っているというだけの話だ。
ホテルまで戻って来ると、予想していた通り、ワーラーのおっさんともめにもめた。もうその一部始終を書くのもめんどくさいくらいの呆れた闘いだった。料金表を取り出して見せたり、ホテルの前の道を往復してメーターの動き具合を見せたりと、おっさんはあらゆる手を使って300ルピーの料金を請求してきた。
「50ルピーだ!」
と僕も引かない。100と250ルピーまで互いが歩み寄ったところで試合が膠着状態になった。ホテルの前の道で三十分ほどバトルを繰り広げた挙げ句、試合は判定にもつれ込んだ。道行く人を捕まえ、こうこうこうだと訴えた。勤め帰りのサラリーマンはふむふむと聞いていたが、次にワーラーのおっさんが僕の理解できない言葉で審判員を泣き落としにかかった。途端にサラリーマン臨時審判員は鬼のような形相になり、
「おまえが悪い! ちゃんと320ルピー払え! いいか、320ルピーをちゃんとこのおっさんに払うんだぞ!」
僕に指を突きつけながら罵るようにわめき声を上げると、へぼ審判は去って行った。おっさんは「どうだ、俺の勝ちだろう」と言いたげな顔でニヤニヤしている。くそぅー! 一言も僕には理解できないが、おっさんがどう言ったかくらい想像はつく。
「この外国人、320ルピーでチャーターすると最初に約束しときながら、50ルピーしか払えんなんて今更言いやがるんだぜ、ちょっとあんたから何とか言ってやってくれないか」
こんなとこだろう。言葉がわからないことでこれほど苦しんだことは初めてだ。
この街で僕の味方と言えば、せいぜいホテルの従業員くらいなものだ。当てにはならないが、それでも僕は諦めず、
「じゃあ今度はホテルで聞いてみよう」
とおっさんを連れてホテルに入って行った。
まず僕がこうこうこうだと(倒す前のメーターの額なども、こうなることを予想してしっかり覚えていた)フロントにいた従業員に説明すると、次におっさんがまた僕の知らない言葉で自分の言い分をまくし立てた。さすがに僕がこのホテルの泊まり客なので、従業員はニコニコ顔で聞いていたが、
「乗ったのは何時だ?」
とニコニコ顔のまま僕に訊いてきた。
「二時半だ」
横でおっさんがまた何かまくし立てている。
「んー。それじゃやっぱり320ルピー払わないと。この人を六時間も雇ってたことになるからねえ」
従業員はニコニコ顔のままやんわりと僕に言った。なんで帰宅途中のサラリーマンやホテルの従業員といったにわか審判がそんなきっちりとしたリクシャーの料金まで暗記しているのだ? おっさんめ、今度は、
「320ルピー払うべきだとこいつに言ってくれ。それだけ言ってくれたらあんたに20ルピー分け前をやるからさぁ」
とでも言ったのだろう。むー、相手の策略にまんまとはまめられてしまっていることは百も承知なのだが、『カムカロウ(負けてくれ)』しか知らない僕にはどうすることもできない。アウェーでの戦いはほんとに厳しいなあ。まさにこういうのを四面楚歌と言うのだろう。悔しいが、今日は項羽の負け、劉邦の勝ち。日本の項羽は高額の戦後賠償金320ルピーをインドの劉邦に支払うと、そのまま階段を上がって自分の部屋に籠城してしまった。
しかし、簡単には諦めきれない。くやしー! 項羽なら虞美人が慰めてもくれようが、僕には本丸で一人荒れ狂うしかない。そうしてベッドに仰向けに寝転がって歯ぎしりしながら思い返しているうちに、自分の間抜けさ加減に気がついた。二時半から八時半まで雇ったから320ルピーになるんだとボーイは言ってたが、じっくり思い返してみると、二時半とはこのホテルを出た時刻で、それからシティ・パレスへ行き、出てからぶらぶらして、あのリクシャーに乗ったのは四時半頃だ。僕は自ら墓穴を掘っていた。
更には途中の坂道で一時間ほどリクシャーがエンコしていた。これは僕の責任ではないし、逆に迷惑料として料金を割り引いてもらう口実にもなったはずだ。そして戻って来てからホテルの前の通りで約三十分のバトル、これはもう雇っている時間には入らない。結局正味あのワーラーを雇っていた時間はわずか二時間半に過ぎない。三時間半も余分に審判に対して計上していたのだ、それも自ら――。
くっそーぅぅぅぅ! 冷静になってそういう計算ができると、その結果にまた僕はカッカッしてきた。ちょっと『魔のトライアングル』をなめすぎていたようだ。ジャイプルのリクシャー・ワーラーはほんとにしたたか者揃いだ。くそうー! 地獄の沙汰とそのサポーターの魑魅魍魎どもめ! 悔しいから明日ジャイプルを出ることにしよう。
4月9日 晴 ジャイプル 〜
ミニ・バスに乗って鉄道予約センターへ。それにしてもジャイプルのリクシャー・ワーラーはやっぱり最低だ。このミニ・バスはたったの2ルピーで市街地のたいていの所へ行ける。中はカルカッタの市バスみたいに混んでないし、行先を言っておくだけで、車掌だけでなく、他の乗客まで「もうすぐだよ」、「ほら、着いたよ」と親切に教えてくれる。車内の雰囲気も、善人しか乗っていないという感じだ。距離は数倍あったとはいえ、昨日の320ルピーは一体何だったんだ。百六十倍ではないか。リクシャーにさえ乗らなければ、ジャイプルはいいとこだ。
しかし鉄道予約センターでは、予想していたものの、その予想を上回る長蛇の列にまたもや嫌気が差し、結局バスにすることにした。僕のように忍耐力に欠ける人間では、インドの列車にはまず乗れないだろう。実際に、アーグラー以後は結局列車には一度も乗ることがなかった。何度か乗ろうと試みてはみたが。それに比べ、バス乗り場へ行くと予約はあっさり取れた。これだと列車の切符を買うなんて馬鹿々々しくなってくるのがわかるだろう。
次にハワ・マハル(風の宮殿)へ行ってみた。ここははっきり言ってつまらない。ジャイプルは『ピンク・シティ』と呼ばれているそうで、何やら艶めかしげな、怪しげな町のようにも聞こえるが、怪しげな奴こそいるものの、単に赤っぽい色をした建物が多いというだけのことだ(期待はずれ……)。このハワ・マハルはピンクの建物そのものだった。補修中らしく、木の足場に囲まれていたが、建物が通りにそのまま面しているし、ちょっと見たところ、ただのアパートにしか見えない。
『風の宮殿』などといかにもロマンチックそうな名前に惹かれて期待して行ってみると、がっかりするに違いない。なぜ『風の宮殿』なのかは入ってみればすぐにわかる。窓には扉もなく、ガラスなども入っていない。風がびゅーびゅー吹きっ晒し状態だ。ジャイプルは暑いからこういう建物がいいとは思うが、金を払ってまで見物するような所ではない。ガラスがみんな叩き割られてなくなってしまった、シンナー少年たちの溜まり場となっている空き家にでも行けば、日本でも『風の宮殿』を発見することができるだろう。
次にジャンタル・マンタル(天文台)へ行った。ここはデリーのそれよりは規模が大きかったものの、同じように児童遊園だった。昔は一応こういう訳のわからないでかいオブジェを用いて天体の位置をちゃんと把握していたのだから凄い。しかし僕がいる今は真昼だし、星の位置がいろいろ書いてあっても、そっちには星が見えない。それで何をしようかとなって、結局は高い所に登ってみたが、そうして辺りを見渡していて、僕みたいに高い所に登って喜んでいるのはガキンチョばかりだということがわかると、自分が情けなくなってきてさっさと下に降りた。しかしインド人たちはこんなつまらないとこにもたくさん押し寄せて来ている。一体何が面白いんだ。これなら屋根の上を走り回っている猿を見ていた方がよっぽど退屈しないでいられる。
そこでさっさと天文台からも出ると、道の向こう側に腰を下ろしていたじいさんが手招きした。何だ、と思って近づいて行こうとしたが、途端に僕は足を止めた。じいさんが笛を口にするや、前に置いてある籠からコブラがニュッと突き出て来たのだ。僕は手を横に振って、
「いや、やめとく」
と言った。じいさんは、いいから来い来いと、また笛を吹いた。コブラがするするーっと立ち上がった。
「蛇は嫌いだから」
と言い訳して、僕は急いで逃げ出した。
コブラは怖い生き物だが、蛇使いのコブラというのは、毒牙を抜き(たまに名人とか言って、意地を張って毒を抜かない蛇使いもいるらしいが)、子蛇の時から飼い慣らしていて、近くで見物しても危険はないということは知っていたのだが、何が危険かと言って、蛇の芸が済んだあと、途方もない見物料を蛇使いから要求されるということを聞いていたものだから、僕はそっちを恐れて逃げ出したのだった。『貧者蛇使いに近寄らず』、またもや新格言ができたではないか。
おまけに万が一のことがあってコブラに噛まれて死んだとしたら、『日本人観光客、インドでコブラに噛まれ死亡!』などというおどろおどろしい見出しで日本の新聞に載ると恥だからな。『触らぬコブラに祟りなし』その記事なども、たぶん面白おかしく、例えばこんなふうに書かれるかもしれない――『インドをうろついていた住所不定、無職(本人は作家であると主張していた形跡がある)伊井田褐太さん(年齢不詳、身元不明)は、昨日の午後(日本時間、だいたい夕方頃)、インド、ジャイプル市の天文台付近にて、インド人蛇使いの操るコブラ一号に喉首を噛まれ、近くの路上にて悶絶死した模様。蛇使いはそのまま姿をくらましたため、インド警察当局は殺人の疑いもあるとして、この蛇使いを全国指名手配した。なお、伊井田さんの遺体は引き取り手もないため、近くの路上でそのまま干からびて鴉の餌食となっているとのこと』
丘の上の砦の一つ、アンベール城へも行ってみたかったのだが、時間が気になってやめた。そこで早めに夕食をとり、二十時三十分発の夜行バスでウダイプルへと向かった。バスの運賃は150ルピーだった。何度も負け惜しみを言うみたいだが、昨日の320ルピーは何だったんだ……。
 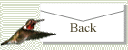
|