|
4.じゃあイクラ! 噂のトライアングルに魔の商人が
3月31日 晴 ジャンシー 〜 オーチャ
特にどこへ行くという予定もなかったので、とりあえず明日の銀孫クンが予約してあるのと同じ列車の切符を取ろうと、朝にジャンシー駅まで行った。目と鼻の先にある(インドの距離にしてはだが)アーグラーヘ行くのに明日まで待たねばならないとはもどかしい。しかし切符売場に並んでいる長蛇の列を見て厭になり、明日乗る直前に買おうかと甘い考えが湧き上がってきているところに、ちょうどリクシャー・ワーラーのおじさんが猛烈な早口で喋りながら近づいて来た。
ヒンドゥ語なので、「負けろ」以外の言葉は知らない僕にはてんで理解できない。真面目な顔して息継ぎもしないでまくし立てるので、何をそんなに怒っているのだろうと、僕と銀孫クンは呆気に取られてしばらくぽかんとしていたが、やがて我に返って考えてみると、何も悪いことをした覚えがなかったものだから、これは単に客引きしてるだけだろうと、そのおっさんを無視して、
「さあ、ホテルに戻ろう」
歩き出すと、リクシャー・ワーラーのそのおじさん、僕たちの前を後ろ向きのまま歩きながら、更に息継ぎなしに猛烈にまくし立て続けた。そのとてつもない早口の謎の言葉の羅列の中に、ただ一言だけ聞き取れる言葉があった。
「q=%)$#m^;¥f^Szおーちゃdf:dg"q^sd:l:おーちゃ、おーちゃ、−rt−r;mc,,pHP"er!……」
つまり「おーちゃ」という言葉だけ聞き取れた。『チャーイ』のことを『お茶』と言うのだとどこで日本人に習ってきたか知らんが、そうか、
「お茶飲んで、土産買えと言ってるんだろ、どうせ」
僕は銀孫クンに向かって、
「こんな奴は相手にすんなよ」
と知った風な口をきくと、早口のおっさんを交わして逃げようとした。しかしおっさんは少しもめげはしない。
「idsfm:q:fmrgi:dispfjdl#+YL_rlkhgot&−#<>f%iuh〜`/t
おーちゃ、おーちゃ、おーちゃ!!!」
お茶か何か知らんが滅茶苦茶だ。言葉が通じないおっさんは自棄になり、駅の観光案内所からパンフレットを一部抜き取ると、僕の前に拡げて見せた。それでまた、
「おーちゃ、おーちゃ!」
と絶叫を繰り返している。そのパンフレットを見てみると、綺麗な城の写真が載っていた。題名が『ORCHA』になっていた。ははあ、「おーちゃ、おーちゃ」とは「おー茶、おー茶」ではなく、「オーチャ、オーチャ」だったのか。こんな地名はガイドブックの地図にも載ってはいないが、インドではそれなりの観光名所みたいだ。
僕がしばらく黙ってパンフレットを読んでいるのを見て取ったリクシャー・ワーラーのおっさんは絶叫をやめ、落ち着いた声になると交渉に切り換えた。
「一日200ルピーでどうだ?」
一応確認したが、二人で200ルピーだそうだ。今日は行く所もないし、値段も特に高くはない。それでも習い覚えたばかりの必殺のヒンドゥ語で、
「カムカロウ」
と言ってみると、
「よっしゃ、175にしよう」
あっさり値下げした。簡単すぎて味気なかったが、それで銀孫クンにお伺いを立ててから、行こうということになった。まずホテルまで乗せてってもらい、カメラなどを取って来た。
ジャンシーは何もない所だが、郊外へ出ると田園風景が広がっていて、のんびりしていていい気分だ。行先はお茶のおっさんに任せることにして、最初はけばけばしい寺院(名前は忘れた)へ連れてってもらった。
ヒンズー教の寺院は靴を脱いで裸足で入らなければならない。地面が焼けて熱いので、回廊沿いに回って行くと、人がたくさんあぐらをかいていて、一緒に座れと陽気に呼びかけてきた。午になったらいいことがあると言う。仕方なく腰を下ろしていると、楽器を持っていた一団がジャンジャカ大きな音で鳴らし始めた。妙に楽しいが、耳元で平気で鳴らしまくるからたまらない。
そのうち午になり、座り込んでいた前の扉が開くと、みんなが騒ぎだした。お堂の中へと我先に入って行こうとする。偉い僧侶みたいな恰好をした坊主が出て来て群衆が殺到、手を握ってもらおうとする。インドでは神でも人気投票みたいに「一番好きなのは○○神」と言ったりするが、さしずめ僧侶もアイドル歌手のような存在なのだろう。しばらく信者たちの様子を呆れて見ていたが、すぐに飽きてしまい、けばけばしい寺院から出た。
寺院の門前には土産物屋がたくさん出ていた。数ルピーのがらくたが多い。僕はがらくたが好きなので、腕輪とか指輪とかペンダントとかいっぱい買った。すぐ横にはチャトルブージ寺院という巨大な廃墟がある。『けばけばしい寺院』ができるまで使われていたが、今ではお払い箱になってしまっているそうだ。
けれども僕は余程こちらの黒々とした廃墟の方に惹かれた。銀孫クンと二人でこの中に入って行くと、一階で老婆が一人、黒い神の像の前で香を焚いているだけだった。ここは外も中もみんな黒い。まるで『黒ミサの館』みたいだった。
外からいくつも尖塔が立っているのが見えたので、登ってみようということになった。打ち捨てられた人気のない巨大な楼閣を登って行くと、まるでダンジョンの中に紛れ込んでしまったかのような錯覚に囚われた。ストレートには上へ上がって行けないし、どこにいるかすぐにわからなくなってしまう。RPGを体でしているみたいだ。
上の方の部屋には、床一面に灰のように軽い、細かい砂が降り積もっていたり、丸天井一面にコウモリがぶら下がっていたりする。ようやく屋根の上に出てみると、高台になっているせいもあって、遠くまで景色が一望できた。『リアル・ファンタジー・ワールド』をここに来て一つ見つけた。偶然来たとはいえ、お茶のおっさんには感謝せねば。
一階まで下りて行くのにもまた時間がかかった。そもそも上がって来た通路など覚えていないし、通路はいくつもある。とにかく階段を見つけては下へ下へと下りて行くだけだった。けばけばしい寺院の方は巡礼者で賑わっているが、こちらは若干のインド人観光客が来ているだけだ。外国人も一人もいない。
一階まで下りると、少しばかり裕福そうなインド人観光客の夫婦が話しかけてきた。僕たちが日本人だと知ると、
「インドの○ヨタに勤めてたことがあるよ」
とか、
「ここの寺院は素晴らしい」
とか、いろいろと喋りだした。どうやら日本びいきのようだ。しかしこの人たちは上には上がって行こうとはしなかった。
黒い寺院を出ると、今度はお茶のおっさんは、城へ連れてってやると言った。走っている間、城がどんなに素晴らしいかを熱弁を揮って熱く語りだしたのだが、そうするとヒンドゥ語になってしまうので、こっちはさっぱりわからない。
しかし宮殿の廃墟に到着し、中に入ってみると、ここに来たのもまたまた正解だった。城からの眺めも素晴らしかったが、城壁、庭園、街、川、城門、これらの造りは中世ヨーロッパの城そのもので、ここもまさしくファンタジー・ワールドだ。この城の造りはファンタジー小説を書くに当たって非常に参考になると思い、僕はカメラのシャッターを切りまくった。
帰りに、道端にテーブルを出している食堂でめしを食うことにした。店の人はやけに陽気だ。お茶のおっさんのことを、
「こいつは超真面目なリクシャー・ワーラーだぞ」
と言って誉め称えている。しかし実際、お茶のおっさんは稀に見る『いいリクシャー・ワーラー』だった。ところがこの食堂のコック、道端にある竈に火を起こしたかと思うと、一品作っては話をして料理を中断し、しばらくしておもむろに料理を再開、もう一品作ると、今度はお茶のおっさんのリクシャーに乗って遊び始めた。
なるほどこのコックから見れば、お茶のおっさんは超真面目に見えるだろう。おい、早く作れよ、と思っていると、そのままエンジンをかけてどっかへ行ってしまった。なかなか戻って来ないので、
「あいつどこ行ったんだ?」
とお茶のおっさんに訊くと、
「さあ」
と、全く埒が明かない。客の注文を途中で放り出して、何考えてんだ。
やっと戻って来たかと思うと、料理を再開しないで、
「オーチャはどうだ? いいとこだろ」
などと言いながら、リクシャーのエンジンを噴かしている。
「注文した料理がまだ全部できてないぞ」
と言ってやると、
「何が食べたい?」
と、とぼけたことぬかすものだから、
「これこれとこれこれがまだだろが」
「ああ、それは今は品切れだよ」
最初に注文した時にはOKと言っていたではないか。ほんとにとんでもない脳天気な商人だ。商売する気なんかまるでない。僕と銀孫クンは呆れ返り、残りを食うのは諦めた。
帰り途、リクシャーで走っていると、道端を歩いている老人とか、赤ん坊をおんぶした女の子とかを見かけ、いい景色だと思ってカメラに収めようとするのだが、お茶のおっさんはすっ飛ばすし、道がでこぼこでがたがた揺れるしで、上手くいかない。横を通り過ぎると向こうが気づき、笑みを浮かべて手を振ったりする。その笑顔の純真なこと。ここはツーリストずれしてなくていい。写真にできなかったのは残念だ。
ホテルに到着した時には、僕はすっかり満足していて、
「175に値切ったけど、やっぱり200やろうよ」
と銀孫クンに持ちかけた。そこで一人100ルピーずつ出したが、僕は更にお茶のおっさんに30ルピー上乗せしてやった。こんなことはあとにも先にもないことだ。お茶のおっさんは喜んで帰って行った。
考えてみれば、30ルピーなど日本円にしてみれば百円程度で、日本では自動販売機で缶コーヒー一本すら買えないのだが、貧しくてケチな僕にしてみれば大盤振る舞いなのであるから、お茶のおっさんよ、許せ。僕は自ら進んでチップをやったりなどはしないのだから。とにかくそれだけオーチャは素晴らしいとこだったわけだ。これまでで一番いいとこだった。今日はほんとにいい拾い物をしたなあ。
4月1日 晴時々曇 ジャンシー 〜 アーグラー
今日は一日移動に費やしたようなものだった。今まで列車が定刻通り到着したことなど一度もない。しかし結果的にはこれがインドで最後の列車での移動になったのだった。何が原因かは知る由もないが、列車は途中の小さな駅で二時間半も停車しているという始末だった。お蔭で、四時間でアーグラーに着くところを、七時間もインドの列車に乗れて、嬉しさの余り発狂しそうだった。
余程空いている路線でない限り、発車前に窓口に並んで買える乗車券は、『ジャーニー・チケット』という、最下等の二等より安い立ち乗り切符だけだ。待つことが嫌いな僕は、この切符を手に入れるのが精一杯だった。
ジャンシーは交通の要衝で、行先のアーグラーは世界的な観光地。席に座れるわけはないと思ってはいたが、それどころではなかった。この列車の混み具合は異常だ。これで脱線事故でも起きれば、一発で二十万人くらいは死者が出るのではなかろうか。もう荷棚を占有しようなどと言っている状況ではない。
立ちっ放しだけは避けたかったので、車輌の中に入ることもやめ、乗降口で早々と座り込みを決めた。しかし車輌の中もすぐにすし詰めになり、中に入れない乗客がここにも殺到してきた。荷物と人間がぎゅうぎゅう詰め込まれてくる。こうしていると、握られるシャリの気持ちもだんだんわかってくるような気がする。
あまりにも狭くて膝を抱えて座り通しも疲れるので、立ったり腰を下ろしたり、もう背中もケツも、汗と泥で雑巾状態だ。ジャーニー・チケットとはまさに、『掃除付き切符』である。安さと引き替えに、服で列車の床掃除をしてから出て行かなければならないとまでは予想していなかった。ああ、今頃銀孫クンは涼しいAC付き車輌で一等寝台に長々と寝そべり、列車旅行を満喫してるんだろうなあ……。
おまけに前に立ってるシーク教徒のじいさんは、僕の顔の前で平気で屁をぶっ放す。このシーク教徒たちがまたうるさい。列車はドアを閉めずに走っていたが、立ったままドアから身を乗り出して外の景色を眺めたりしながら、何を討論しているのか、真剣な表情をしたまま三人でわいわい騒いでいる。シーク教徒だからみんなターバンを頭に巻いているのだが、この中の屁こきじいさんは、富士山型に下へ行くほど広がっている、膝下まである白いワンピースを着込み、首から腰へと、紐でおもちゃのような短剣を吊り下げていた。まるで漫画のキャラクターだ。
僕は肉体的精神的苦痛を紛らわせようと、文庫本を取り出して読書を始めた。インドで解読してやろうと思って日本から持参した『リグ・ヴェーダ』(もちろん翻訳本)だ。しかしこれが日本語に訳してあるのに、読んでてもさっぱりわからないし、だから当然面白くもない。解読どころか、ただの一文も日本語として意味を拾うことができない。これではちっとも気晴らしにならない。
ところが騒いでいたシーク教徒たちは、この本に気づくと急に興味を示して静かになった。文庫本を指差して何だかんだ言ってくるが、ヒンドゥ語なのでもちろん僕にはわからない。すると屁こきじいさんが僕の手から本を取り上げた。それを横向きにして神妙な顔つきで見ている。それからまたいろいろとわめきだした。
シーク教のご本尊というのは、神の像とかではなくて教典だそうだ。パキスタンへ抜けられるアムリトサルという町に、インド式金閣寺みたいな『黄金寺院』という総本山の寺が池の中におっ建てられていて、その中に祀られているのはシーク教典で、何の意味があるのか、巡礼者たちはその教典に向かって拝むらしい。だから書物という形態に対して、屁こきじじいであっても異様な興味を示すのだろう。
僕はじいさんの手にした本をまた縦向きにすると、こう読むのだと言って、指で文字を縦に辿ってみせた。じいさんも他の連中も納得いかないという顔をして、また本を横にする。僕も意地になり、
「違う、違う、こう読むんだ」
また縦向きにした。屁こきじじいは不思議そうな顔をして、「こうか」とばかり、指で文字を縦になぞってみせた。
「そうそう。日本語は縦に読むんだよ」
僕が頷いてみせると、みんな感心したように「おー」っと驚きの表情を見せた。別に縦に読む言葉があろうが、下から上に読む言葉があろうが、ぐるぐる回りながら読んでいく言葉があろうが、大したことじゃないだろうとは思うのだが、この人たちにしてみれば、横書きでない言語が存在するということを、この時初めて知ったに違いない。たかが文庫本一冊のことだが、屁こきじいさんにしてみれば、まさに未知との遭遇だったわけだ。
アーグラー駅に到着した頃にはもう日が暮れていた。やっと地獄行から解放されて列車からプラットホームに降りると、ここでも例によってリクシャー・ワーラーたちが群がり寄って来た。
「ちょっと友達捜さなきゃなんないんだよ」
と交わしながら、一等車輌の方へ歩いて行くと、銀孫クンにはすぐに出会えたが、彼は早速捕まったリクシャー・ワーラーに乗ると契約してしまったようで、しょうがないからそれに乗ることにすると、さっきから僕について来ていたリクシャー・ワーラーが、
「日本人は嘘つきだ!」
と急に怒りだした。僕が、
「あんたのに乗るなんてまだ言ってないだろ」
と言うと、そのリクシャー・ワーラーは、
「日本人は悪人ばかりだ、日本人は悪い、悪い!」
とわめき散らしながらどこかへ行ってしまった。うーむ、そう言えば、既に『魔のトライアングル』に突入しているのだ。アーグラーに必要以上に恐れを抱いている銀孫クンは、早くも出ばなを挫かれてしまっていた。
それでも僕は緒戦で負けてはならじと、ホテルへ強引に連れて行こうとするリクシャー・ワーラーに向かって、
「タージマハルへ行け!」
と命令口調で強く言った。
「もう夜だ。タージマハルは閉まってるぞ」
とリクシャー・ワーラーは言ってきたが、
「いいから行け。行かないと、他のに乗るぞ」
と出たら、
「しょうがないから行こう」
と折れた。タージマハルを今日見るつもりではなかったが、その近くに安宿街があるはずだから、着いたらそのまま地図を頼りに安宿街へ行ってしまおうと思ったのだ。
銀孫クンがリクシャーの中で、
「一等寝台は冷房が効き過ぎてて寒かったよ」
と言って笑った。ちぇっ、贅沢な高校生め。こっちの生き地獄状態など知るまい。
「タージに着いたよ」
ワーラーが言ったので降りてみると、確かにでかい門があったが閉まっていて、おまけに暗くて中も見えない。僕はタージマハルはどうでもいいから、周囲を見渡してみた。灯り一つ見えない。うーむ、この近くにあるはずなんだが……、と早くも弱気になってきた。昼間の強行軍が祟ってもうへとへとだ。
「あんたのホテルはいくらだ?」
僕はリクシャー・ワーラーに訊いた。もはやここから歩いて安宿を探す気力が湧いてこない。ここぞとばかりにリクシャー・ワーラーはべらぼうな値段を言ってきた、1000ルピーとか何とか。
「もっと安いとこは?」
当然そんな高級なとこには泊まらない。ホテルへ連れて行こうとするこの手のリクシャー・ワーラーはたいてい客引きを兼ねていて、いくつかのホテルと契約しているはずだ。まず値段の高い所から言い出すのが常道で、それを次々とはねていく。
最終的に300ルピーのホテルになった。これが一番安いとこだと言う。そんなはずはなく、この近くに50ルピー程度の宿がごろごろあるはずなのだが、もちろんリクシャー・ワーラーはマージンのもらえない安宿に連れてってくれるはずがない。疲れ切って弱気になっていた僕は銀孫クンに、「そこにしようか」と持ちかけた。裕福な高校生銀孫クンに否応はない。
「じゃあそこに連れてってくれ」
「OK!」
ワーラーはニタリと笑った。
ホテルにチェックインして部屋に入ってみると、床が大理石張りで、バスタブまであった。僕がインド旅行中にバスタブ付きの部屋に泊まったのは、これが最初で最後だった。高級ホテルでもなければインドのホテルに普通はバスタブなど付いていない。シャワーから湯が出ればいい方で、バスルームと言っても、水道の蛇口があってバケツが置いてあるだけというのは少しも珍しくない。
アーグラーはそれほど物価が高いわけではなく、少し上乗せすればそこそこの所に泊まれる。カルカッタなどは、同じ300でもぼろぼろの汚い部屋だった。そう考えれば、贅沢したくなったら、物価の低い所でするに限る。
「やったあー、風呂だぁー!」
僕と銀孫クンははしゃいだが、なんと、よく見るとバスタブに栓がない。何か代用品を使えば済んだのだが、もうくたくたで、そんな考えも湧いてこなくて、
「ざんねーん」
と二人ともあっさりと湯船に浸かることを諦めてしまった。
リクシャー・ワーラーとボーイがまだ僕たちの部屋にいて、ワーラー(Gと名乗った)が、
「明日観光案内に迎えに来るから、何時?」
と訊いてきた。めんどくさいから適当な時刻を言って追い返した。ボーイの方はマッサージして小遣いを稼ごうという魂胆だ。さすがにこの時ばかりは、『マッサージ』という言葉に魅力を感じてしまったが、
「50ルピー」
と言うので、
「いらん」
と即座に断わった。ところが銀孫クンが、
「してくれ」
と言ってマッサージを頼みやがった。ベッドに俯せになり、気持ち良さそうに体を揉んでもらっている。
「ああ、効く効くー」
とか
「ううう、うひゃひゃ」
と歓喜の呻き声を洩らすもんだから、
「上手か?」
と訊いてみると、
「まあまあ上手」
と偉そうに言いいやがる。
「ふーん」
と表では相槌を打っていただけだが、「AC一等寝台で半日寝てたくせに、ホテルに着いたらマッサージ。高校生がそんな贅沢してていいのかぁー!」と腹の中で叫んでいた。ところがこのあと自分のインド用の財布の中を覗いてみると、ルピー切れになっていることに気がついた。僕はこの晩、裕福な高校生から借金する羽目になってしまったのだった。
4月2日 晴のち曇 アーグラー
朝早くから部屋の呼び鈴が鳴りだした。ドアの向こうで誰かがわめいている。うるせーなぁ。まだ疲れの癒えない僕は、そいつを無視してベッドで寝ていた。ところがこいつがいつまで経っても諦めずに、ジリジリと何度も呼び鈴を鳴らしては大声でわめき立てる。昨日のリクシャー・ワーラーのGだ。
いいだろう、こういう根比べなら自信がある。居留守は僕の得意中の得意技だ。僕はピクリとも起き上がろうとはしなかった。だが、若さ溢れる銀孫クンの方がたまらなくなったみたいで、起き出してドアを開けに行った。
「さあ、観光へ行こうじゃないか!」とばかり、Gがはりきって部屋の中に乱入して来た。
「まだ眠い」
僕が起き上がらずにいると、
「まずはアーグラー城へ行って、それからタージ」
と、観光計画をでかい声でわめき立てる。あまりのしつこさとやかましさに根負けして、僕もとうとう寝床から起き出した。
「じゃあ連れてけ」
とアーグラー城へ向かわせたが、ルピーがなくなっていたことを思い出し、
「その前に両替屋へ行ってくれ」
と言うと、
「任せとけ」
と、Gはたちまち両替屋へ連れてってくれた。こういう場合は、旅行者の必須ポイントをよく知っているリクシャー・ワーラーは役に立つ。両替屋はたいていどこへ行っても見つけにくい所にひっそりと隠れていたりする。銀行の方は目立つ場所にあるが、よく待たされるし、手際は悪いし、率は良くない、TCの種類によっては替えてくれない、とろくなことはない。
アーグラー城はでかくて壮観だったが、中に入ってもやたらにだだっ広いだけで、あまりどうと言うほどのものではない。ただ、扉とか窓とか、あちこちにダビデの星(イスラエルの国旗のマークにもなっている六芒星)が隠されていた。
うーむ、これは謎だ。アーグラー城はアクバル帝が建てたそうだし(無論、皇帝当人が石の一つも積んだはずはなかろうが)、敷地内にもモスクがあって、イスラム建築には違いないだろう。イスラム教はユダヤ教の影響を受けているそうだが、イスラム教徒の皇帝が命じて、宮殿にダビデの星を入れさせたとは思えない。
昔のユダヤでは建築士の身分が高く、今でもフリー・メーソン(『自由な石工』という意味だそうだ)という世界中の上流社会人の集まりがあるそうな。むしろこの大建築物を建造するに当たり、ユダヤ人建築士が起用されたのではなかろうか。このユダヤ人建築士たちがこっそり宮殿に自分たちのシンボルマークをちりばめたのだ、ふむふむ――などと一人で推理をしていたが、突如もっと根本的な問題に気づいた。
要するに、誰が造ったかは『俺にとってはどうでもいいことじゃないか』という結論に達したので、もう推理はよしにして、さっさと歩いて上まで行くと、結構近くに真っ白なタージマハルが見えた。さすがにこの二つの建物は馬鹿でかいので、この辺りだとよく目立つ。
城から出る時、中にある土産屋で絵はがきを買ったが、外に出ると、今まで近くに誰もいなかったのに、突然目の前に鞭を手にしたインド人が一人現われたかと思うと、たちまち周囲を七、八人のインド人たちに取り囲まれていた。な、何をする気だっ! どこから現われたのか、こいつらはもしかすると地の底から湧き上がって来た地底人か、さもなくば天から降りて来た天人たちか、この海の物とも山の物とも知れない謎の奴らどもが僕に向かって一斉にわめき立て始めた。
ふと見ると、銀孫クンも向こうで何人かに捕まっている。うぬっ、これが噂の魔境アーグラーなのか。すると、こ奴らは地獄の使者か何かか? 天人とはお世辞にも思えなかったが、この地獄の使者ども、わっと群がり寄って来ては、キャーキャー悲鳴を上げながら、手にした品々を僕に差し出してきた。まるでファンからプレゼントをもらうアイドル歌手の気分に一瞬浸った。僕は知らぬ間にインドで有名人になっていたのだろうか?
いや、違った。真っ先に出現した地底人どもの親分格、鞭を手にした兄さんが、
「ゴヒャクルピー」
と発声した。日本語でだ。よく見れば、黒い革のでっかい鞭で、サーカスの猛獣使いが使ってそうな本格的な代物だ。さては鞭を手にして外国人観光客を脅して回り、カツアゲをしている悪党どもか。いや、それも違ってた。
「高い! いらん」
一言で追っ払おうとしたが、
「ジャアイクラ? ヨンヒャクルピー」
とまたまた日本語で攻めてきた。
「いらないって」
「ジャアイクラ? サンビャクルピー」
「ノーノーノー」
と迷惑そうな顔をして首を激しく横に振ると、今度は他の奴らがまくし立てる。宝石や真珠(みたいな物)を連ねた首飾り、大理石でできた小物入れ、何か訳のわからんバネのおもちゃ、スタンプ、絵はがき、サンダル、竹箒、それぞれ自慢の逸品を手にして目の前にしゃしゃり出て来ては、売り物でもってこれ見よがしにデモンストレーションをおっ始めだした。
「いらんっつうの。ノーノー」
こちらが拒否すれば売り子たちは益々シャカリキになってわめきだす。もう耳の鼓膜が破れそうだ。
気がついたら腕に色粉でスタンプをいっぱい捺されていた。鞭屋の鞭はいつの間にか「ヨンジュウルピー」まで値下がりしていた。
「おっ、いいなぁ」
僕はとうとう鞭が欲しくなり、手に取ってみた。
「じゃあ買った」
と40ルピー払うと、売り子たちは益々勢いを得て、猛烈なセールスを繰り広げた。既に一本40ルピー払って買ったというのに、鞭屋はまだ値下げをしている。
「ジャアイクラ? サンジュウルピー」
今40で買ったばかりなのに、そんなことをするかぁ? と思いながらも、これを買わないと損した気になる。30ルピー払ってもう一本鞭を買った。ここまで紙もろくに切れない果物ナイフと安全カミソリしか持っていなかった僕は、魔境アーグラーで二本の鞭を手に入れ、『強さ』が一気にグレードアップした。
それを見て、他の奴らは更に勢いを得た。大理石の小箱も15ルピーまで下がったので買った。すると今度は二個で20ルピーと来た。これも買わないと損する気になったので買った。すると他の奴らは更に更に勢いを得た。
「絵はがきどうだ、絵はがき!」
一枚一枚取り出して見せてくる。
「絵はがきはもう買ったからいらないよ」
しかし値段は城の中の売店より遙かに安かったので、早まったなあという気になった。それから色粉のスタンプセットも、二組で5ルピーと言うので、お土産にいいだろうと、腕に捺された記念に二セット買った。すると他の奴らは更に更に更に勢いを得た。あまりにやかましいので嫌になり、捕まって身動きが取れずにいる銀孫クンを促し、向こうで待っているGに、
「もう行くぞ」
と合図した。
僕がリクシャーの方に向かって再び歩き出すと、売りそびれた奴らは断末魔の悲鳴を上げながら、死に物狂いになって追い縋って来た。リクシャーに乗り込むと、アクセサリー売りがネックレスの束をドサッと僕の腕に引っ掛けてきた。「いらない」と返そうとしても受け取ろうとしない。
「いらないよ!」
とネックレスの束を返そうと差し出しても、手を後ろに組んだままニコッと笑い、
「50ルピー」
見ると、偽宝石の首飾りと偽真珠の首飾りがそれぞれ五本ずつあった。ほんとにインドの物価というものは今もってわからない。いくら偽物とはいえ、これだけたくさんの石を磨いたり、繋ぎにしている真鍮を加工するだけでもかなりの手間がかかるだろう。一体インドの人件費はどうなっているのだ? 僕は商人の開き直り戦法に根負けして、50ルピー札を渡した。
銀孫クンはまだ地獄の使者どもの包囲網から抜け出せずにいたので、
「いい加減にしろ! もう行くぞ!」
と活を入れると、Gがリクシャーのエンジンをかけた。竹箒売りは最後の悪あがきとして地面をこれ見よがしに掃いて見せたが、そんな物は只でくれると言われても必要ない。すると今度はサンダル売りだ。リクシャーの中に乗り込んで来た。そうして僕の膝の上に売り物を一足、二足、三足と載っけていく。銀孫クンがやっと乗り込んできたので、
「早く出せ出せ!」
と僕はGに催促した。Gはリクシャーをゆっくりと走らせ始めたが、草履売りは平気で値段交渉をしてくる。ほんとにもう、こいつらのド根性商人パワーには呆れるばかりだ。
「三足で50ルピー!」
おい、俺はタコじゃないんだ。足は二本しかついてないんだぞ。
「もう履いてる」
と、僕は草履売りに自分の足を突き出して見せると同時に、
「早く行け行け! 飛ばせッ!」
とGを叱咤した。そうやって押し問答の挙げ句、僕が急に黙り込んで知らん顔をしたので、草履売りは100メートルほど進んだ所でとうとう諦めてリクシャーから降りた。
ふうー、勝ったぁー。いや、勝ったのか? 改めて見てみると、がらくたをたくさん買い込んでしまっていることに気がついた。うーむ、知らぬ間に……。まだ旅の序盤だというのに、こんなに荷物が増えてしまった。それに、鞭が意外にかさばるものだということがわかった。このあとしばらく持ち歩くこととなったが、リュックの中に辛うじて入るが、そうすると他の物が全く入らなくなるので、リュックの両脇に縛りつけて運ぶという、日本では恥ずかしくてとてもできないようなことをせざるを得なかった。『旅の恥はかき捨て』と言うが、まあ特にインドでは抵抗なく恥がかけるものだ。
このあと鞭がある間は、僕のリュックは街中でもバスの中でも常に注目の的となった。おまけにこれがついているために、バスの荷棚になかなか収まってくれないという困ったことも何度も起きた。では捨てて行けばいいではないか? どうせ日本円にすれば只みたいな値段で買ったがらくたばかりだ。いや、そうではない。こうやって汗みずくの格闘により手に入れた品々なのだ。捨てる気には絶対になれない。
この魔境での闘いにより僕の経験値は一気に増えた。これで少々の相手には負けはしなくなることだろう。ついでにインドにおける買い物のコツというものを体得したような気がする。どうしても今すぐ必要な品物なら、こちらから出向いて行き、掛け値された品物をそれなりの金を払って買わなければならないだろうが、そういった急場しのぎの必需品ではなく、何か土産でも買ってこうというのなら、人の集まる場所へ行ってぶらついていればいい。店を構えている所にこちらから出向いて行ってもあまり負けてくれない。更に、誰かに誘われて店に連れて行かれるのは危険が伴う。
その点、品物を持って徘徊している物売りは、観光客を見つければ向こうからやって来てくれるし、インドでは土産売りに限らず、あらゆる種類の物売りがうじゃうじゃいて、獲物を探して常に動き回っているので、じっとしててもいつの間にか、どこからともなく寄って来る。
その時に、待ってましたとばかりに飛びついてはいけない。売り物に興味が出ても、最初からそういうそぶりは見せない。向こうは決して友好関係を結ぼうとやって来たのではないのだから、こちらは笑顔で応対する必要は全くない。
そして「いらない」とはねつけたり、「高い」と即座に難癖をつける。店ではこれが必ずしも通用するとは限らないのだが、これで「あっそ」と諦めて去って行ってしまう行商人は未熟者である。小さな子供の物売りでもこんなことで諦めて引き下がったりはしない。
相手は宣伝を始め、値段交渉に入ろうとするが、それでもまだ興味のないふりを続ける。すると価格はまるで底なしのように破格値へと下がっていく。これはベテランの物売りほど(人格によるところも大だが)最初はふっかけてくるから、自分だけが大安売りにぶつかって非常に得した気分になり、ついつい買ってしまうが、それでもまだあちらには儲けがあるのだ。
まあ、あまりケチるのも良くないかもしれない。何もかも是が非でも史上最安値で買う必要などないからだ。売り子の方は値段の駆け引きが仕事のようなもので、その手腕により儲けの幅が広がったり狭まったりする。単純に言えば、お金持ちはポーンと買ってしまえばいいのだ。そして貧乏人は激しく食い下がる。それが貧富の差の激しいインドのお国柄に合っているというばかりか、世界中の市場経済にも当てはまっていると思う。時間と労力とを費やすか、それとも代わりに金を費やすかというだけの問題だ。もっとも理屈ではそうだが、僕など日本では、必ずしもこの通りにはいっていないというのが現状だ。
とかく日本人は、旅行に出るとパアーッと金を使ってしまいがちだ。普段はスーパーで5円、10円をケチっていながら、旅行先では万単位の金を平気で無駄遣いする。たまの贅沢気分を金で買っているといったところだろうか。
ところがインドのような定価というものがない国で、「安い安い」とありがたがって土産物を買ったあとに、別の日本人から、「それと同じ物を、私はいくらで買いました」などど数分の一の値段を聞かされると、途端に悔しがる。その気持ちがわからないではないが、そういう人は、適正価格などは知らない方がいいのだ。気分を害されるだけ損であろう。
所詮、インドで値切って品物を買ったと言うが、例えば100ルピーを50ルピーまで負けさせたとしても、300円が150円になったまでのことに過ぎない。インドなら安宿代一泊分浮かした値打ちになりはするが、日本ではドーナツ一個だ。
値切るというのはつまり、損しないように用心するというよりも、売り物の値段の駆け引きという、今時の日本ではあまりすることができなくなってしまったその行為自体が面白くてするのだ。それでもあまりやっていると飽きてきて、これも面倒になってくる。
それにしてもインドで安旅行すると、ケチになる。僕なんかは元々ケチだったが、更にそのケチに磨きをかけて帰って来た。ケチと言うより、しみったれた貧乏性に磨きがかかったと言った方が近いだろうか。日本にいては、こんなことはちっとも美徳にはならない。他人から軽蔑されるだけだ。安旅行をした弊害とでも言うべきか、それともインドで値切りまくった祟りとでも言うべきか。
次にタージマハルへ行こうとしたが、走っている途中でGが、
「大理石工場へ行かないか。カーペット工場はどうだ」
としつこく勧めてきた。
「いらない、いらない」と言っても、
「見るだけ」と言って、タージマハルへなかなか行こうとはしない。
「じゃあ、見るだけだぞ」と行かせた。
着いた所は大理石工場兼店で、早速店の主が出て来ていろいろと売り物を勧める。
「見るだけだ」
と最初に断わると、
「それでOK」
と言ったので、見るだけで店を出たが、さすがにここは大理石の加工が盛んで、大理石でできた面白い置物や家具などがあった。値段は高いし、こんな重い物を持って行くわけにはいかないので当然買わなかった。
「さあ、見たぞ。タージへ行け」
とGに命令したが、Gはまた途中で、
「もう一軒だけ見てくれ。客を連れてくだけで俺にはマージンが入って来るんだ」
と正直に言ったから、
「じゃあもう一軒だけだぞ」
と連れて行かせた。
今度はカーペット工場兼店だった。店の主は買いに来たものとばかり思っていたのだろう、自ら先頭に立って工場の中を案内した。ここでも最初に、
「見に来ただけだ」
と断わっておいたが、主は、
「それでいい」
と余裕しゃくしゃくだった。手作業でカーペットを作り上げていく行程を見られたのは良かった。見学が済むと、案の定、主は僕たちを広い売り場へと連れて行った。適当に眺めていたが、あれこれと売り物を勧めてくる。「とにかくいらない」の一点張りで押し通した。
「つまらないのか?」
と訊いてきたから、
「つまらない」
と答えてやった。実はつまらないこともなかったのだが、高級品みたいで、値段はべらぼうに高かった。
こうしてGへの義理立てを済ますと、今度こそタージマハルへ行かせた。これまで出会った人たちは、みんなアーグラーやタージマハルのことを良く言ってなかったが、僕には期待以上に良かった。とにかくよくこんな馬鹿でかい墓を総大理石で造ったものだと、その馬鹿さ加減にまず感心した。おまけにここの真っ白な大理石は選り抜きの石材だそうで、暗い廟の中で懐中電灯の光を大理石に当てると、光が透けて、大理石の中が光って見えるそうだ。
のちにデリーで出会った弓外クンという若者から、アーグラーで雇ったガイドからそれを実演してもらい、感動したという話を聴かされたが、僕はその予備知識を既に持っていて、懐中電灯も用意して行ったものの、肝腎な時にそのことをすっかり忘れてしまっていた。暑さのせいか歳のせいなのか、どうも忘れっぽくて困る。お蔭で弓外クン一押しの感動の場面に巡り会えずに終わってしまったのだった。
せめて誰かがそういうことをしていたら、それを見て思い出しただろうに、人はうじゃうじゃいるのに、知らないのか、それともそんなことには興味ないのか、誰一人懐中電灯で照らしている者はいなく、みんな縦穴の底に置いてある棺桶を覗き込むことに夢中になっていた。
それにしてもここには観光客が多い。ひっきりなしに人が出入りしている。他の観光地と違って、タージマハルはインド人より西洋人観光客の割合の方が大きいに違いない。修学旅行みたいな、オーストラリア人の女子高校生の団体まで来ていた。
敷地内に入る前に、「ここで待ってるぞ」と言うGをクビにした僕と銀孫クンは、有料区域から出ると、今度は裏からタージマハルを眺めようと、乾季で水が少なくなっているヤムナー川の河原へと下りて行った。河原からの眺めもまたいい。
一つ発見したことがあった。裏から見ると、タージマハルのドームに三本ほどひびが入っているのがはっきりと見て取れたのだ。
夕涼みの時間になったようで、まずは近所に住んでいるガキどもが大勢で寄って来て、わいわいと騒ぎだした。僕がチョコレートを食っているのを見て、「チョコレートくれくれ!」と騒ぎ立ててうるさかったので、チョコレートはやらずに、代わりに不味い漬物みたいな味がする飴をやった。インドの子供は飴は欲しがらないが、チョコレートはどこへ行っても欲しがる。チョコレートは高級品みたいで、インドにしては高かったが、飴は安くて、駄菓子屋で一個20パイサ(100パイサで1ルピー)くらいでばら売りしている。
このガキどもが元気の塊みたいな奴らばかりで、いつまでもはしゃぎまくっている。カメラを向けるといろいろポーズを取って見せたりするが、見たくもないのに、唐辛子みたいなポコチンまで引っ張り出す奴もいた。なんでいつもいつもこういう奴がいるのだ?
こいつらも晩めしの時間が来ると我が家へと帰って行く。しかしほんとにエンターテイナーたちだ。家に向かうまでの砂地の上で、何度も何度も一斉にずっこけてみせてくれた。
お次はおじさん連がやって来た。僕たち二人のそばに輪になって座り込み、雑談を始めた。しかし何か喋っていると、その中にいた一人のおじさんが、
「ハイ・イングリッシュはやめてくれ。わしは頭悪いからわからんよ」
としょっちゅう言いやがる。何がハイ・イングリッシュなものか。あんたがわからなかっただけだろが。こっちだって『ハイ・イングリッシュ』なんか使えるものか。
暗くなってから、ぶらぶらとホテルの方角へ歩いて戻ったが、ホテルの位置など覚えてはいない。そこで、道端に屯していたサイクル・リクシャーたちに、
「ホテルへ帰りたいから、乗せてってくれ」
と言うと、「1ルピー」だと言う。やけに安いなあと思い、「××ホテルだ」と言うと、「じゃあ3ルピーだ」と言ってきた。1ルピーで行けるのはマージンの入って来るホテルだけなのだろう。それでも安いのでホテルは近いんだろうとは思ったが、今日身に着けた値切りの癖がついつい出て、
「1ルピーに負けろ」
と言ってやった。わずか3ルピーを値切るのはまさに醍醐味だ。
そこでああだのこうだのと、わずかな金額のことで言い合いになったが、結局両者歩み寄り、2ルピーということになった。
ところが200メートルほど走った辺りで角を曲がると、
「着いたよ」
ワーラーが言って指差した。確かに自分たちの泊まっているホテルだ。暗くて目印が見つけられなかっただけだ。まあ、道に迷って遠くへ行ってしまうことを考えれば安いものか。僕はポケットに手を突っ込むと、2ルピー硬貨を取り出し、ワーラーに渡した。そしてホテルに向かって歩き出すと、
「おっ、5ルピーだ、5ルピーだ!」
とワーラーが背後で歓喜の叫び声を上げた。暗いので間違えて5ルピー硬貨を渡してしまったらしい。
「つり返せ」
と言ってやったが、
「やだよー」
と子供のようにはしゃいでいる。そんなに嬉しいのならくれてやろう。
僕と銀孫クンは部屋に戻る前に、近くの屋台でコーラを飲んだ。店の親子がいろいろと話しかけてきた。すると奥からシタールの音色が流れてくる。おやじが弦が三本も失くなっているギターを持って来たので、銀孫クンは調子に乗ってそれを弾き始めた。もちろん音楽にはならないが、するとじいさんが出て来て、
「シタール工場を見に行かないか?」
と訊いてきた。僕はくたびれていたから、「ホテルに帰る」と答えたけれど、銀孫クンは、「見たい、見たい」と言い出し、そのままじいさんに連れて行かれた。
「買うなよ」
と一応銀孫クンに釘を刺しておいたのだが。
ホテルに戻ってベッドの上でごろごろしていてふと思い出した――「鞭を忘れた。しまった!」Gのオート・リクシャーの後ろにある小さなトランクの中に入れっ放しにしたまま、Gをお払い箱にしてしまったのだ。あれは気に入ってたんだけど、持ってれば持ってるで邪魔になるし、まあいっか。これも天命と思って諦めよう。
やがて銀孫クンが帰って来た。
「買っちゃったぁー」
ドアを開けた銀孫クンの片手には大きなギターケースがぶら下がっていた。
「それギター?」
「うん」
「いくら?」
「5000ルピー」
やれやれ……、言わんこっちゃない。
「でも欲しかったから、でも欲しかったから」
沈黙した僕に向かって、銀孫クンは弁解するように何度も言った。
「お人好しだねえ」
「それで、金貸してくんない?」
今朝両替したばかりなのに、もう翌朝両替しなければならない。要するに有り金みんな持ってかれたというわけだ。500ルピーしか持ってなかったら、500ルピーで買えただろう。ゆうべは僕の方が借りたが、今晩は裕福な高校生にルピーを貸す側になってしまった。
4月3日 晴 アーグラー 〜 マトゥラー
何ということか。今朝も八時半にまた激しく部屋の呼び鈴が鳴った。僕にはやはり起きる気力はないのでほっておこうとしたが、しつこく鳴らし続ける。ううう、もしやあの声は……。
銀孫クンが根負けしてドアの鍵を開けに行った。ドアを開けて元気いっぱい部屋の中に飛び込んで来た体操のおにいさんは、誰あろう、やはり昨日クビにしたはずのGだった。猛獣使いよろしく鞭を二本手にしている。僕の最新鋭兵器は意外にも戻って来たのだが、Gが親切心だけで忘れ物を届けに来てくれたとはどうしても思えないのだ。
「さあ、観光に行こうぜ!」
昨日引導を渡したのに、ちぃーっともわかっとらん。まあ、わざわざ鞭を持って来てくれたので、追い返すわけにもいかない。許す。そこでホテルをチェックアウトしたあと、銀孫クンの連日の両替、続いて、
「美味い店はないか?」
「あるぜ」
と、レストランへ連れてってもらった。『レストラン』と言うと、日本語では高級感が漂うが、僕がインドで行くレストランとは、ほとんどみんなあっちの大衆食堂のことだ。
朝めしを食い終わると、またもや土産屋に連れて行かれてしまった。
「バス停へ行け」
と言ったのだが、
「マトゥラー行きはまだまだ出ないよ」
などと言っている。
「それでもいいから行け」
と言うと、
「一人連れてくと10ルピー入るんだ」
と、今日ははっきり言った。
「だから頼むよ」
しょうがないので土産屋で時間潰しすることにした。店員が来て、
「パジャーマーを作りませんか?」
と勧めてきた。ジーンズは暑いので、買ってもいいかなと思っていると、
「オーダーメイドです」
と言う。
「時間かかるんじゃないの?」
と訊いてみると、すぐできると言うことだったので、布を選び、サイズを測ってもらって作らせた。
待っている間、店員たちが音楽をかけてインドの歌謡曲を歌ったりするので退屈しのぎにはなった。そこにおじさんが一人やって来た。店員の一人が、
「この人はダンスの名人だ」
と言った。別に興味はないのだけれど、
「じゃあ、踊ってみせてくれ」
と言うと、
「まずあんた踊ってみせてくれ」
と、ダンスに命を懸けているのか、マジになっている。そこで音楽に合わせて適当に踊って見せてやると、おじさんムッとしてしまった。名人のお気に召さなかったのか。
「さあ、今度はあんた踊ってみせろ」
と言うと、
「あんたダンスが上手すぎる。踊るのやめた」
このおじさん、どんなに下手くそなダンスの名人なんだろうと、にわかに名人芸を見てみたくなり、
「踊ってみせてくれ」
とさんざん囃し立てたのに、おじさんは尻込みするばかりで、絶対に踊ってみせようとはしなかった。
そうこうするうちにパジャーマーができあがり、履いてみたらちょうど良かった。
「上もどうです?」
と店員が言うので、
「上のパジャーマーはいらないよ」
と答えると、
「上はパジャーマーじゃなくてクルーターですよ」
と笑われた。
店を出ると、次にGは旅行会社に連れて行こうとしたので、
「おい、いい加減にしろ!」
と、とうとう怒って怒鳴りつけてやった。全くこの国は、何もしなくても誰かがあれこれと面倒見てくれる。途方に暮れてしまうことはなくて、それはそれでいいのだが、なかなか自由に行動させてくれない。親切行為を切り売りしようとする奴らで満ち満ちている。まあ、面白いからいいが、これがいつもいつもだとうんざりしてくる。
バスターミナルでとうとうGと手を切り、マトゥラーへ向かった。銀孫クンは大道芸人でもあるまいに、ずーっとギターケースを抱えてて、さぞかし大変だろう。
マトゥラーに着くと、とりあえずホテルを見つけて部屋に荷物を置き、ヤムナー河へ行ってみた。ここもヒンズー教の聖地の一つだ。川縁にガート(沐浴場)と寺院がある。聖地と言ってもバラナシと同じように、金をせびり取ろうとする奴はいる。聖地の壁に立ちションしてる奴もやっぱりいた。勝手にガイドがついて、ああだこうだと解説を始めたが、全く無視してガートへ下りてった。
船頭に訊くと、下流の橋の辺りまで行って帰って来て10ルピーだと言うので乗ることにした。乾季だから水は少なくなっている。他にも船遊びをしている家族連れなどがいて、手を振ると子供たちも手を振り返してきた。その舟が近づいて来た時、銀孫クンが何を血迷ったのか、両掌を合わせて、
「ナマステー」
と何度も言ったが、完全に無視されていた。インド人は挨拶をすることはほとんどない。そういう習慣がないみたいだ。日本でだってする人はするが、たいていは形式上のものだろう。日本の『こんにちは』に当たるのは、ヒンドゥ語では『ナマステー』だが、これを日本人がインド人の口から聞けるのは、ほとんどの場合、営業上のサービスとしてだけかもしれない。外国人と見たら、まず英語で来るし、インド人同士が挨拶しているのは見たことがない。
帰りは歩きながらレストランを捜したが、ちっとも見つからない。大通りを街の中心部辺りまでやって来ると、ようやくそれらしきものが見つかった。純インド大衆食堂といった趣のある店だ。菓子は店先のケースの中にいろいろな種類が並べられていたが、めしの類は、プーリーとカレー、あとはサモーサー(マッシュポテトの包み揚げ)みたいな油で揚げたスナック類と、ラッシーしか置いてない。
プーリーはチャパティを揚げたものだが、店先で揚げているのを見ていると、なんであんなに風船みたいに膨れるのだろうと思うくらい膨れ上がって、旨そうに見えた。これを一種類しかないカレーにつけて食べたが、チャパティと違ってこれはいける。日本人の舌を持つ僕としては、カレーもつけずにそのまま食べても旨いと思った。
他の揚げ菓子にも挑戦してみたが、四種類しかないので全部注文してみた。さすがに腹いっぱいになったけれど、店員が「甘いよ」と言っているインドの菓子もいくつか買って帰った。見た目は洋菓子のようにも見えるし、和菓子のようにも見える。
カレーの本場のインド人が「甘いよ」と言うのだから、どうせ中辛くらいだろうと思って、これをホテルに戻ってからおやつに食べてみたが、どれもこれもとんでもなく甘い。日本ではちょっとお目にかかれない甘さだ。銀孫クンなどは一口囓っただけでギブアップしてしまった。
僕は甘いものにも辛いものにも強いつもりでいたが(厳密に言えば『粗食に強い』。単に貧乏くさいだけ)、それでもこの『砂糖二十倍オリエンタル風味羊羹』とか、『ケーキ蜂蜜漬けスペシャル』みたいなインドの菓子だけは食べ続けることができなかった。(捨てるのはもったいないから、翌日までかけてじっくり平らげたが、急性糖尿病になりそうだ)
ほんとに辛いものは辛いし、甘いものは甘いし、味のないものは味がない。そりゃ当たり前なんだろうが、なんか物足りない、と言うか、かなり物足りない。味が極端すぎて、食ってもどこに入ったのか実感がない。もう少し味にグラデーションをかけて欲しいなあと思う。この究極の『激辛』・『激甘』・『無味』の三味一体から成り立っているのがインドの味なのかもしれない。
マトゥラーでは外国人を見かけなかったし、住民は観光地ずれしていないから、インドらしさが味わえるような気がする。
公園に馬車が停まっていて、もう暗くなっていたからホテルまで連れて行ってもらおうとそれに乗った。仔馬一頭で曳く馬車だが、馭者と合わせて三人乗っていても、坂道でも平気で登って行く。
部屋に入るとホテルのオーナーがやって来て、話しかけてきた。押し被せるような英語を喋る年輩のインド人だ。
「私はアーチストだ」
と、いきなり自己紹介するや、ずっと押し被せるような物言いで哲学談義を一人でおっ始めた。ちょっと怖いので、「出てけ!」とは言えずにハイハイと相手をしていたが、結局最後には、
「売る物はないか?」
と来た。なんだ、外国製品が欲しいだけのアーチストだったのか。
「売る物はない」
と返事して、ついでに、
「お菓子食わないか?」
と余り物の甘い菓子を差し出してみたが、たちまち、
「そうか」
としょぼんとなってしまい、哲学者アーチストはさっさと部屋から出て行った。
夜遅くなって寝ようとしていると、妙に面白い音楽が外から聞こえてきた。更には歌も始まった。バルコニーから身を乗り出して眺めてみると、どうやら近所の公園でジョイント・コンサートをやっているような雰囲気だ。次から次へといろいろな音色や歌声が聞こえてくる。歓声はちっとも聞こえないから、聴衆はほとんどいないみたいだが、もう十一時を回っているというのに、その音量と言ったら半端じゃない。
インド人は音楽を聴く時は、「これでもかっ!」とばかりに音量をとことん上げて聴く。あらゆる場所で、音質の悪い音だろうと平気でラジカセのボリュームを目一杯に上げて聴いている。それを「うるさい!」と言って怒る人も誰一人としていない。とにかく何事に関しても極端を好む民族みたいだ。『騒音』という言葉はインドの辞書を引いても載ってないに違いない。だから暴走族もいないのだろう。ここではみんながいつもいつも暴走している。
4月4日 晴時々曇 マトゥラー 〜 デリー
今日はマトゥラーを出るので、ホテルをチェックアウトし、荷物を背負ったまま午前中は博物館を見に行った。ここには古い仏教美術の出土品などが展示されているらしい。早く来すぎてまだ開いてなかったので、仕方なく門前で待っていた。
しばらくすると、おじさんどもが屋台を引っ張って来て、妙な飲み物を売り始めた。屋台の上にはかき氷の蜜のようなどぎつい色をした液体が入った瓶がたくさん並んでいて、大きな氷も載っている。どう見てもかき氷屋さんだ。
すると通りすがりのインド人たちが寄って来て、小銭を払って一息に飲み干していく。客が「それ」と指差した蜜を、かき氷屋はコップに少し入れ、水で薄め、氷を削ってできあがり、『インド風かき氷ドリンク!』
そう言えば、インドに来て食べたいなあと懐かしくなった日本の食べ物は、かき氷とざるそばだ。かき氷など日本では滅多に食べたりしないのに、気候のせいか、インドではいつもかき氷が食いたかった。日本料理とも言えないが、他には牛肉と豚肉。
そこで屋台に寄ってって、しばらく様子を窺ってから、銀孫クンに、
「飲んでみようか」
と言ったが、
「生水使ってるから」
と言って絶対に飲もうとはしないで、ぬるくなったミネラルウォーターを大事そうに飲んでいる。抗生物質を山ほど日本から持って来てるくせに、この根性なしめ! いや、ほんとはこの銀孫クンの慎重さこそ正しいのだ。一ヶ月ほどのちに、僕は不用心からひどい目に遭うことになる。
しかし通勤途中のインド人たちなのだろうか、みんな旨そうに飲み干しては、『元気×つ×つ! オ○ナ○ンC』、または「フ××ト一発! ○ポ○タンD」みたいになって出勤して行く。「これを飲むと、きっと二十四時間働けるようになるに違いない」僕は好奇心を抑えられなくなった。
「一杯くれ」
氷屋のおやじに言うと、どれにしようかな……と考えるまでもなく、一番ましな色をしている黄色のにしてもらった。レモン味か何かだろうと思ったからだ。
他のと言えば、これはバッタの輸血用血液ではなかろうかとも推測される深い緑、マリアナ海溝の底から汲んで来たみたいな深い青(もちろんマリアナ海溝の底へなんか行ったことはないが)、怨念が染み込んだ地獄の血の池から汲み上げたかとさえ思える深い赤(もちろん地獄へなど行ったことはないし、僕に限ってこの先行くこともなかろう)、観賞用としては素晴らしい、涼しげな色ばかりだが、ちょっと怖くて飲む勇気が出ない。おやじは氷を削り終えるとマサーラー(香辛料)を放り込もうとしたので、
「それだけはやめてくれ!」
と必死で止めたが、おやじは、
「なんでだ?」
と不思議そうな顔をしてまたマサーラーをコップにぶち込もうとする。
「とにかく俺はインド人みたいに年季が入ってないんだ」
と説得して、辛うじてやめさせることができた。
さあ、氷レモン飲もう――「おっ、旨い!」と思ったのは口をつけた一瞬の出来事で、冷たいのはいいのだが、あまりにも濃すぎて甘すぎる。余計に喉が渇きそうだ。
「薄めてやろう」
と察しよく、おやじが水を注ぎ足したが、なぜかちっとも薄くならない。おまけに不味いのなんの、『青じ○』を飲んだことはないが、『青じ○』より遙かに「うー、不味い、もう一杯!」に違いない。おやじはまた水を注ぎ足してくる。しかし味も濃さも少しも薄くならない。レモン味などちっともしない。おやじは僕の様子を笑みを浮かべながらじっと窺っている。「あはは」と僕もおやじに微笑み返した。見るなっつうの!
この正体不明の液体の原料は一体何なのだ? ペンキ工場の排液か何かか? これはほんとに飲物なのか? いくら僕が粗食に強くても、こんなもの……べっ。屋台のおやじが他の客に気を取られている隙に、コップの中身をみんな足元のどぶに捨ててしまった。呪いのドリンクよさらば、故郷に帰るがいい……。
「グッド!」
そう言うと、僕は空になったコップを屋台に置いた。
「じゃあもう一杯行こう! 今度はどれがいいかな?」
と、おやじがバッタの血液を手につかんで微笑みかけてきたので、
「もう充分満喫させてもらったよ」
と、慌てて屋台から逃げ出した。
銀孫クンは暇潰しに、アーグラーで押し売りされたギターを取り出して弾き始めた。たちまち道行くインド人たちが群がって来た。あっと言う間に人垣ができてしまう。
「これじゃ何かしないとなあ」
「じゃあ弾くから歌って」
「よし」
「○○○○は知ってる?」
「そんなの知らん」
「じゃあ××××は?」
「聴いたこともない」
と、銀孫クンのレパートリーと僕が知ってる曲が一つも重ならない。
「じゃあ弾き語りしろよ」
銀孫クンはギターを弾きながら、若者らしく尾崎豊を歌い始めた。一分もしないうちに誰もいなくなっていた。このギターの腕前とこの歌声じゃあなあ……、と納得できたが、
「インド人には日本の歌は理解しにくいんだよ」
と銀孫クンを慰めると、
「やっぱそうだよね」
と、彼は一人で頷いた。
だいたいどこにいてもガキどもは寄って来る。お揃いの制服を着て、髪をポマードでてかてかにしたガキどもが話しかけてきた。どう見ても貧乏な家の子たちには見えない。
「これから学校へ行くのか?」
と訊くと、
「そうだ」
と答える。マトゥラーの観光名所の話などを聴かされていたが、そのうち博物館の門が開いたのでそっちへ歩き出すと、ずっとついて来て、
「ガイドしてやる」
と言ってうるさい。
「そんなものいらん」
と答えて、建物の入口の前まで来ると、
「金くれ、金くれ」
と口々に騒ぎだした。ここから先は入場料を払わないと入れないのだ。結局は物乞いに来たのかと不愉快になり、
「学校へ行くんじゃないのか? 学校はどうした?」
と言ってやると、ふてくされてみんな去って行った。
入口で入場料と荷物預かり料を払ったが、カメラ持ち込み料が20ルピーと高い。それでもカメラだけ持ってって、元を取ろうと展示品を撮りまくった。
博物館の建物はロの字型で、中庭にも展示物があったので見て回っていると、でかいライフル銃を肩に担いだ警官が一人近づいて来て、僕に向かって、
「カメラを見せろ」
と言ったかと思うと、猿並みの速さで素早く引ったくり、常習犯なのか、初めから一つだけ胸のボタンを外していて、そこにカメラをサッと押し込んでしまった。まるでスリの手口だ。
「ほら、カメラ持ち込み料20ルピーは払ってあるぞ」
とチケットを見せて言ってみたが、そんな物見ようともしない。
「え? 何のことだ?」
としらばっくれている。腹が立ってきたので、
「じゃああっちへ行こう。入口で訊いてみろ。来い!」
と凄んでみせると、胸からまたカメラを取り出して、
「これは日本製か?」
と訊いてきた。
「違う。シンガポール製だ」
と答えると、
「いくらだ?」
と訊く。
「70シンガポール・ドル」
「ルピーでいくらだ?」
「1000ルピー」
警官はカメラを返してきたが、今度は「来い」と言って、建物の中へと連れて行かれた。
「俺が何か悪いことでもしたのか?」
と抗議していると、やがて立ち止まり、
「これを写せ」
と言った。不届き警官が指差した所に目をやると、素っ裸の女人像が立っていた。こいつ一体何なんだと益々不愉快になったが、
「もうフィルムが切れてんの」
と言ってやると、ニタニタと笑いやがる。それから女人像の局部を指差しながら、
「なんだ、かんだ」
とヒンドゥ語で言ってはニタニタといやらしそうに笑っていたが、僕がムッとした顔のまま、
「この女が好きなのか?」
と言ってやると、エロ警官はニヤニヤしながらどこかへ行ってしまった。
バスでデリーへと向かう。44ルピー。バスにも格がいくつかあるものの、列車に比べると安くつくし、何と言っても何日も前から座席を予約しておく必要がない。行ったその場で来たバスに乗ればいいのだ。概して本数も列車より多い。これからの移動はバスだなあ。
デリーのバス・スタンドには客引きはそんなにいなかった。ホテルを紹介すると言って高い所をふっかけてくる奴らを断わり、別のリクシャーを拾ってメイン・バザール(デリーの安宿街)へ行ってくれと言って乗り込んだが、ところがこいつも要求した行先へは素直に行こうとしないのがリクシャー・ワーラーだ。リクシャーを停めて、
「この近くにいいホテルがあるんだ」
としつこい。
「ホテルはいいから、とにかくメイン・バザールへ行け」
とさんざん言ってから、
「じゃ、メイン・バザールまであと10ルピー」
と言ってきたからカーッとなり、ワーラーと言い合いになったがいつまでも埒が明かない。この意地汚い奴が10ルピーと言うのなら、これは近いなと思い直し、癪に障るが、その場で降りて、歩いて捜すことにした。近くにいた人に尋ねると、この一筋向こうがメイン・バザールだと言う。案の定、目と鼻の先だった。
メイン・バザールはカルカッタのサダル・ストリートと似て、いろいろな国の人間がごちゃ混ぜになって歩いている。ガイドブックを見ながら安そうなホテルに目星をつけて行ってみたが、どこもいっぱいだったり、ガイドブックに載っている値段とかけ離れている。そもそもデータが古すぎるのだ。
それで適当に当たってこうと思い、『ホテル・アジャイ』という看板があったので、そのすぐそばにあるパン屋か何かで、このホテルはどこだと訊くと、「そこだ」、とすぐ斜交いを指差した。そこへ行って訊いてみると、珍しくシングルルームがあり、今空いていると言う。140ルピーと、先程回って来たいくつかのホテルよりずっと安かったので、その部屋を取ることにした。
このホテルを僕はしばらくの間、『ホテル・アジャイ』だと勘違いしていた。三日目くらいになって初めて、自分が泊まっているのは『ホテル・アンクール』だと気づいた。
銀孫クンはこのデリーにある知り合いの家を基地にしているので、ここでお別れだ。僕はようやくお役御免となった。それで最後の晩餐に出かける前に、しばらく部屋の前で立ち話をしていると、隣の部屋のドアが開いて、若い日本人の女の人が出て来た。それでいきなりシャワーの湯が出ないとか言ってきた。そんなことを僕に言われても……。一応自分の部屋のバスルームで確かめてみると湯が出たので、
「出るみたいだから、ボーイに言って、直してもらいなさいよ」
とだけ言って外へ出た。外国へ行くと、見ず知らずの日本人でも平気で話しかけられるようになるから不思議なものだ。
今夜は久しぶりに一人で眠る。旅は道連れと言うけれど、一人もまたいいもんだ。デリーは悪評ばかり聞かされていたが、僕にしてみれば、メイン・バザールはカルカッタのサダル・ストリートを思い出させてくれ、なかなかいい所だと思った。どうやら僕は人種の坩堝みたいな所が好きなのかもしれない。
矛盾するようだけど、それでも日本人がいたら喋ってしまう。英語がペラペラ話せるわけじゃなし、細かいことまで言えないフラストレーションが溜まってきて、たいていの日本人旅行者は『日本語喋りたい症候群』に陥るのかもしれない。ホームシックにはならないが、僕も例に漏れず、『日本語喋りたい症候群』になってきた、まだインドに来て二十日も経ってないというのに。基本的にお喋りなのだろう。
デリーの夜は少し冷え込んできた。狭いベッドに寝転がり、まだ一文も解読できていない『リグ・ヴェーダ』を読んでいると、他のことばかりが頭に浮かんできた。
 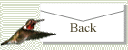
|