|
1.緒戦完敗! インド人詐欺師対カモ日本人旅行者
3月18日 晴/曇 日本 〜 カルカッタ
空港へ向かう電車の中で、友人小町からもらった手紙を読む。大したことは書いてない。しかしなんで手紙なんかくれるんだろう。もしかすると僕がインドでくたばるかもしれんとでも思ってか? 大袈裟な。手紙には新渡戸稲造氏が挟まっていた。ふふん、餞別のつもりか。
そう言えば、綿密な計算の下にはじき出された金額しか持って行かないと僕が言っていたので、「インドで金が尽きたら必ず電話してくれ、金を送るから」と言ってたっけ。なめた真似しやがる。
嬉しくもあり情けなくもある複雑な心境だ。しかし見送りに来て、これから旅に出る僕から千円無心して帰ったもう一人の学生時代の友人凶山よりは遥かにましか。そう思うと、僕はその新渡戸氏(何をした偉人なのかは知らない)をありがたく封筒に戻してお守りとすることにした。
楽に行こうと少々奮発した午の便に乗り、関西国際空港を出て、シンガポールのチャンギ空港で飛行機を乗り継いだが、乗り継ぎ便が遅れ、カルカッタのダムダム空港に着いたのは深夜零時頃だった。
飛行機からタラップに降り立った時には真っ暗だったが、はっきりとわかる変な臭いがした。しかしその臭いを嗅いだ途端、なぜか無性に懐かしい思いが甦ってきた。なぜこんな感覚になったのだろう? もしかすると僕の子供の頃には、日本の空気にはこれと同じように臭いがついていたのかもしれない。いや、逆だろうか、現在の日本の空気が昔の空気とだんだん変わってきて、今の臭いになっているだけなのかも。いつの間にか日本人の嗅覚がそちらに慣れてしまっただけなのだろう、きっと。
空港を出てタクシーに乗ろうとしていると、日本人女性がシェアしようと申し込んできた。そうすることにしたが、乗ったタクシーの運転手が姑息な手段でボろうとしてきた。この日本人大畑さんがプリペイドの乗車券を買ったのだが、乗り場で乗車券を渡した係(らしき)インド人はタクシーに乗った途端に跡形もなく消え去り、運チャンは、
「そんな奴知らん、まだ金もらってない」
とぬかしやがった。日本での綿密な下調べでいろいろと読んで知ってはいたものの、着いていきなりこれだ。インドはやっぱりファンタジーしてるなあ。この調子だと、『犬も歩けば詐欺師に当たる』くらいは期待できそうだ。
しかしここで退き下がってはならんのだ。初体験とはいえ、インドの詐欺師にはなからやられたとあっては、自称ファンタジー作家としての僕のプライドが許さん。
「インタクの運チャンよ、大和魂見せてやるぜ!」
プリペイド乗車券持ち逃げにはまんまと引っ掛かった。その負けは潔く認めよう。だが……。僕は早速詐欺師タクシードライバーと料金の交渉を始めた。ところが向こうの言い値が目茶苦茶だ。まあ日本円にすればべらぼうに安いのだが、この時点での僕は、日本の安旅行者のバイブルとも言える某社『○○の○き方』なるガイドブックによる物価知識に頼っていたものだから、いきなり激しい言い合いになった。
「よう、運チャンよう、そんなべらぼうな値段があるかい! なめてんじゃねーよ」
という意味の英語もベンガル語もヒンドゥ語も知らないから、「ベリー・エクスペンシブ」とか「ノーノー」とかの応酬となったが、いつまでも退かないので時間の無駄だと思ったのだろう、インタクの詐欺師運チャンはとうとう値下げを始めた。だが簡単には値引きしない。こっちは行先をサダル・ストリート(外国人旅行者が集まるカルカッタの安宿街)と言ってあるのだが、
「空港近くのホテルにしないか? ずっといいのがあるよ」
と言ってくる。ホテルの値段を訊くと馬鹿高い。
「駄目駄目、サダル・ストリート!」
また値引き交渉になった。
「しょうがねーなあ。あんたには負けたよ」
運チャンは悔しそうな顔をしてとうとう運賃を値下げした。結局サダルに行かせることができた。これでvs.詐欺師戦一勝一敗、と胸を撫で下ろしたのだが、のちにカルカッタのタクシーの相場値を知った時、この時の料金は持ち逃げされた乗車券よりボられてたことがわかった。恐るべし、インタクの運チャン!
しかし簡単には目的地へ行ってくれないのがインドの運転手だ。
「サダルに今行っても部屋が空いてないよ。この近くにいいホテル知ってるから連れてくよ」
走っている途中で運チャンが振り返り振り返り、そわそわして言い始めた。おい、ちゃんと前向いて運転しろよな。料金が決まったとなると、なるべく早めに客を降ろそうとする。また僕の大和魂に火が点き始めた。しかし同乗している大畑さんは女性だし、もう時間が時間だ。
「じゃあ、とりあえずそこへ連れてってくれ」
「OK!」
やがてタクシーが停まった。運チャンはさっさと階段を上がって行った。二階にあるフロントで何か喋り始める。またボる気かと思って、慌てて僕は自分で値段交渉に入った。怪しげな泊まり客が部屋から出て来る。見るからに怪しげなホテルだ。ホテルと言っても、これ以降もそうだが、僕の泊まる所はみんないわゆる安宿のことだ。値段を聞くと、これもとんでもない。僕と大畑さんはさっさと階段を下りた。
「頼むからサダル・ストリートへ直行してくれないか」
僕は詐欺師運チャンに向かって言った。こんなことで時間潰してると、ほんとに泊まれなくなってしまうではないか。
「OK! OK!」
運チャンはタクシーを走らせた。道端に人がごろごろ転がっているのが見えた。事前に下調べしておいた話では、カルカッタの街には乞食と牛が路上に溢れ返っていて、それで日本人の旅行者などは本当の意味でのカルチャーショックを受け、発狂してしまう人もいるらしい。カルカッタは特にそれがひどく、『カルカッタ・ショック』という固有名詞まであるそうだ。だからガイドブックには、「初めてインドへ行く人はカルカッタからは入らずに、デリーかボンベイから入るべきだ」などとまことしやかに書かれてあったりする。
しかし僕にはこのカルカッタ・ショックなるものを少なからず期待していたところも確かにあった。だけど人は転がっているものの、牛はさっぱり見かけなかった。ちなみに日本に帰ってから正直に思った感想が、「ホテルが高いのを除けば、カルカッタが一番住み易そうな街じゃないか。ボンベイは物価が馬鹿高いし。どこがカルカッタ・ショックだ?」ということだったのだが。
少なくともインドに関する情報は古いものは役に立たないことが多い。数年前の情報であってもそうだ。特に物価の上がり方ははなはだしいから、ガイドブックを睨みながら値引き交渉していたら、すぐに喧嘩になってしまう。かっこよく言えば、『都市は生き物である』といったところだろうか。
「OK,サダル・ストリート!」
運チャンはタクシーを停めて言った。
「え、こんなとこ?」
周囲を見回してみると、街灯の灯りこそあるが、建物から光が一つも洩れていない。宿屋らしきものがないのだ。タクシーから降りてみたものの、僕と大畑さんは途方に暮れてしまった。運チャンはそんな僕たちの様子を見て、ニヤニヤしながら言った。
「空港の近くのホテルだったら部屋が空いてるよ。600ルピーだよ。(この時の1インドルピーは約3.5円)引き返そうか。あと150ルピー出せば乗っけてってやるよ」
ははん、詐欺師の手が読めた。わざと薄暗い場所に降ろしたのだ、きっと。消えかかっていた僕の大和魂にとうとう本格的に火が点いた。
「もうあんたには用はない。失せろ!」
僕はタクシーから荷物を降ろし始めた。それでもまだなんだかんだ詐欺タクシードライバーは言ってくる。
「こっからは歩いてホテルを捜す。どっか行け、詐欺師ヤロウ!」
僕は大畑さんのことも考えずに運転手に啖呵を切ってしまった。
そもそもインド旅行にはあらゆるグレードがある。『マハラジャ級』から『どん底級』まで、この国のカーストと同じく、様々なクラスの旅行ができるのだ。そこらじゅうに落ちてるゴミやうんこを気にせず、詐欺師に騙されても気づかず、伝染病の怖さを除くと、金さえ出せば、日本では決してできない快適で贅沢な旅行も可能だ。もっともそれだと「ほんとのインドを知ることはできないのだ」などとおっしゃるインド通の方もいらっしゃるにはいらっしゃるのだが。
ほんとのインドを知ることができようとできまいと、僕の場合はほとんど経済的な理由でグレードの選択の余地はあまりなかった。かと言って、体力的にも精神的にも、無銭旅行並みのどん底コースを選ぶ根性もないので、『梅の上』コースとも言うべきレベルで旅行した。それでも多くのインド人の目から見れば金持ちと見られてしまうのだが。
(註 : コースは上位から順に、『松の[特上]・[上]・[並]』・『竹の[上]・[中]・[並]』・『梅の[上]・[並]・[下]』の九段階となっている。いわゆる日本人の『安旅行』というのは、この『梅の上』及び『梅の並』を指すと考えてくれればいいであろう)
しかしこの時取った僕の行動が、日本人女性の大畑さんに、インドに着いた初日から野宿させてしまう羽目になろうとは……。今回二度目のインドだそうだが、大畑さんが『梅の上』で旅行する気でいるのかどうかはわからない。ほんとのインドを見るために、わざわざバックパッカーのなりをしているだけなのかもしれない。
「サダルのホテルはもうどこも開いてないよ。空港に引き返そうや。100ルピーに負けといてやるよ」
詐欺師運転手は、僕がリュックを背負ったのを見てさすがに慌てたようだった。僕は街灯の弱い光に腕時計を翳してみた。そして詐欺師運転手の方を振り返って言った。
「もう三時だ。もうすぐ夜が明けるじゃないか。ホテルがなけりゃこのまま起きとくさ」
タクシー代を詐欺師運転手に押し付けると、
「大畑さん! 行きましょう」
「は、はい」
大畑さんの荷物もタクシーから取り出した。
「三時じゃないよ。今十二時だよ。真夜中だ」
運転手はまだ言ってる。
「何言ってやがんだ。見ろ、三時じゃないか!」
そう言うと、詐欺師運転手の鼻先にこれ見よがしに腕時計を突きつけてやった。日本人は時計の一つも持ってないとでも思ってやがるのか! 『ジャパン』をなめるなよ!
「ふん!」
そうして歩き出そうとすると、
「それはシンガポール時間ね」
運転手が言った。
「ん?」
僕はまた腕時計を見た。
「インド時間は十二時ね。まだまだ夜は明けないよ」
待てよ、詐欺師のほざくこととはいえ、もしかするとそうかもしれないような気がなんとなく……。
僕は今日の出来事を思い返してみた。シンガポールに着いた時には確かに、乗り継ぎ便の時間を間違えないようにと時計を一時間戻した記憶はある。だが……、シンガポールとインドとの間には更に三時間時差がある。シンガポールの空港で時計を一時間戻した僕は、それから腕時計をいじっただろうか?
ガーン! その記憶は全くない。飛行機の中でしたことと言えば、狭い座席で肘をすぼめながら機内食を食ったことと、スチュワーデスに気取ってワインを要求したことと、あとはシートベルトをはめたり外したり、あとは怪しげなインド音楽をヘッドホンで聴きながら日本のバックパッカーのバイブルたる『○○の○き方・インド』をずっと眺めてただけだ。あとは……、ベンガル湾上の気象のせいか、ガタガタガタッと機体が揺れたり、ふわっと浮いたりストーンと沈んだりよくなったので、「墜ちるなよ、墜ちるな……」と心の中で必死に飛行機を叱咤激励していたくらいのものだ。あとは……
空港に到着した時はどうか? 到着した時はただ浮かれてただけ。そして空港を出ると詐欺師タクシードライバーとのトラブル。やはり三時間時計を戻した記憶がない。いや、考えるまでもなかった。
「十二時ですよ」
大畑さんがあっさりとそうのたまわれたのだ。ぐえぇ! 詐欺師運チャンの言ったことは嘘ではなかった。
「それシンガポール時間ね。インド時間まだ十二時だよ」
僕の動揺を見て取ったのか、詐欺師運チャンは九割方勝利を確信した笑みを浮かべながら、ここぞとばかりに同じ台詞でたたみかけてきた。これは相手の怪我してる所を繰り返し攻めるという、悪役レスラーのような攻撃だ。
だが、一旦本格的に火が点いてしまった僕の大和魂は、今更引き返すわけには絶対にいかないのだ。これは『インド人詐欺師vs.最大のカモ日本人旅行者』という、国と国との威信を懸けた、円が没落するまで果てしなく続くであろう飽くなき戦いのワン・ラウンドであるわけなのだから。
「ノー・プロブレムよ」
僕は詐欺師運チャンに向かって偽りの笑みをお返ししてやった。だが勝算がなかったわけではない。サダル・ストリートには安宿がたくさんある。一軒も開いてないわけがないじゃないか。こっちにはつよーい味方、『○○の○き方』という虎ノ巻があるんだぜ。細かい地図が付いてるし、そこには安ホテルの紹介もたくさん載っていた。ここがどこなのかもすぐに判明するであろう。
「歩いてこの辺りでホテルを捜すよ。大畑さん! 行きましょう」
僕は笑みを絶やさずに歩き出した。
「は、はい」
大畑さんは僕を信じきってくれているようで、すぐさまリュックを背負ってついて来てくれた。この隙一つ見せない、揺るぎないばかりのどっしりとした構えがインドでは常に肝要なのだ。
「バイバイ、おっちゃん」
「待て待て」
おっちゃんが後ろでわめいている。うろたえるんじゃねえ。見苦しいぞ、この負け犬めが。ははは、もう勝負は終わりだ。諦めろ、おっちゃん。それでもおっちゃんは僕を追いかけて来た。
「おいおい、待てよ。これ忘れ物だぞ」
「何言ってんだい!」
おっちゃんは僕の前まで来ると、片手で一冊の本らしき物を差し出した。
「あんた、タクシーの中に置き忘れてたよ」
街灯の薄明かりで見てみると、表紙には『○○の○き方・インド』と印刷されてあった。僕はおっちゃんの手から虎ノ巻を引ったくった。
「じゃあ、気をつけてな」
おっちゃんはタクシーの窓から顔を出して陽気にそう言うと、片手を振りながらたちまち走り去ってしまった。
3月19日 晴のち曇 カルカッタ
サダル・ストリートはどこだ? 僕と大畑さんが夜更けの街をうろうろしていると、道端に寝転がっていた乞食の一人が起き上がって近づいて来た。見るからにみすぼらしい恰好をしている。泥沼の底で洗濯したようなぼろぼろのシャツ(か何かわからんとにかく着ている物)とズボン(これは一応はいているということはわかった)に、ぼさぼさの髪の毛も顔もインド人だから黒いという黒さではなく、垢と埃をまぶして黒くしたような奴だった。
「サダル・ストリートはどこですか?」
大畑さんがその乞食に丁重に訊いた。乞食はついて来いという身振りでさっさと先に立って歩き出した。
「ホテルはありますか?」
大畑さんが歩きながら訊くと、
「ホテル?」
また身振りでついて来いとやった。
そうして何度か角を曲がってからやがて乞食は立ち止まった。
「ホテル!」
ガマガエルを踏みつぶしたような声で乞食は叫んだ。入口が閉まっている。小さな覗き窓みたいなのがあったから、そこから「泊めてくれ」と大声で叫んでいると、誰かが顔を出した。しばらくこっちの様子をじろじろ眺めてから、
「満員だ!」
吐き捨てるようにそう言って覗き窓をピシャリと閉じてしまった。
乞食は手を出している。何かくれと言っているみたいだ。なんだ、親切でしてくれたんじゃないのか。まあ、こういう時のために行きつけのタバコ屋から使い捨てライターをたくさんもらって来ていたので、一つ取り出して握らせてやった。乞食はライターを受け取るとポケット(らしき所)に押し込んでから、また手を出した。
「マネー、マネー」
またガマガエルの声で怒ったように言っている。
「マネーって、ホテル空いてないじゃないの」
大畑さんは不満げに日本語で文句を言った。
「マネー、マネー」
乞食は全然動じない。
「インド人は何でも金取りやがるなあ」
しょうがない。
「いくら?」
「10ルピー」
僕は10ルピー札を捜し出すと、この泥沼から這い上がって来たような乞食にくれてやった。ガマガエルはゲコゲコと喜びの鳴き声を上げるわけでもなく、とっとと暗闇の中に消えて行った。またあとでわかったことだが、日本円で約35円とはいえ、10ルピーも乞食にやる必要はなかったのだ。百円ライターなど、30ルピー近い値段になるわけだし。
「空いてないですねえ」
いくつもホテルを回っても、どこでも「満室!」で門前払いを食らわされた僕と大畑さんはもう疲れきっていた。
「タクシーの運チャンの勧める600ルピーのホテルに泊まっとくべきだったかなあ」
僕は弱気になった。しかしオールナイトの喫茶店みたいな夜明かしできる店もどこにもなさそうだ。僕は実は野宿の経験はかなり豊富なので、どこでも寝られるし(日本の墓地で寝たことだってある。もっとも朝目覚めてからそこが墓地だと初めて気がついたのだが)、ここは夜でもあったかいから、一人なら面倒になってその辺の路上生活者の隣で寝たと思うけど、女性の大畑さんに勧められるわけがない。どうしていいかわからなくなると、急に尿意を催した。
「ちょっと失礼します」
僕は路地裏へ行き、黒い壁に向けて小便を飛ばした。すると隣に誰かやって来て、やはり立ちしょんを始めた。大畑さんは女性なのに立ちしょんができるのか? インドに一人で来るくらいだから、只者ではない凄い女傑なのかもしれないが、でもまさか……、女性に立ちしょんなどできるのだろうか? 子供の頃、いとこの女の子が「立ちしょん見せてやる」と言って、脚からパンツからびしょびしょに濡らしていた場面を思い出した。やはり無理だろう。大畑さんはもしかして男だったのか?
すると、
「ホテルどこも空いてないよ」
隣の立ちしょんが紛れもない日本人男性の声で話しかけてきた。やはり大畑さんが女立ちしょんをしていたのではなかった。
「こっちもさっぱりです」
スッキリしてからそう言うと、僕はまた明るい所に戻った。少しすると謎の立ちしょん日本人も路地裏から出て来て、姿を見ることができた。さっきの図々しい乞食には敵わないものの、それでも泥酔してどぶ川に転落して這い上がって来たくらいのよれよれのなりをしている。気がつくと、同じようにくたびれたなりをした日本人の若者らしき男性があと二人、知らぬ間に僕の背後に忍び寄って来ていた。女傑大畑さんも近くにいた。
「今バングラから着いたところで」
立ちしょん日本人は言った。
「ああ、そうですか。こっちは今日本から着いたばかりです」
「いい寝場所見つけたよ」
そう言うと、立ちしょん小僧とその配下の忍び二人は先に立って歩き出した。僕と大畑さんは黙ってついて行った。
少し行くと安宿らしき前でどぶ川トリオは立ち止まり、そのペンキの剥げたトタン張りの門扉を押した。
「ここ」
どぶ川トリオは疲れ果てたように地べたに腰を下ろすと、途端に煙草を吸ったり水をがぶ飲みしたりしだした。見ると、屋根もないし、下はコンクリート、その宿のものか客のものだろう車が一台停めてあるだけ。すぐそこの建物には灯りは見えた。
「ここはマリア・ホテル。部屋空いてないって」
立ちしょん小僧が言った。忍びの一人がまたトタン張りの門扉を閉めに行った。
「だけどここホテルの敷地だろ? 勝手に寝ていいのかな?」
僕が訊くと、
「いい、いい」
小便小僧は荷物を枕にしてさっさと寝転がった。まあ、扉があるだけましか。そう思うと、僕も荷物を枕にして、硬いコンクリートの上に横になった。だけどやはり大畑さんのことは気がかりだ。大畑さんは笑顔をふりまいてみんなと話してはいたのだが。僕と一緒にタクシーに乗らなければ、ホテルのベッドですやすやと寝られただろうに。着いていきなりどん底コースか。悪いことしたなあと思いながらも、僕はいつの間にか眠り込んでしまった。昨夜も送別とか言って、小町や凶山たちにオールナイトのカラオケに連れて行かれて寝てなかったのだ。
目が醒めると大畑さんはもう起きていて(もしかすると寝なかったのかもしれない)、時計を見ると(もうちゃんとインド時間にしてある)、四時頃だった。
「あのバングラデッシュから来た人たちは?」
大畑さんに訊くと、
「もう起きて行きましたよ」
話していると、ホテルの人が出て来て、何か言っている。
「グッド・モーニング」
と二人が言うと、ホテルの人は、
「ここで寝たのか?」
と訊くので、
「そうだ」
と答えたが、別に追い出そうとするわけでもなく、かと言って中に入れてくれるわけでもなく、ニコニコしながらまた建物の中に戻ってしまった。
明るくなってくると、荷物を背負って大畑さんと街を歩き始めた。カルカッタは大都市なのだが、いやに静かで気味が悪いくらいだった。たまに道を箒で掃いているおばさんを見かけたが、そこにはあらゆるゴミの山ができていた。
やがてカルカッタ公園に出くわしたので、そこを散歩した。朝早く沐浴しているインド人たちがたくさんいた。水はとても汚ない。インド人には朝外で沐浴する習慣があるみたいだが、水さえ溜まっていれば、それがどんなに汚れていようとどこでも平気で水浴びしているような感じだった。
しばらく歩いて行くと、売店みたいなのが開いていたので、そこで一休みすることにした。男の子の店員がいたので、テーブルに着いて飲み物を注文したけど、英語が全く通じない(僕の発音がまずいのだろうか?)。僕と大畑さんは虎ノ巻を取り出すと、それを見ながら、「エーク(ヒンドゥ語の1)・ペプシ」とか、「エーク・リムカ」とか言ったが、ボーイはニコニコしながらこっちを見ているだけだ。指を一本立てて言ったりしてみたのだが、まるで通じていないようだ。
「なんで通じないんだろうねえ」
「発音が悪いんでしょうか?」
などと言い合って、またいろんなイントネーションで、「エ・イ・ク」「エーック」「エークッ」「エエエエック」「エークゥ!」などと言って試してみたが、男の子は相変わらずニコニコしているだけ。
「うーん……」
コーラ持って来るだけのことじゃないかよ! としまいにはイライラしてきた。すると、あとからやって来て、椅子に座って新聞を読んでいたおじさんが、
「ここではヒンドゥ語は通じないよ。ここはベンガル語だ」
と英語で言ってきたので、「そうなのかあ」と初めてわかった。
「数字も全然違うんだよ」
そう言うと、おじさんはボーイに何かペラペラと喋った。ボーイはサッと飛んでって、すぐにコーラとリムカ(インドの清涼飲料水の一つ)の瓶を持って来るや、目の前で栓を勢いよくスポスポッ!と抜いてみせた。それに素早くストローを突き刺す。笑顔は絶やさない。坊やにもおじさんにも、
「サンキュー」
と言うと、
「ヒンディ、ナマステー、ベンガリー、ナマスカール……」
おじさんは調子に乗って、受講者のいないベンガル語講座をいつまでも続けていた。
休憩が済むと、まだ一人でヒンドゥ語とベンガル語の比較論をやっている大先生を適当にあしらって、僕たちはサダル・ストリートの方へ引き返し始めた。荷物を背負っての歩きはきついし、またホテルにあぶれるとまずいので、朝のうちに部屋を取っておこうと思ったのだ。
フーグリ河沿いに線路が通っていて、それに沿って歩いて行くと、駅のホームに人が何人も寝ているのが見えたが、生きているのか死んでいるのかわからないような印象を受けた。もしかして死体置き場なのではなかろうか、なんて気もしてきたりした。
午前九時ごろになっていたが、大通りは既に車で溢れ返っていた。サダル・ストリートもいろんな人種でごった返していた。今朝までとはまるで全く別の場所に来たみたいだ。安宿を何軒か回ってみたが、部屋を取ろうと既に待ち状態になっている。部屋代も虎ノ巻に載っている値段とはかなり開きがあった。
「高いなあ」
とホテルの人に言うと、
「首相がカルカッタに来たからだ」
とちっとも理由になってない。
「虎ノ巻め、嘘ばっかし書きやがって」
と大畑さんと文句を言ってたら、道端に寝転がってたじいちゃんが急に起き上がり、
「ホテル?」
と来たもんだから、
「そうだ」
と答えると、じいちゃんはついて来いとばかりにさっさと歩き始めた。じいちゃんはキャピタル・ホテルという所に入って行った。フロントで訊くと、300ルピーということだった。もう安宿捜すの疲れたし、僕は『梅の上』コースでいいものだから、
「ここでいいですか?」
と恐る恐る大畑さんにお伺いを立ててみると、
「また部屋がなくなると困るし」
ということで、ここに泊まることにした。話が決まるとじいちゃんは嬉しそうに去って行った。地面に転がってたが、結局客引きだったわけだ。
ブルー・スカイ・カフェという、これもガイドブックで紹介されてて外国人客ばかりがいる喫茶店で軽く朝めしを食っていると、外から笛の音が聞こえてきた。従業員用の戸の隙間から外を見た時、笛を吹いているおじさんと目が合った。おじさんは笛を吹きながらニヤリと笑った。こっちもニコッと笑ってみせたが、あとはそのまま知らん顔して食事した。
ワンパターンのメロディが繰り返し繰り返し聞こえてくる。外へ出ると笛吹き男が僕を待ってくれていた。待ってくれてなくたっていいのに……。そんでまたあのメロディだ。
「買わないか」
と言う。
「いらない」
と言っても、おじさんはまたご機嫌になって売り物の笛を吹き始める。そんでまた、
「買わないか?」
「売りたいんだったらまず自分の笛の腕前上げなよ」とアドバイスしそうになったが、もちろん言わなかった。
ところがそこを離れてチョーロンギー通り(カルカッタの大通り)の方へ向かってふらふら歩いていると、前方からまたあの陽気でへたくそな笛の音が聞こえてくるではないか。笛を吹きやめた笛吹き童子は、いや、どこをどう先回りしたのか謎だが、笛吹き童子ではなく、紛れもないあの笛吹きおやじだった。地理を知らない外国人旅行者の行先などお見通しのようだ。(恐るべしインドの物売り!)
笛吹きおやじは得意のスマイルで、
「買わないか?」
と笛を差し出した。
「ノー・サンキュー」
僕もスマイルでかつての笛吹き童子とさよならした。これを聞いて、しつこい物売りだと思えるかもしれないが、のちに僕が他の観光地で出くわす羽目になるメタメタな物売り軍団に比べれば、このおやじはとてつもないジェントルマンなのであった。むしろこの程度のしつこさが旅行者にとっては旅にアクセントをつけてくれる良きイベントなのである。
のちに他の土地で不愉快な物売りどもに出くわした時、僕はその度にこのサダル・ストリートの陽気でへたくそな笛吹きおやじを思い出さずにはいられなかった。
「ああ、カルカッタの笛のおっさんよ、わたしゃあんたに、も一度逢いたいよ。も一度あのへたっぴの笛を聴かせてくれや」
午過ぎにホテルに戻ると、さっそく従業員がやって来て、
「ランチはどうだ」
と言う。そうだな、じゃあそろそろインド・カレーを食ってみるとするか。なんやらカレーとかダル(インドのみそ汁みたいなもの)を頼むと部屋まで持って来てくれた。カレーはやはりカレーには違いなかったが、僕が長年憧れていた食品、『チャパティ』は、これは期待を大きく裏切る味気ない代物だった。味気ないと言うより、味そのものがなかった。
高校生の時、友人に借りて読んだ北杜夫の『どくとるマンボウ』ものの中にこの『チャパティ』が出て来て、「俺は死ぬまでに必ずチャパティを食ってやる!」とその時密かに心に一生の誓いを立てたのだが、なんだこれは! 冷凍ピザの土台じゃないか! おまけに『ダル』が、これがまたとんでもない。まるで胡椒と唐辛子の濃縮果汁100%ミックスジュースみたいなもので、空しさと共に口の中をひーひーさせながら僕はホテルの出口まで行くと、
「リムカ! 一番冷たいやつ!」
ホテルの従業員に食ってかかるようにそう言うと、手渡されたリムカを一気に飲み干した。
夕方には地下鉄に乗ってカーリー寺院へ行ってみた。『カーリー』というのはヒンズー教の神様の一人だそうだ。寺院自体は大したことなかったのだが、この界隈は門前町&下町といった雰囲気で、とても気に入った。
寺院に入ると、勝手に案内を始めるインド人がいた。非常に聞き取り易い綺麗な英語で(たいていのインド人の英語は訛りがきつくて聞き取りにくい。と言っても、日本人の英語だってかなり訛ってるには違いなかろうが)次々と寺の中を案内しては説明してくれる。
それで最終的には案の定、金を要求してきた。「チャリティだ」とか言って(一体誰にチャリティするんだ? あんただろが)ノートを開いた。サインがずらずらと並んでいて、そのあとに寄付金額が『400ルピー』とか『300ルピー』とかばかりずらずらと書き込まれている。僕は詐欺師ガイドを無視して池を眺めていた。大畑さんは迷っている様子だ。
「やる必要なんかないですよ」
僕はそっぽを向いたまま日本語で言った。
「うーん、でも……。じゃあ10ルピーくらいあげときましょうか?」
(おや?)僕は意外に思った。大畑さんも『梅の上』コースだったのか。10ルピーだと昨夜の忌々しい乞食にくれてやったのと同額ではないか。この詐欺師ガイドは頼まれてもいないとはいえ、あのガマガエルよりは遥かに働いたはずだ。
大畑さんは10ルピー札をガイドに手渡した。詐欺師ガイドはそれでも自分の額に10ルピー札をあてがい(これがインド人の感謝のポーズ)、丁重に僕たちを見送ってくれた。それでも僕は手口が気に入らなかったのでビタ一文出さなかった。
帰りは街を見物しながらぶらぶら歩いて戻ろうとした。暑いので途中でサンダルを買って履き替えたが、「負けろ、負けろ」としつこく値切ってみたものの、あまり負けてもらえなかった。
夜のカルカッタの街はどこまで行っても人と車と犬で溢れ返っていた。電気が乏しくて暗いのだが、特別な日でもあるまいに、ここは毎日がお祭なのか? しかしサンダルの革が硬くて、歩いているうちに靴擦れになってしまい、途中から地下鉄に乗ってしまった。
チャパティとダルにぶちのめされた僕と大畑さんは、晩めしは早くも中華料理屋へ行って食べることとなってしまった。『香港』という名前の、どう見ても中国料理店だ。そこでヤキソバ(インド名チョーミン)と餃子と、あと何か食った。ヤキソバは細く、餃子はやけに皮が厚かった。これがチベット料理の『モモ』というやつか? もぐもぐ……
食事していると、大畑さんがある時ぽつっと言った。
「伊井田さん(僕のこと)が一緒にタクシーに乗ってくれてなかったら、もぐもぐ……私きっと高いホテルにそのまま泊まってました。ありがとうございました。もぐもぐ……」
そう言われて僕はほっとすると共に、女傑大畑さんも実は『梅の上』コースだったのだということがやっとはっきりした。
僕の綿密な計画表によれば、翌日はもうカルカッタを離れることになっていた。カルカッタは気に入ったのだが、半島を一周してもう一度戻って来るはずだから、その時ゆっくりする予定にしていたからだ。なのだけれど……。
3月20日 晴 カルカッタ
日本人女性大畑さんは、『梅の上』ではなく、『梅の並』であることが判明した。
朝チェックアウトしてもっと安い宿をと言うことで、サルベーション・アーミー(救世軍という意味らしい)という、四大都市にある、まさに貧乏旅行者のための代表的安宿へ行ってみた。従業員は兵隊みたいな制服を着ていてちょっとイカついが、値段を聞くと、他より遥かに安い。大畑さんはその中でも更に一番安いドミトリー(大部屋)を取った。僕は今晩発つつもりでいたのでそのまま出たが、昨日は損をした気分だった。
荷物を背負ったまま鉄道予約事務所まで行ったが、インド人で混雑している所に並んでいると、ある人が、
「外国人はあっちの階段を上がった二階ですぐに予約できるよ」
と親切にも教えてくれた。行ってみるとその通り、西洋人と日本人が何人かいて、椅子に掛けて待っているだけだった。切符売りの駅員に、夜行でガヤーへ行きたいのだと言うと、夜行は翌々日まで満席だと言う。
「えー」
なんて交通事情の悪さだ。
「明日の昼なら席が空いてるけど」
切符売り場の駅員が言った。宿泊費を浮かすために夜行にしようと思ったのだが、仕方がない。
「じゃあそれ」
朝にキャピタル・ホテルのあんちゃんから、
「300ルピーでガヤー行き夜行の切符取って来てやるぜ、どうだ?」
と言われたのだが、この切符だと147ルピーだったので、やはりこっちにすることにした。
カルカッタでもう一泊しなければならないと決まったからにはぐずぐずしてはいられないのだが、僕はついて来てくれていた大畑さんと一緒にフーグリー河畔へ行って一休みした。川はほんとに水が汚なかった。
木陰で話をしていると、ふと頭上の枝にでかい木の実が成っているのに気づいた。いや、木の実と呼ぶにはあまりにも巨大だったし、この木の実はぶら下がっているのではなく、下から上へと成っていた。もちろんいくらインドが不思議な国とは言っても、そんな木の実があるはずもない。
それは馬鹿でかい鳥たちだった。更にはそれがハゲタカだとわかった。『ハゲタカが木の枝にたわわに成っている!』僕も大畑さんもギョッとして思わず後ずさりしていた。
「な、な、なんなんだ、おまえらは、なんでこんなとこにいるんだ?」
僕の脳神経細胞は激しく『ハゲタカ』の項目を検索しようとしていた。すぐに検出された(ハゲタカについての知識に乏しいもんで)データを元に、僕は大畑さんを安心させようとして言った。
「だ、だいじょぶですよ……、た、たぶん……」
ハゲタカは死肉を食うはずだ。テレビの動物番組などでも、生きた獲物を追っかけている場面を見た記憶がない。別名『草原の掃除屋』。つまり僕と大畑さんなら、死んだらこいつらに襲われるかもしれないが、生きている限りこいつらに殺されはしないだろう。つまり、『死なない限り死にはしない』のだ。『ハゲタカのような奴』という、人を形容する言い回しを聞いたことがあるが、あれはたぶん、『前頭部が禿げている人』という意味ではなく、『腐りかけのお肉が好物な人』という意味なのであろう、恐らく。少なくとも今はそういうことにしておこう。
それでも大畑さんは気味悪がった。僕にしたって同じだが、それにしてもハゲタカを間近に見てこんなに恐怖するとは……。子供の頃、動物園で見た覚えはあるが、お友達にしか思えなかった。間に金網があるかないかでこんなにもハゲタカを見る目が変わるものだとは!
驚愕の余り、その時数えてはいなかったが、とにかく一本の木に二十〜三十羽は止まっていた。おまけにどいつもこいつも馬鹿にでかく見えて仕方がない。ハゲタカたちは休憩中なのかおとなしくしていたが、とにかく迫力があった。
しかし近くにいるインド人たちは、ハゲタカなど気にも留めていない様子だ。やはり日本人は野生動物に対して慣れていないなあ。冒険者としてのレベル、ダウン。『日本人観光客、インドでハゲタカに襲われ死亡!』そんな見出しが日本の新聞に出ないことを祈りながら、僕と大畑さんはそろそろとハゲタカの成る木から離れた。
またホテルにあぶれてはまずい! ハゲタカに怖じ気づいたわけでは決してないのだが、僕は重い荷物を背負って、手ぶらの大畑さんと共にサダル・ストリートへと引き返し始めた。それでも途中で大畑さんが何とかという(名称は忘れた)インド製のクラシック・カーまがいのポンコツ車と記念撮影がしたいとかのたまうので、写真を撮ったりして寄り道しながらサルベーション・アーミーまで引き返して来た。
幸いなことに、部屋はまだ空いていた。ダブルルームだが、90ルピーと、カルカッタにしては安い。部屋はもちろん良くはないが、悪くもなかった。重荷から解放された僕は、大畑さんと共に再びカルカッタ見物へと街に繰り出した。
ニュー・マーケットという大衆向けの市場(別に値段が安いとは思わなかったが)へ行ってみたが、入口で案内係と称する男が現れ、広い市場の中を連れ回してくれた。(いい迷惑だ)
ともすると高い土産物屋へ連れて行きたがるし、サリーを買わないかと言ってうるさい。途中で案内係が交代した。最初から何も買うつもりもなかったが、結局は何も買わなかったし、二人の案内係にリードされて市場の中を連れ回されただけだった。それでもそれなりに面白かった。しかしインドは人手が余りまくっているようで、自分勝手に職種を作っては勝手に始めてしまうところが楽しい。楽しいけど、時には迷惑でもある。
それにしてもこのマーケットの中は店が所狭しと並んでいて、通路もさほど広くはないのだが、金を持った買物客を当てにしているのか、物乞いがやたらに多い。赤ん坊を抱いた女の子、片手のない男、手が捻じ曲がった男、くしゃくしゃの老婆、次から次へと近づいて来ては手を差し出してくる。乞食は相手にしないつもりでいたのだが、マーケットを出た時にはとうとう根負けしてしまい、外にいた赤ん坊を抱いた若い女に1ルピーやった。たった1ルピーでも女は大層喜んだ。あの満室のホテルへと案内したふてぶてしい泥塗れの乞食とは大違いだ。
ところがそれを見てどこから現れたのか、髯もじゃの爺さんがいつの間にか寄って来た。インドを旅してて常に不思議に思ったことは、金の臭いを少しでもさせると、それまで周囲に影一つ見かけなかった乞食か物売りか詐欺師のどれかが、必ずと言っていいほど出現するということだ。奴らは一体どこに隠れているのか? もしかすると忍者が変装していて、地遁の術でも身に着けているのだろうか?
乞食にも金の要求の仕方に様々なスタイルがある。この爺さんは、『陽気な乞食』タイプだ。金物の皿を片手に、棒切れでガラガラ叩きながら、
「バクシーシ(喜捨)!」
とだみ声でわめく。めんどくさいからこのじじいの皿にも1ルピー硬貨を放り込んだ。爺さんは顔をほころばせ、その1ルピー硬貨を皿の中で回してカラカラと鳴らしてみせた。
ついでにこの乞食二人と並んで記念撮影していたら、たちまち周囲に人が集まって来て見物を始めた。そんなに写真が面白いのか? しかしモデルの乞食も見物の野次馬も急になごやかな雰囲気になった。
「ははあ、インド人と友好を結ぶには写真かあ」
名もない小さな店でラッシー(インドのヨーグルト・ドリンク)とアイスコーヒーを飲んだ。これがこってりしててとても美味かった。そうしてまた歩いていると、汚ならしい女の子が赤ん坊を抱いて物乞いに寄って来た。めんどくさいからすぐに小銭をやった。だがこの子がわざわざ友達を呼んで来た。呼ぶなっつうの。また面倒だから、最後に残ってた小銭をやった。
ところが少し歩いていると、あとの方の女の子が追っかけて来て、何か頻りにわめき始めた。赤ん坊を抱いたお友達を指差し、自分の手にした硬貨を指し示し、何か抗議しているような感じだ。言葉はわからないが、見るとそれが80パイサ(100パイサが1ルピー)だったので、どうやら「不公平じゃないか」と言いたいみたいだ。
「もう小銭ないよ」
と言ってみたが、そんなことは通じない。「ノー・ノー」と言ってもさっぱりお構いなしで抗議を続ける。
この小さな抗議者に辟易としていると、やがて人力車が停まった。ガリガリに痩せこけた爺さんが乗らないかと言っている。
「いくら?」
「10ルピー」
渡りに船だ。人力車はカルカッタにしかないらしいので、大畑さんも記念に乗りたいと言った。
「じゃあ乗ろう」
すると爺さんは乞食の女の子を一喝した。じじいのせいで20パイサもらい損ねた可哀そうな女の子は黙って去って行った。
爺さんはあたかも骨と皮だけのようなスリムな脚で踏ん張りながら、贅沢日本人二人を乗せた人力車をゆるゆると曳き始めた。炎天下の重労働に瞬く間に汗みずくになり、車を曳きながら何度も首にぶら下げたタオルで汗を拭う。後ろに座っている僕は見ていられなくなった。大畑さんも、「かわいそう、かわいそう」を連発した。じゃあ俺たちなんで乗ってんだ?
昔、明治の頃、西洋から来た偉い人が、役所へ行く迎えに人力車がやって来て(インドでリクシャーと呼ぶが、日本の『人力車』が語源だそうだ)これにお乗り下さいと言われると、途端に、「この国では人間を馬車馬代わりにしているのかっ!」と怒り出し、人力車には乗らずに歩いて行ったという話を何かで読んだことがあるが、その話を思い出した。
この偉い西洋人はやはり異文化を理解しようとしない石頭だとは思うものの、こうやって実際に自分が人力車にのほほんと座っていて、それを痩せ細った老人が関節を今にも折れそうにきしませながら、汗をだらだらと流して悪戦苦闘しつつ引っ張って行く。それを目の当たりにしていると、僕も大畑さんもたちまちいたたまれない気持ちになってしまったのだった。
そうしているうちにすぐに人力車は停まった。
「着いた」
ひょろひょろの爺さんはクビキを下ろすとまた汗を拭った。サダル・ストリートは狭いし、リクシャーが活動していい範囲は限られている。しかし高々200メートル進んだか進まないかという程度だった。それでも僕と大畑さんはこれ以上乗りたくなかったものだから、すぐに人力車から降りた。
「20ルピー」
車夫の爺さんが料金を請求してきた。
「えっ、10ルピーだろ?」
僕が言うと、爺さんは僕と大畑さんを交互に指差しながら、
「10ルピー、10ルピー、20ルピー」
と言った。なるほどね。一人につき10ルピーってわけか。それも理屈だ。仕方なく僕と大畑さんは10ルピー札をそれぞれ車夫のじじいに手渡した。じじいは金を手にすると、すぐにまた近くを歩いていた外国人観光客に声をかけ始めた。
「まんまとしてやられたね」
「歩いた方がましじゃない」
僕と大畑さんは既に新たな客をカモろうとしている憎たらしいじじいの背中に言葉を投げつけた。先程の憐れな車曳きに対する車上での同情の念など、どこかへ吹き飛んでいた。
「クソじじいめ!」
そしてお次は大通りの歩道を歩いていて、物乞いの極めつけに出会った。そいつは何のことはない、年端もいかぬ男の子だったのだが、この子がほんとか嘘か、両足では歩けない。
ところがそばまで行った時、尻を地面に着いて両足を前方に放り出したままの姿勢で、両手だけを使ってまるでカニのように僕の前にしゃしゃり出て来た。当然僕はよけて通ろうとした。ところがサササッとカニさん歩きで僕の前を塞ぐ。またよけようとしたが、またもやサササーッと得意のカニさん歩きで前方を塞がれてしまった。
それならば、と僕は小学生の時に日本で習い覚えた反復横飛びという高度な技を用いてこのカニ小僧を交わしてやろうと試みた。だがこの恐るべきカニ小僧、両手だけで後ずさりしながらも右へ左へとブロックを繰り返し、僕の前方には決してスペースを作らせてはくれない。その神業に、僕はただただ呆れ返ってしまった。
カニ小僧は更に満面に浮かべた笑みを決して崩そうとはしない。うーむ、これならこのままでもバスケット、サッカー、ラグビー、アメフトなどのディフェンスとして充分通用することだろう。
ところが僕が途方に暮れていると、間もなく通りがかりのおじさんの一人がこのインド代表名ディフェンダーに一喝を食らわした。天敵のタコに睨まれたカニが岩陰へと逃げ隠れるかの如く、カニ小僧はサササッと歩道の脇へ退き、道を空けた。
それでもこの救いのタコおじさんはカニ小僧をしつこいまでに怒鳴りつけていた。きっと、「そんな国辱的なみっともない真似さらすな!」とでも言ってるのだろう。その通りだ。こんな貧乏日本人を相手にせずに、金持ちインド人の行く手を塞げってんだ! それでもカニ小僧には応えた様子もまるでなく、腹の中ではこのタコおやじめとでも思っているのか、ただニタニタ笑っているのだった。
昨日は一日がやたらに長く感じられたが、今日はやけに短い。大畑さんがマザー・ハウスへ行きたいと言い出した。大畑さんは看護婦志望なのだそうだが、そう言えば、このカルカッタはかの聖女マザー・テレサの根拠地でもある。
僕はナルシストなせいか、人とそんな話になると、口では「素晴らしいことだ」などともっともらしいこと言いながら、実はボランティアには全くと言っていいほど興味がないし、ボランティア活動全てを素晴らしいことだなんて決して思ってはいない。
僕のことに限って言えば、自分一人の面倒さえろくに見ることができないのに、ましてや他人に献身するなどできるはずがないことを自分なりによく知っているつもりだ。それどころか、自分ができもしないのにこんなことを言っては悪いのだが、ある種のボランティア活動などは、僕にとっては鼻につくことさえある。
それにしてもマザー・テレサと言えば、テレビで見て知っているだけだが、こんな利己的な僕でさえ、『聖女の中の聖女』、『二十世紀の奇跡的人物』、『女神のこの世での現身』とでも呼びたくなる、無条件に別格の存在なのであった。だが残念なことに、日本を発つ前に、『マザー・テレサ病臥中、危篤』というニュースは僕の耳にも入っていた。
たった今思いついて病臥中のマザテレに会いに行くなどとははなはだおこがましいことである。それでも偉大なる『神の愛の宣教者会』のごく一部なりとも見せてもらおうという気になり、ここは大畑さんにお任せすることにした。
とりあえず虎ノ巻の地図を見てみると、『マザー・ハウス』とあって、ここからさほど遠くもなさそうだ。大畑さんと僕はその方角に向かって裏道を歩いて行った。途中で向こうからやって来た日本人の大学生くらいの女の子が、
「サダル・ストリートへはどう行けばいいんですか?」
と道を尋ねてきた。
「だいたいあちっに行けば辿り着きますよ」
と不親切な道案内をしてしまったが、恐らくこの人もマザー・ハウスへ行った帰りなのだろう。これだけの些細なことでも、その昔カトリック教会の掟を破ってヨーロッパの修道院を抜け、カルカッタの巨大なスラムへと無一物で乗り込み、たった一人で奉仕活動を始めた『聖なる背教者』の、全世界への影響力の凄さを知らされる思いだった。
たぶんここじゃないかと、入口か勝手口かわからない所でわいわい言っていると、守衛が出て来たので、
「見学させてくれ」
と言うと、守衛は最初、なんだかんだ言って渋っている様子だった。
「あっ、そ」
潔い態度が取り柄の僕はあっさり諦めようとしたが、それでも諦めの悪い大畑さんが熱心にお願いし続けると、
「まあ、いいでしょう」
と敷地の中に入れてくれた。しぶとく食い下がってみるもんだなあ。
『死を待つ者の家』は有名なのだが、ここはそうではなくて孤児院だった。一旦見学を許されると、きっちりと案内までしてくれる。今度は案内人がついた。
途中には孤児院の仕事をしている少年少女や老人までいたが、やはりここで育った孤児たちなのだろうか、僕たちに気づいた時の接し方が、愛想がいいとか無愛想だとかそんなのではなくて、何か、『汚れなく育った無垢な』とでもいう形容をしたくなる印象ばかりを受けた。
サンダルを脱いで建物の中に入ると、赤子ばかりがベビーベッドに寝かされていた。今度は部屋の中にいたシスターが説明してくれた。乳飲み子だけでも166人もいるそうだ。大畑さんは既に水を得た魚のようになり、満面笑顔で乳飲み子をあやして回った。僕はすることがないので、
「赤ちゃんを写真に撮ってもいいですか?」
とシスターに訊いてみたが、やはりあっさりと断られてしまった。
三十代くらいの身なりのいいインド人夫婦がそこにいて、シスターと話していた。それとなく聴いていると、子供がいないので養子が欲しいらしく、ここに見つけに来ているということだった。
更には、これまた見ただけで上流階級だとわかる大学生らしきインド美人の女の子がいて、この休み中にここで奉仕するということで、シスターから説明を受けていた。
みんな立派なボランティア精神を持ってここに来ているというのに、僕だけ野次馬だ。たちまちこの場に居辛くなってしまった。することもなく気詰まりになって、僕は一人で隣の部屋へと避難した。ここにはもう少し大きくなって乳離れした赤ん坊たちがいた。
「さて、ここで何をしよう?」
「飛び入りとはいえ、一つボランティアでもしてみるか」
僕は動物園に来たような感覚で赤ん坊を見て回った。しかし赤ん坊の世話とは一体何をすればいいのか? とりあえず宙に小さな掌を放り出している赤ん坊を見つけたので、そのちっちゃな手と握手してみた。すっぽりと僕の手に包まれてしまうほどその手は小さかったが、この柔らかくて、力を入れるとぶちゅっと潰れてしまいそうな手を握ると、今度はあのぶよぶよしたほっぺをつねってみたくなった。
「果たしてつねってもいいものだろうか?」
「泣き出すだろうか?」
と良からぬ企みをしていると、先程のお嬢様聖女子大生がこっちの部屋にやって来たので、僕は何食わぬ顔をして更に隣の部屋へと移動した。
そこはもうちょっと大きくなった一歳児くらいの部屋だった。こっちの方が子供に個性が現れてきていてまだ面白い。
「さあ、何をしようか? 大畑さん早く済ませてくれないかなあ」
と思いながら、子供を見物していると、一人だけ黄色人種の子供がいて(たぶんチベット難民の捨て子だろう)、この子がうつ伏せに寝たまま首だけを垂直に立てて僕の顔をじいーっと見ていた。
「ガキのくせにこの俺にガンつけやがって!」
僕はお返しにその子を睨み返したり、笑ってみせたり、日本風にベロベロバーをしてみせたりした。しかしその子はやはりつぶらな瞳で僕の顔をじいーっと見ているだけだ。
「首の骨がよく折れないもんだなあ。いや、もしかして折れていて元に戻らないのかな? 試しにちょっと首を引っ張ってみるか」
そんなことを考えてみたが、この東洋系赤ん坊は相変わらず僕の顔を見つめるばかりだ。
「俺の顔になんかついてるのか?」
「そんなにこの顔が面白いかねえ」
「俺に一目惚れしたって無駄だぜ、お嬢ちゃん」
「そんなに見つめられると照れちゃうよ」
いろいろ日本語で言ってみたが、やはりこの子は首90°の体勢のままじぃーっと僕の顔を見つめ続けている。
「よーし、こうなったらとことんやったろうじゃねーか!」
とうとう日本代表の僕とチベット代表一歳児とのにらめっこ一本勝負が幕を切って落とされた。
しかし僕は赤ん坊パワーの凄まじさを思い知らされただけだった。この時は暇を持て余していたこともあって、そうとう気合入れて挑んだつもりだった。五分はにらめっこが続いたと思う。だがこの子はびくともしなかった。相変わらず首90°、心は無心無我の境地。大畑さんがやって来て、
「何してるんですか。そろそろ行きましょう」
と来てくれなかったら、そのうち僕はこの未来のヨガ的美女の視線に射抜かれ、硬直して鼻血を噴いてその場で卒倒していたかもしれない。
「いえ、そうですね。そろそろ行きますか」
僕とチベット幼女の束の間の見つめ合う恋は儚くも終わってしまった。ところが、
「バイバイ、ちっちゃな別嬪さん」
とチベットの恋人の方を再び見ると、まだ首90°、あの魅惑の瞳で僕を見つめたままでいたものだから、運命の出逢いをビビッと感じたとでも言うか、僕はむしろこの小さな恋人から離れ難くなってしまった。
あのインド人夫婦くらい裕福で、日本に厳しい入国規制がなかったら、衝動的にこの場でこの子を引き取っていたかもしれない。いや、僕に引き取られなどしたら、それこそあっと言う間にのたれ死ぬに違いないから、そうでなくて良かったのだろうが、この子がまだ見ているであろう魅惑の視線に後ろ髪を引かれながらも、僕は大畑さんとマザー・ハウスをあとにしたのだった。はっきり言うと、またもや日本代表はあえなく敗れ去ってしまったのだった。
帰りに路地裏を歩いていると、空地で子供たちが大勢遊んでいた。面白そうだからしばらく見物していると、柔らかい小さな庭球で裸足のままクリケットをしたり、サッカーをしたり、いたずら坊主が牛を曳いて来てみんなを蹴散らしたりと、やたらに楽しそうだ。そのうちクリケットをしていたガキ大将がやって来て、僕に一緒にやろうと言ってきた。
「ルール知らん」
と言うと、
「じゃあフットボールしよう」
ときた。靴擦れが痛いし、ほんとは疲れるから嫌なだけなのだが、
「やって見せてくれ。あとで仲間に加わる」
と答えると、裸足のわんぱく坊主どものサッカーの試合が始まった。
しばらく見物してから、僕は写真を撮ろうとした。たちまち空地じゅうにいた子供たちが全員(五十人はいたと思う)寄り集まって来て、写真に写ろうとみんなが殺到した。そんなに写真に写るのが面白いことなのか? 僕なんか写真に写るのはどちらかと言うと嫌いなのだが、まあいい、撮ってやろう。このガキどものガキパワーは僕の写真心を激しく揺さぶったのだから(実はそんなもの全然持ち合わせてはいないけど)。この何とも言えない土埃の臭いがぷんぷんするするガキども。まるで俺のガキの頃ではないか!
この中にみんなから『モンキー』と呼ばれるひょうきん者がいて、こいつがまたみんなが囃し立てると調子に乗り、次々とカメラの前で得体の知れないポーズを取ってみせた。それがエスカレートして、しまいには写真に写してはいけないモノまで放り出してきたので、僕は辟易として、
「あっ、フィルム終わっちゃったよ」
とごまかしてカメラをしまった。近くにアイスクリームのワゴンを前にしたじいちゃんがちょうど座っていたので、アイスをごっそり買い込むと(これがほんとに安物で、舐めると舌がどぎつい天然色に変わった)、わんぱくモデルたちにギャラとして配った。
晩飯を食ったあと(激辛ダルショックがまだ残っていて、また『龍鳳』とかいう店で中華)、夜にサルベーション・アーミーの二階のロビーみたいな所で甘い菓子パンを食べながら大畑さんと駄べっていると、背中を蹴られた。振り向くと、頭をほぼ坊主にした白人のねえちゃんが座っていて、両脚をテーブルの上に投げ出している。ねえちゃんは、
「ごめん」
と口先だけで言った。相変わらずテーブルに脚を乗っけてふんぞり返った姿勢のままだ。
「どういたしまして」
それで終わりでいいはずなのに、僕が菓子パンを食いながら大畑さんと日本語でまた駄べっていると、
「ホワイト・クリームは不味い。げぇー」
なんて言いながら横から出しゃばってきて、ゲロを吐く真似をしてみせやがる。そうかよ。だったら食うなよ。俺がいつこれをあんたにやるって言った? 誰もあんたの好みなんか訊いてないだろが。人の食ってる物にケチつけたがるこのねえちゃんに作り笑いを返すと、僕は再び大畑さんと日本語で喋りだした。
ところがこのねえちゃん、話し相手がいなくて暇を持て余してるみたいで、やたらと絡んでくる。しょうがない、少しは相手してやるかーと、僕は今日早速身に着けたボランティア精神を発揮して、インド人女性が額の真ん中に付けるアクセサリーをこのねえちゃんも付けてたものだから(当然のことながらちっとも似合ってなかったけど)、
「それイカすねえ。どうやってくっつけるの?」
と英語で訊いてやると、
「あんた、英語できないの?」
とぬかしやがった。どこまでもムカつくねえちゃんだ。やがて仲間のねえちゃん(こっちはまとも)がやって来ると、こっちのことはすっかり忘れて二人でベラベラ喋り始めた。全て猛烈な速さのドイツ語だった。僕は、『学生の頃ドイツ文学を専攻していたくせしてドイツ語が一言も聞き取れない』という特技を持っている。この狂ったマシンガンの乱射のような会話が一言も聞き取れぬ故にドイツ語なのだとわかっただけのことだ。なんだ、このムカつく坊主のあまぁ、ネオナチかぁ。
「そろそろ寝みましょうか」
ムカついたので、僕は大畑さんに言った。今日の安眠のためにも、部屋に戻る前にこの金髪坊主のネオナチねえちゃんに一発反撃してぎゃふんと言わせ(西洋人だから
"gyafun!" か?)、すっきりしてから眠りにつきたかったのだが、口ではとても敵いそうもないし、第一相手が見るからに恐ろしそうだったから、潔い態度が何より取り柄の僕は、諦めた。ドイツにも負けたか、くそぅー!
「ええ。明日、伊井田さんと会えるかどうかわからないから、ここでお別れの挨拶しときます」
大畑さんと僕は立ち上がると、日本風にお互い頭を何度もぺこぺこ下げ合いながら、笑顔を絶やすことなくいろいろと別れの言葉を交わし合った。すると途端にマシンガンの音がピタリとやんだ。どったの?
振り向くと、ネオナチねえちゃんとまともなねえちゃんの二人が、鳩が豆鉄砲食らったような顔して口をあんぐりと開けたまま、こっちをぽかんと見ている。なんでそんな顔するのか意味不明だが、恐らく西洋人にはこの『日本式回りくどい礼儀作法的別れの挨拶』が一体何をやっているのか理解できないのだろう。まるで『東洋の神秘的な儀式』とその青い眼には映ったのかもしれない。
国粋主義に走るのを止める気はないけど、よう、ネオナチのねえちゃんよ、インドを安旅行するつもりなら、少しくらいは異文化を理解しようとする目も持ちなよ、よぅ、ねえちゃんよぅ! ねえちゃんは依然として大口を全開にしたままだった。それを見ていると僕は、ねえちゃんの下品なでかい口の中にホワイト・クリームを思いっきり詰め込んでやりたくなった。
3月21日 晴 カルカッタ 〜 ガヤー
ホテルをチェックアウトすると、歩いてシアルダー駅まで行くつもりでいたが、入口の番人がタクシーを呼んでやると言って聞かない。わがままな奴め。50ルピーだと言う。もう少し若ければ確実に断っていただろうけど、まあいいや、楽しようと思い、呼んでもらうことにした。と言うより、番人はこっちがうんとも言わないうちに、手回しよく先に電話していたのだった。それであんなにしつこく乗れ乗れと勧めたのか。まあいいけど。
しかし駅に着くのが早すぎて、僕は時間を持て余してしまった。やっぱり歩いて来れば良かった。二時間くらい駅の構内をうろついたり、また外に出たり、何度も駅員に切符を見せてこの列車はまだ到着してないのかと尋ねたりしていた。
インドの列車には、『定刻通りに発車しない』という定評がある。僕は人を待たせるのは平気だが、待つことは大嫌いで、五分も待っているとたちまち厭になってしまう。普段の生活でも、無意識のうちに時計を何度も何度も見て時刻を確認したりしている。時間の浪費は平気でしているくせに、時間がもったいないとすぐに思ってしまったりするのだ。
この全身に染み着いているせこい『日本人的時間感覚』を、今回インドで徹底的に叩き直さねばならない。もっとも今となってみれば、インド滞在中に徹底的に叩き直され過ぎてしまい、日本に帰って来てからはあまりに時間にルーズになってしまって、これはこれで困っているのだが。
ところが驚いたことに、僕の乗るはずの列車は定刻通りに出発したのだ。始発駅だったということもあるかもしれない。ところがインドの列車は乗りにくい。こういう大きな駅だと特に列車がたくさん停まっていて、はっきりとした目印がないものだから、一体どれに乗っていいのかわからなくなってしまう。
駅員から、「あれです。もうすぐ出ますよ」と言われて慌てて荷物を引っつかんで走って行ったのはいいのだが、今度はどの車輌に乗り込めばいいのかわからない。
(註:インドの列車は、とりあえず乗り込んでから、自分の指定席がある車輌まで中を通って行くということがたいていできない。車輌と車輌を結ぶ通路がないから、それをするには一旦窓から屋根に上がり、隣の車輌へと飛び移り、再び窓から中に入り込むという、活劇まがいの冒険が必要となる)
切符を手にして捜していると、売り子たちが寄って来て、「あっちだ」「いやこっちだ」と親切に教えてくれるのはいいのだが、指差す方角がてんでばらばらだ。こういう時はポーターを雇うのが一番いいらしい。僕は結局ポーターの厄介になることは一度もなかったが、荷物を運んで欲しくなくても、自分の乗る列車を絶対に逃したくないのなら、プロであるポーターに自分の座席まで荷物を運んでもらうのが一番確実だろう。
駅に着いたら列車が動き出していたという最悪の場合、とりあえずどこでもいいから乗り込む。その車輌に自分の席がなかったら、次に停車した時にホームに降り、急いで次の車輌へと移って席を捜す。なかったらまた次の車輌を捜す。見つかるまでこれを繰り返す。(渡り鳥戦法)
しかしこれは大変な労力を費やすことになるので、最悪の場合の手段としてお薦めは、とりあえず乗り込む。そして運悪く自分の指定席がその車輌になかったら(やみくもに乗り込んだ場合はたぶん、ない)、指定席のことは潔く諦め、空いている荷棚(日本の列車の網棚に相当)がないか捜す。荷物で埋まっていればどけて、そこに上がってふんぞり返る。(乗っ鳥戦法)
(註:この日本にはない『荷棚の乗り方』については後ほど解説)
ともかく、幸いにも僕はインドでの最初の列車に辛うじて飛び乗ることができた。動き出した列車の中で切符を睨みながら自分の席を捜していると、インド人の客が席まで連れてってくれた。
カルカッタ近郊は人混みと小さな家の塊が多かったが、しばらく行くと大平原と刈田の跡ばかりになり、列車はかなりのスピードで走り始めた。たまに小山がぽこぽこっとあるものの、見渡す限りの平原に木がまばらに生えていたりするだけだ。
日が暮れると満月が顔を出し、晩の眺めも幻想的で素晴らしかった。結果としてそうなっただけだが、景色の見えない夜行列車にしなくて良かったと思った。カルカッタと違い、ガヤーに近づくと涼しくなってきた。
ここはどこにでも犬がいるが、列車に近寄って来て危なっかしい。外国人向けのホテルなどにはあるのだが、インドではゴミ箱というものを使わない。ゴミはその辺に投げ捨てる。家の中で出たゴミは窓から放り投げる。列車でも同じことだ。たぶん乗客が窓からポイポイ食い残しのゴミを投げ捨てるので、それをあさる癖がついてしまっているのだろう。
列車はしょっちゅう停車するし、その度に売り子たちが乗り込んで来てやかましかったが、窓から外を見ていると、前足の片方が失くなっている野良犬がいた。三本の足で器用に線路脇をひょこひょこ歩いて来て、何か食っている様子だったが、列車がゆるゆると動き出したというのに、レールを跨いで列車の下に入り込んでしまった。この野良犬は自殺志願者なのか? なにも僕の目の前でしなくても……。
しかし夜になってから妙な事件が起こった。たまたま僕の乗っている車輌の窓から見えたのだが、赤いサリーを着た女が一人、列車が停まっている隙に出口から降りて原っぱへと歩いて行った。それから列車が何度も汽笛を鳴らしだした。すると乗客たちがにわかに騒ぎ始め、みんな立ち上がって窓から外を眺めだしたのだ。
さっきの急に列車から降りてった赤サリーの女が何か秘密を握っているのかと僕は怪しんで、また窓の外を見てみたが、ところが女は暗がりで三人の女になって列車に戻って来た。この女は分身の術が使えるのか……! さては魔女か、それとも物の怪か! んー、一体どうなってんだろう? それになんで乗客たちは騒いでるんだろう? さっぱり訳がわからない。
魔法使いサリーの代わりに列車に乗り込んで来た分身女たちは、着ているサリーの色は違ってるし、そうすると降りてった魔法使い赤サリーはこんなだだっ広い平原のどこへ行ったのだろう? 満月の月明かりはあるものの、僕の両目ではあの謎の魔女を再び見つけることはできなかった。もしかすると女忍び『くノ一』の源流がここにあるのかもしれない。
と、間抜けな推理をあれこれとしているうちに、やがて列車はゆるゆると動き出したのだが、少し先に警官らしき者が何人もいて、原っぱを頻りに懐中電灯で照らしていた。一体あれは何だったんだろう? あの女は警察に追われていたのだろうか? 「がんばれ、サリーちゃん!」
インドの列車は何にもない所でもよく停車するし、そんな時に人が乗り降りしたりもままある。あの女は警察と何も関係ないのかもしれないが、周りの乗客たちが何を言っているのか言葉がまるでわからないから、全くの謎のままで終わってしまった。
「マハリぃ〜クマハぁ〜リタヤンバラヤンヤンヤン♪」
僕の頭の中で、メロディ付きの呪文の言葉がいつまでも鳴り続けていた。とにかく「がんばれ、サリーちゃん!!」上手く逃げおおせろよ……。
インドでは列車に乗るのも一苦労だが、降りるのもまた難しい。何しろ駅に到着しても、車内アナウンス一つしてくれない。夜行の寝台だと、目的の駅が近づくと車掌が起こしに来てくれるのだが、寝台でないとしてくれない。ましてや車内が混んでいるからそれも不可能だろう。駅に着きそうになったら目を皿のようにして外を見ていなくてはならない。
それでも駅名の看板がない場合もあるし、あってもインドの文字だけで書かれていたり、英語で表示されていても、その看板が列車に対して垂直に立てられていたりして、うっかりしていると裏側のインドの文字しか見えなかったりする。ここは何駅だと乗客に訊いても、たいていみんな自分の乗り降りしない駅のことは知らない。
ガヤーには二時間以上遅れて到着した。列車の中の人とはほとんど言葉も通じず、約十一時間列車の中に座り続けているのはさすがにつまらなくなっていた。僕はその時座席でうとうとしてしまっていた。ところが向かいの座席でじっとしかめっ面のまま何も言わずに座り続けていたおじさんが、ガヤー駅に到着しかけた頃に僕を起こしてくれて、そればかりかわざわざ僕の荷物まで引き出してくれたのだった。
列車に乗り込んで席に着く時に、「ガヤー、ガヤー」と周りの人に言っといて良かった。それにしてもこのおじさん、その時は全く無反応だったのだが、きっちり向かいの外国人の降りる駅を心に留めていてくれたのだ。他の「よしよし」と笑顔で頷いてた人たちは、そんなことすっかり忘れてるみたいだった。インドにおいても『人は見掛けによらない』ということわざは当てはまったようだ。無愛想なおじさんのお蔭で、僕は初めての列車で無事に目的地に到着することができた。
駅から出ると、出迎えのM氏が(別に出迎えを頼んでいたわけではない)声をかけてきて、そのまま立ち止まりもせずに駅前のホテル・シャクーンへと連れて行ってくれた。ダブルルーム100ルピーだと言うので、二泊頼んだ。ターリーとコーヒーを持って来てもらったが、かなり安かった。都市部とは物価にかなり格差があるようだ。インドを安旅行すると、宿泊費より一日の飲食費の方が高くつくことになると思うが、食費も抑えたければ、この『ターリー』(定食)をよく食べるようにするといいかもしれない。
南インドへ行くと、この呼び名が『ミールス』になる。まあ簡単に言うとやはりカレーなのだが、ライスとチャパティ、あるいはそのどちらかがついていて、いくらでもお代わりできる。僕はターリーの時はいつもチャパティとダルを残してしまっていたが。
だがこのホテルのマネジャーMも、実は詐欺師の一味なのであった。嗚呼、どこへ行っても悪徳インド人詐欺師とカモ日本人旅行者との因縁の対決は果てしなく続くのか……。
 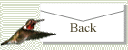
|